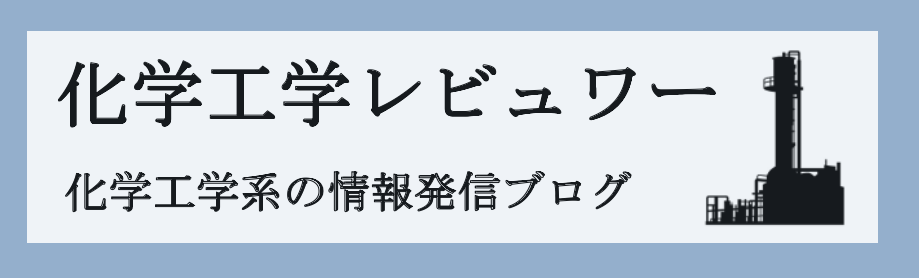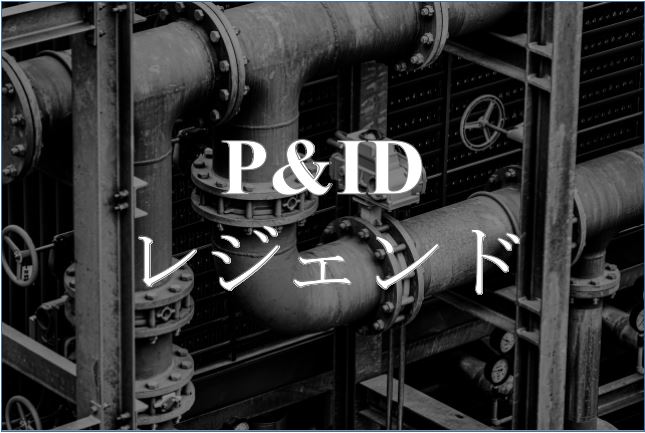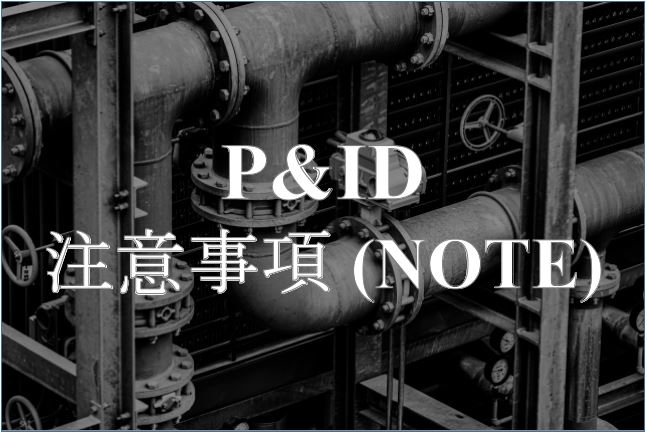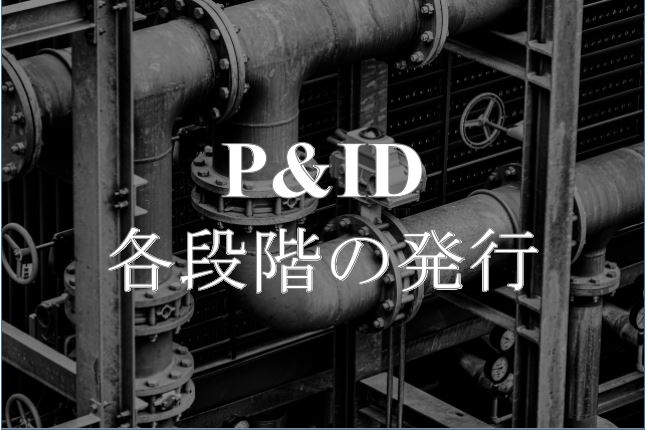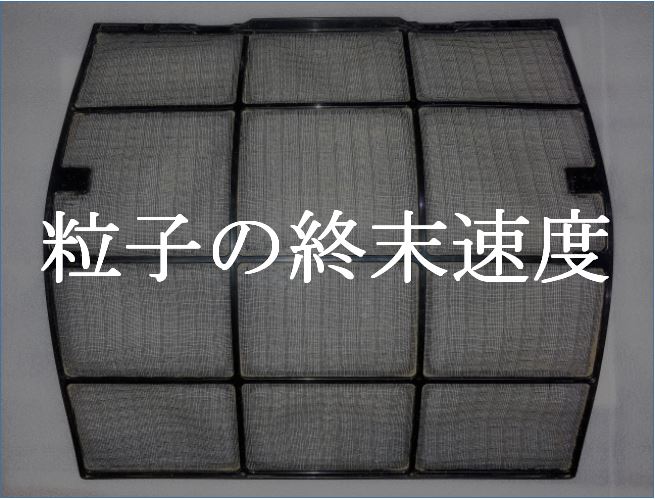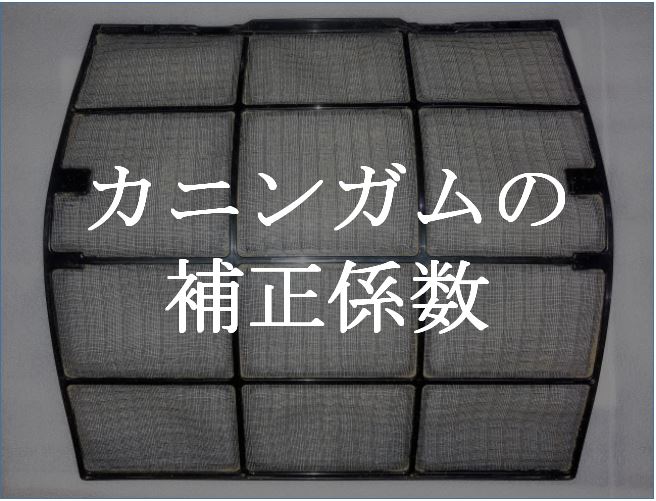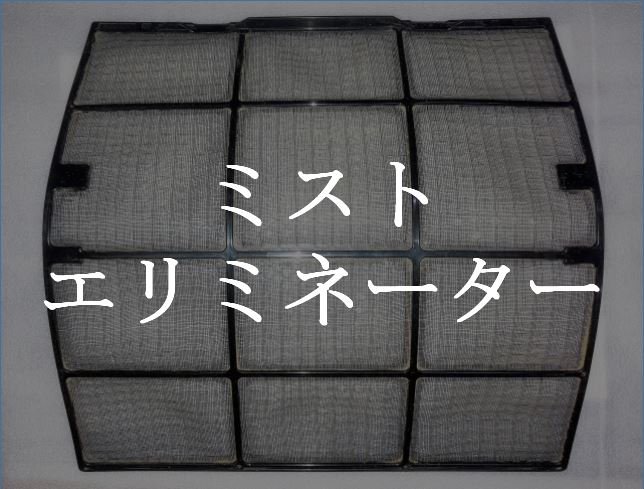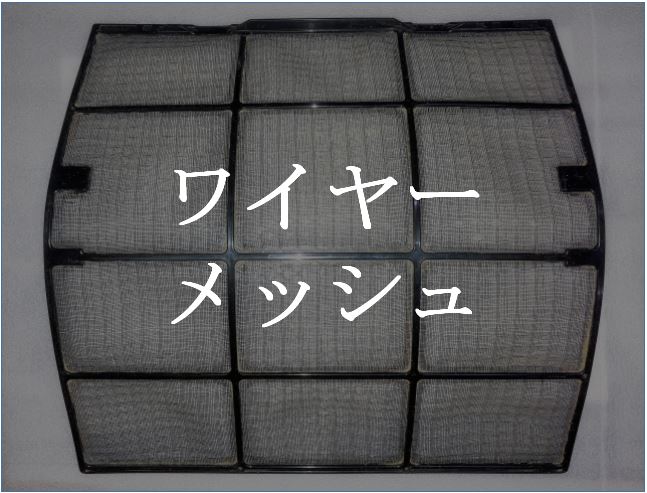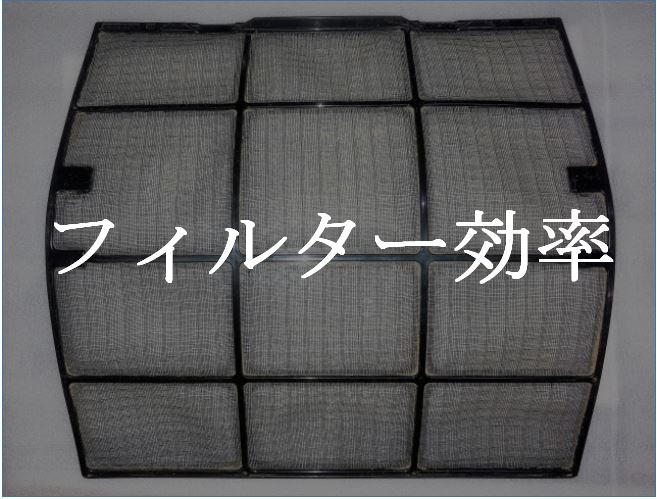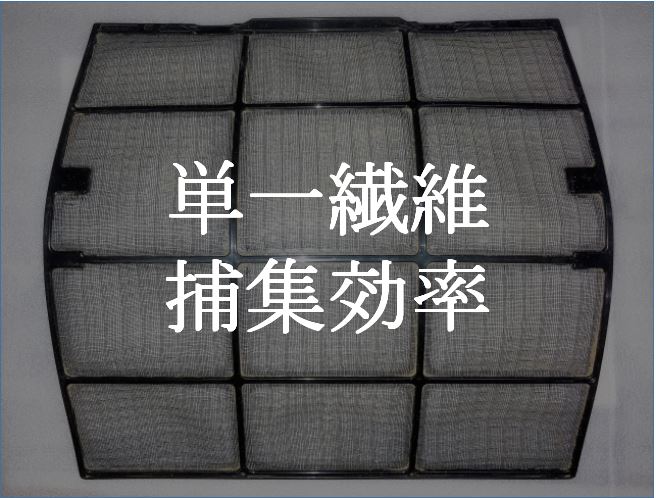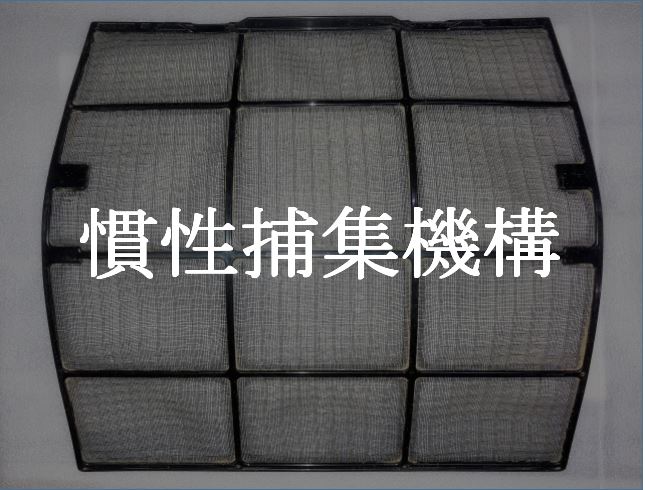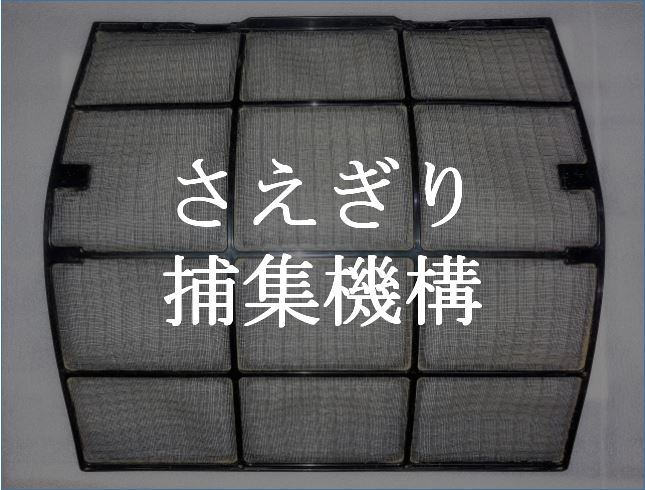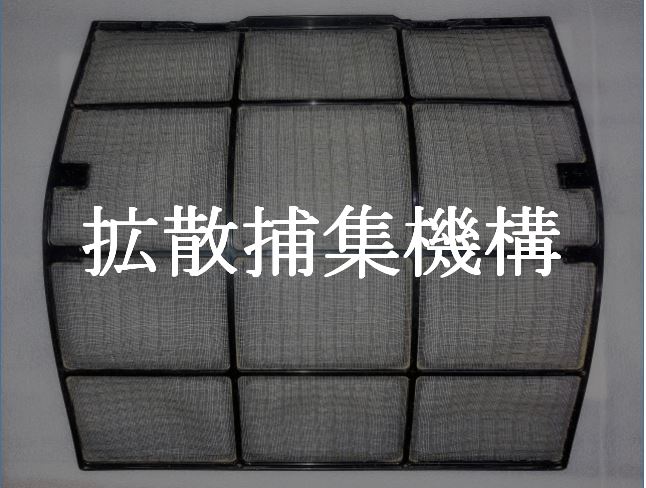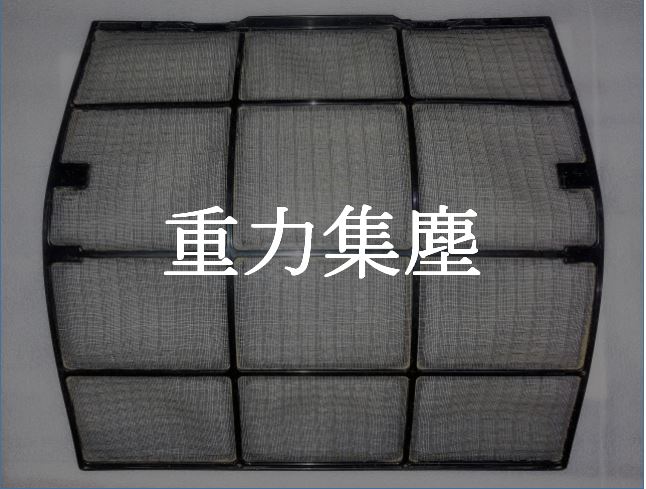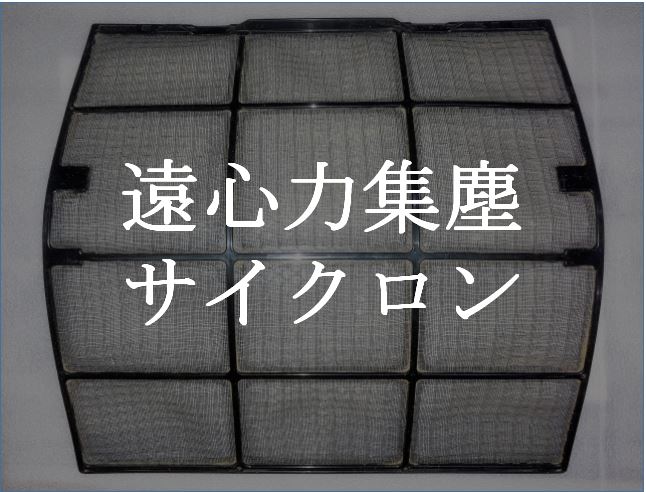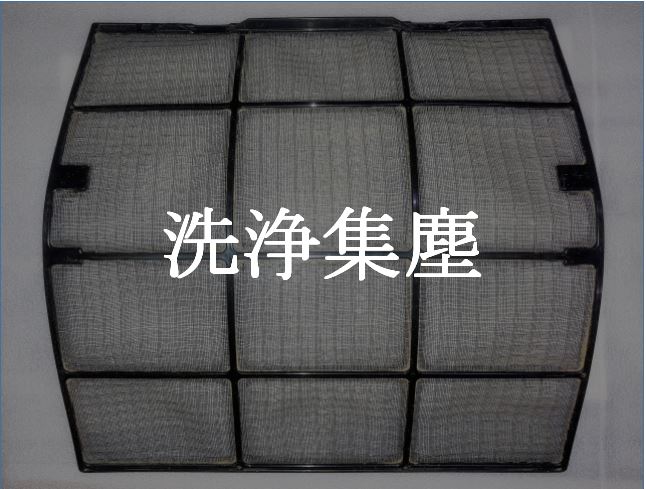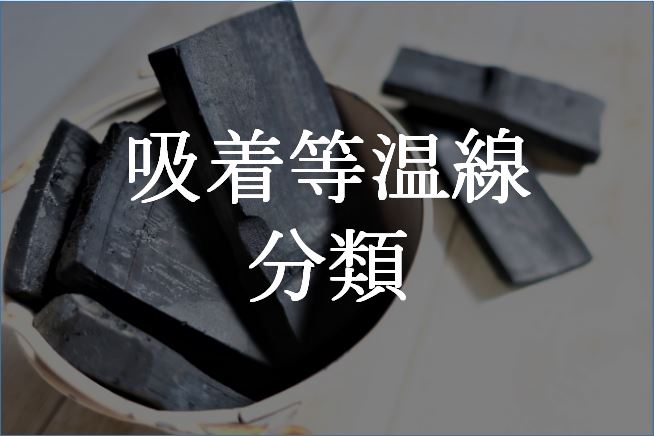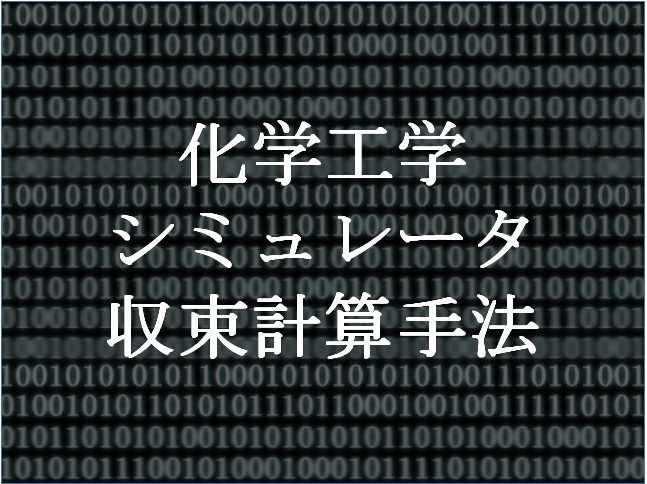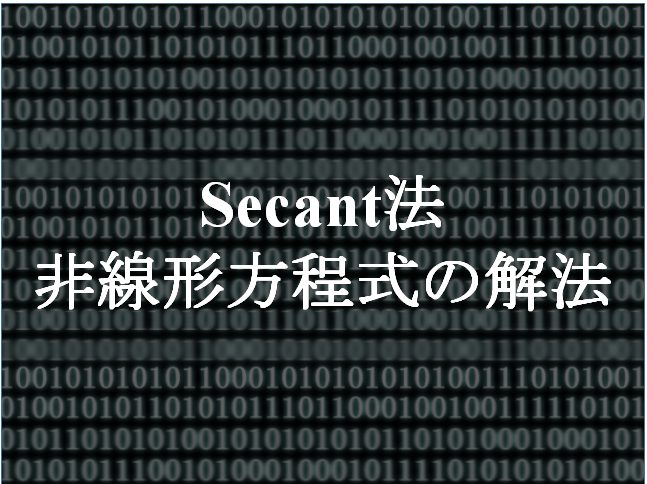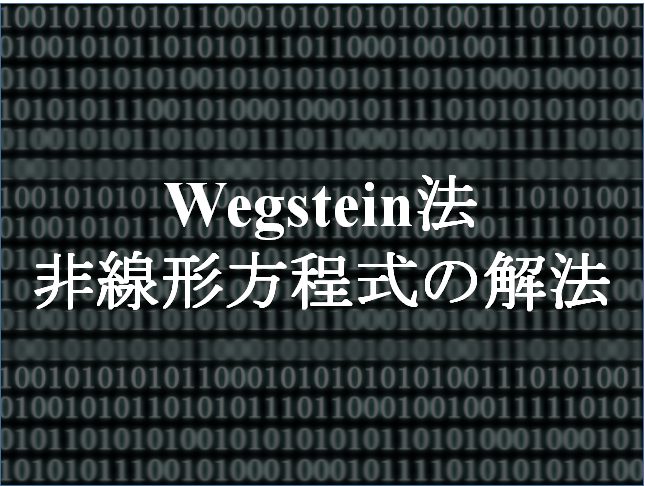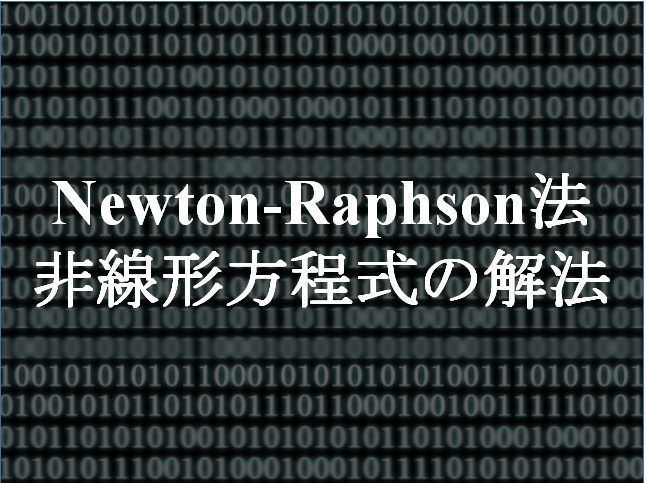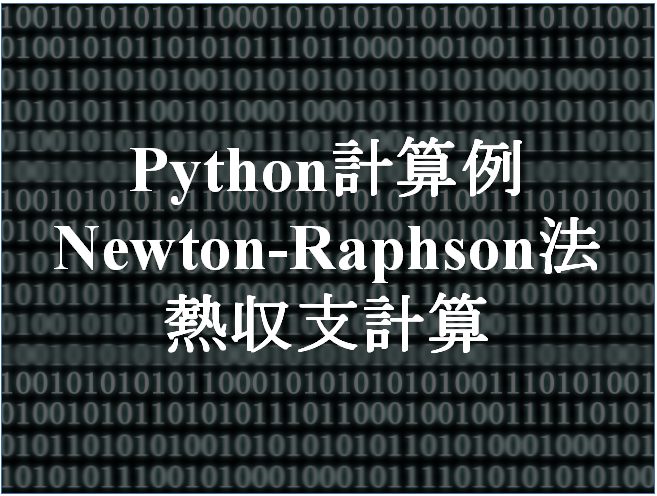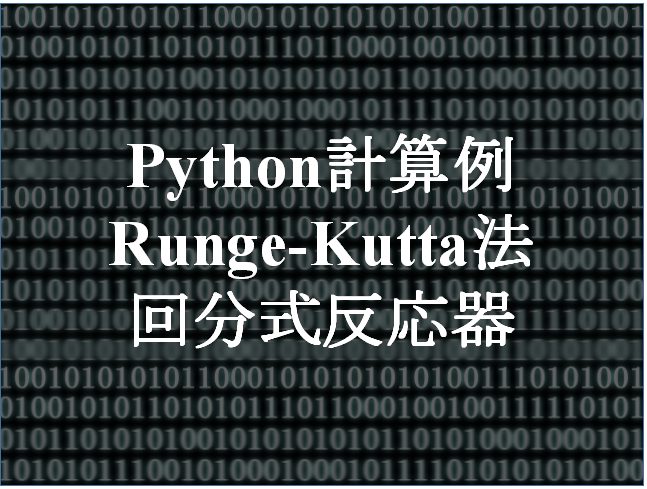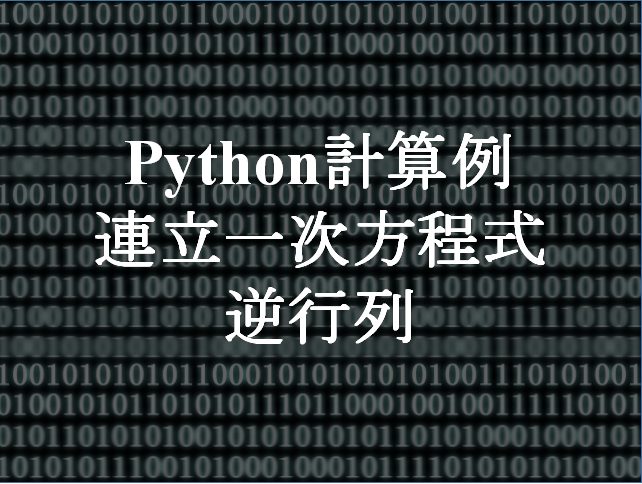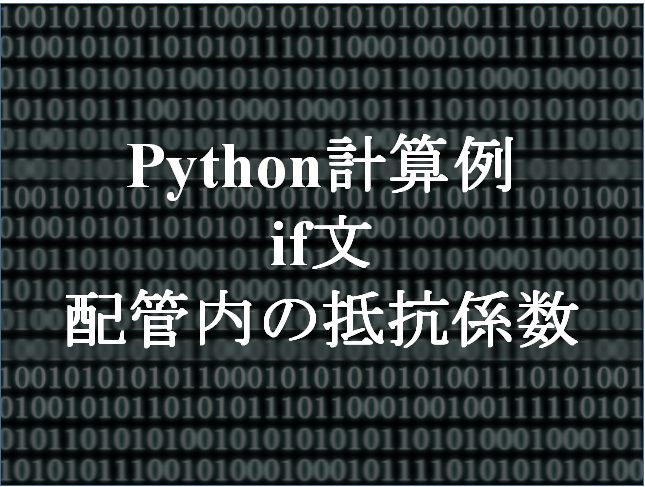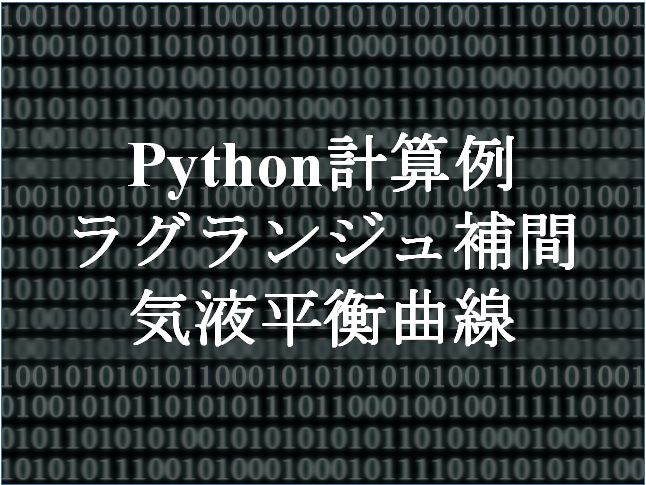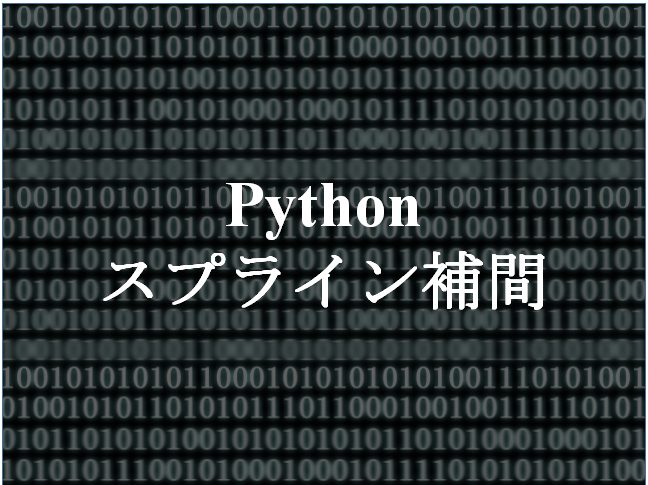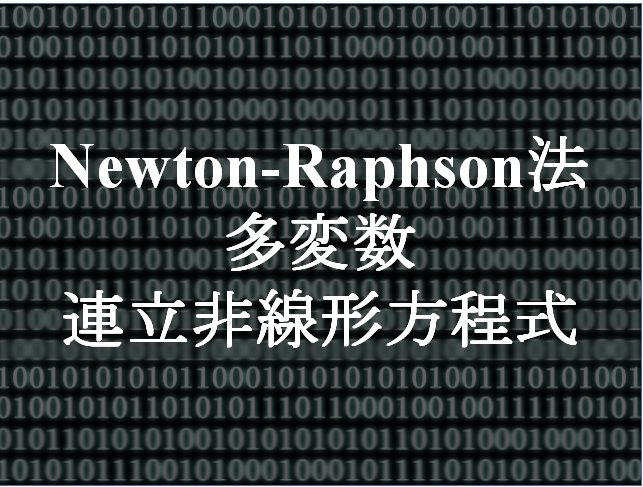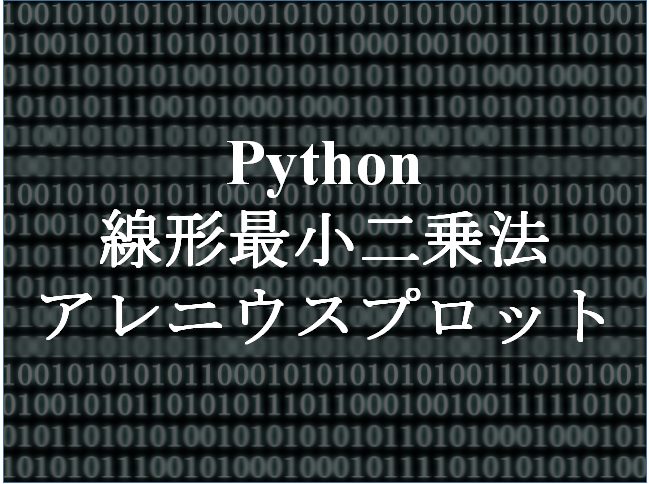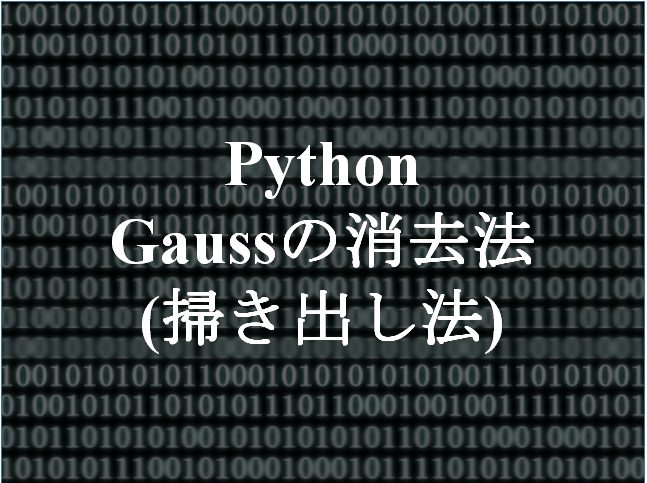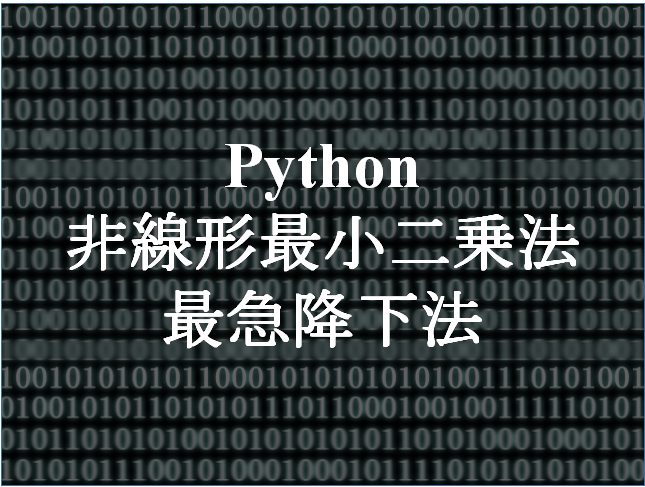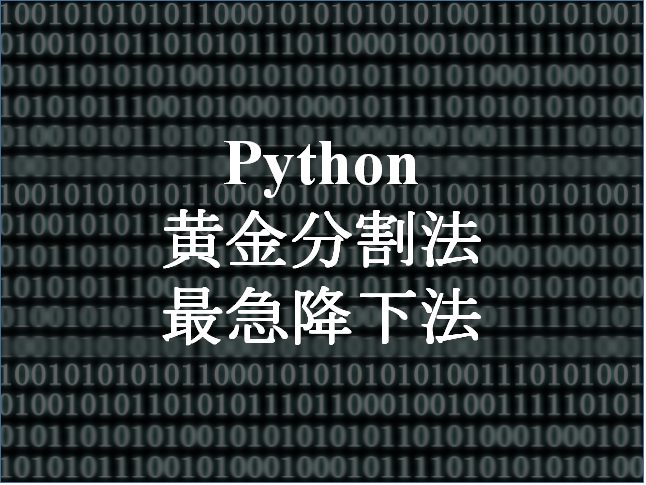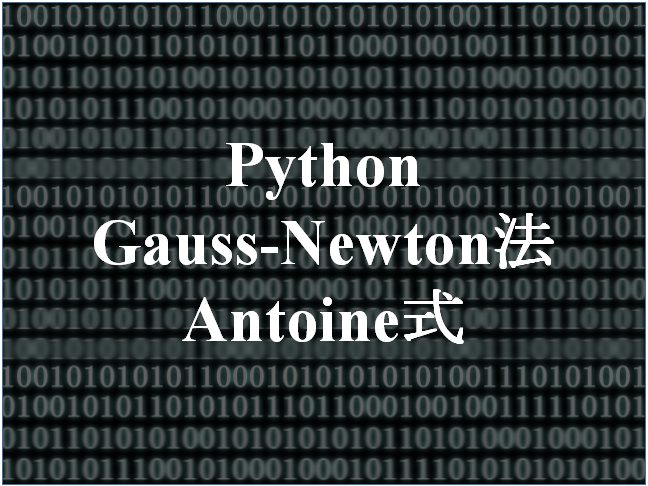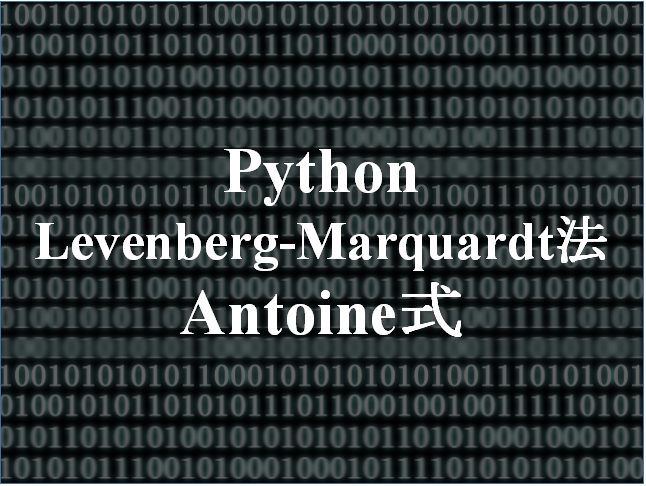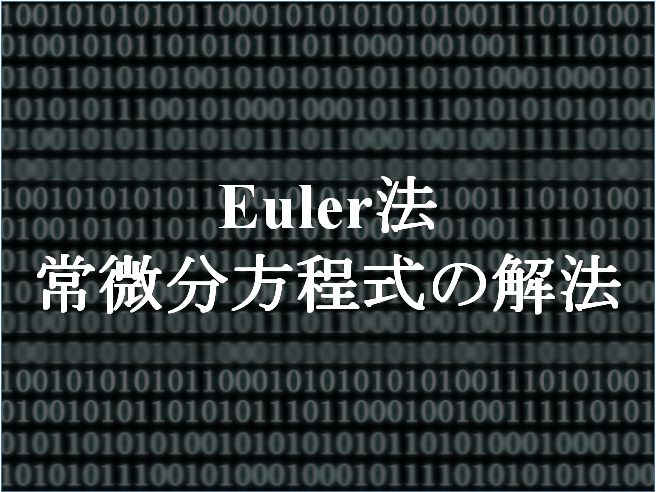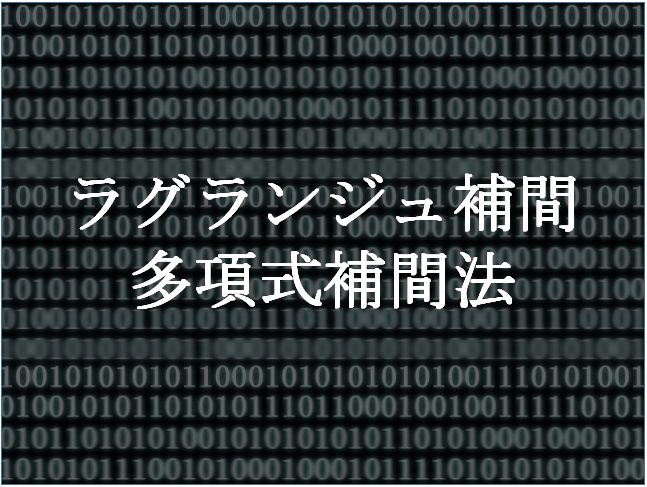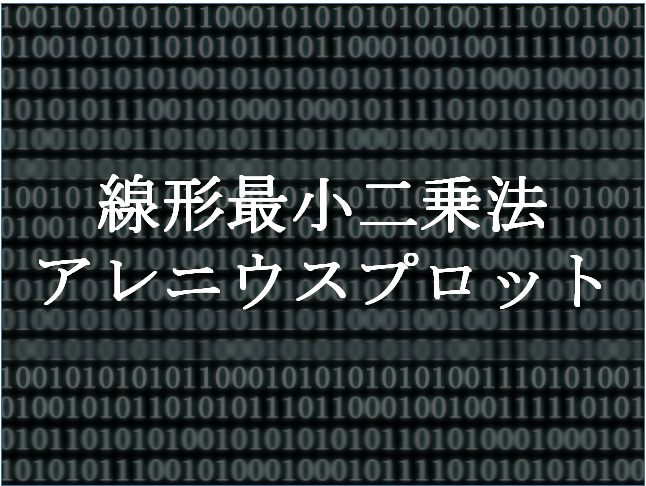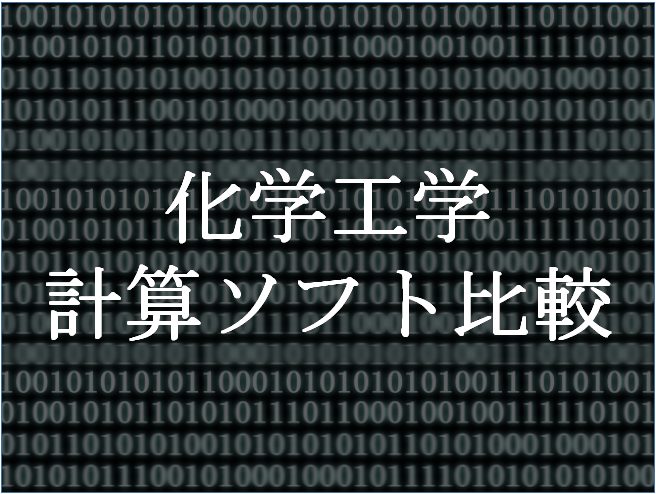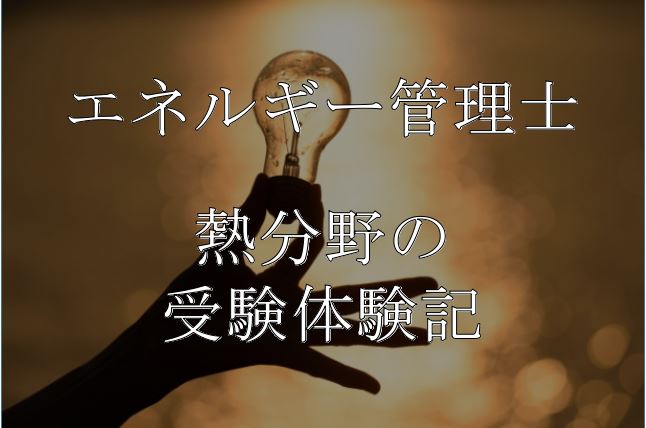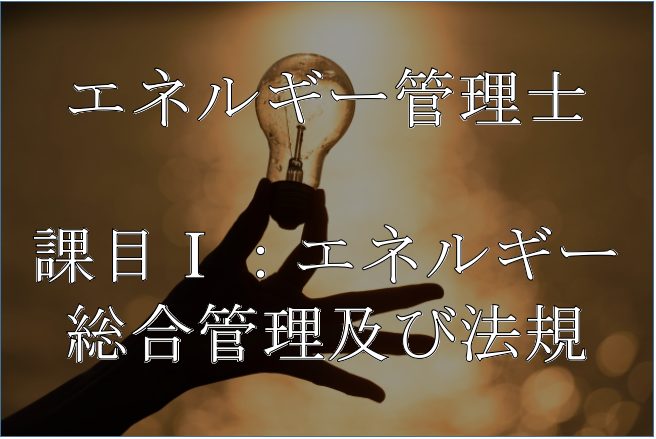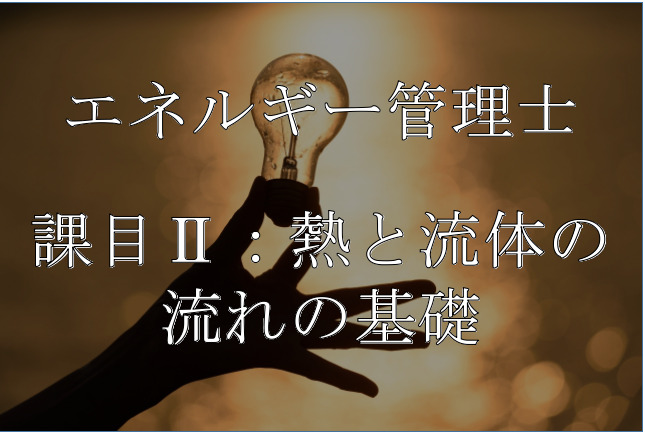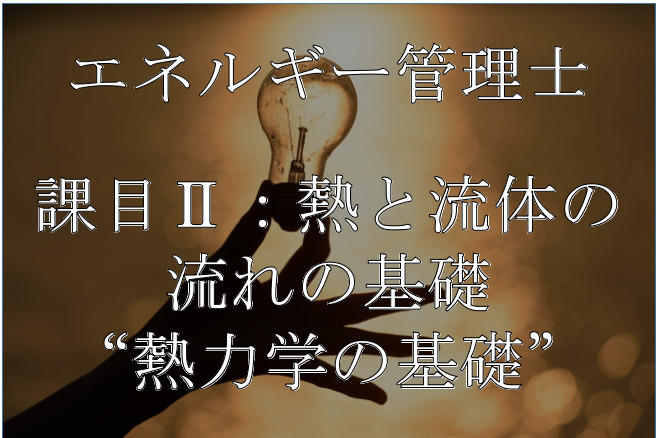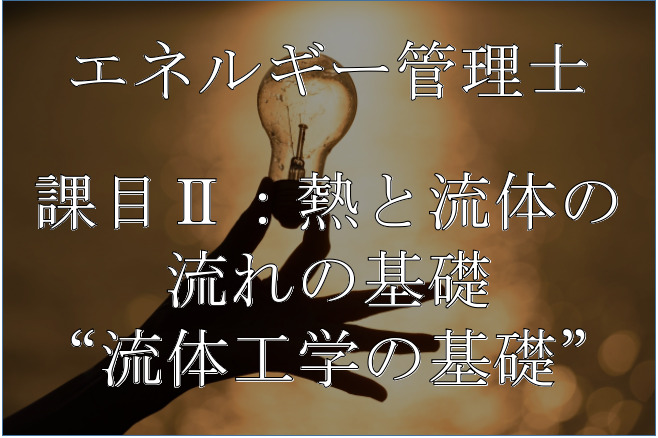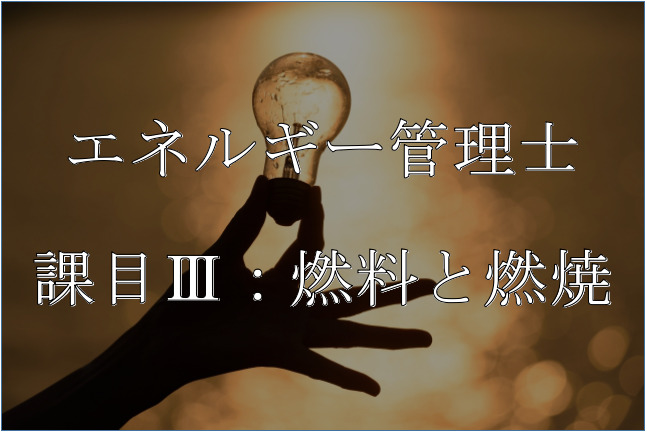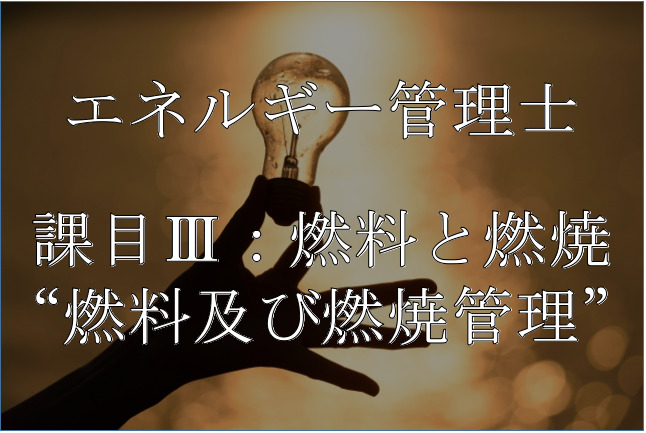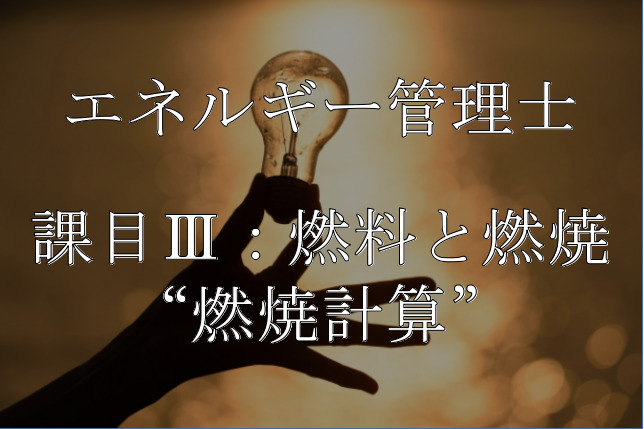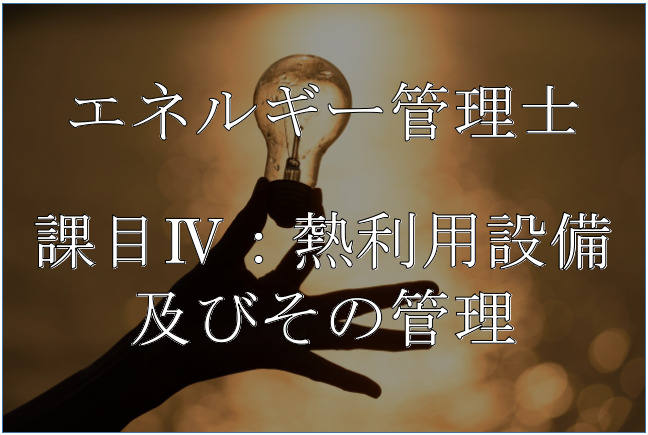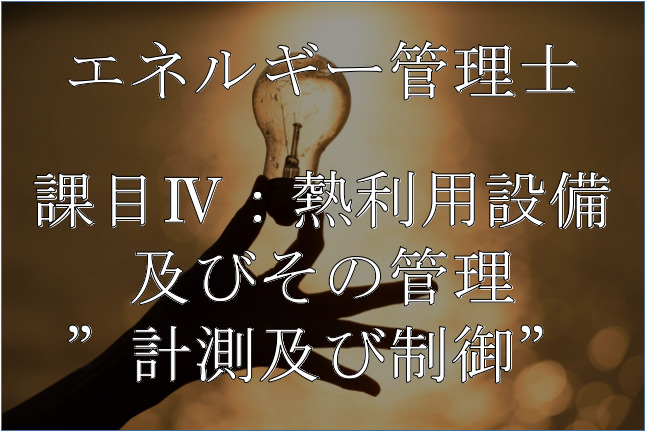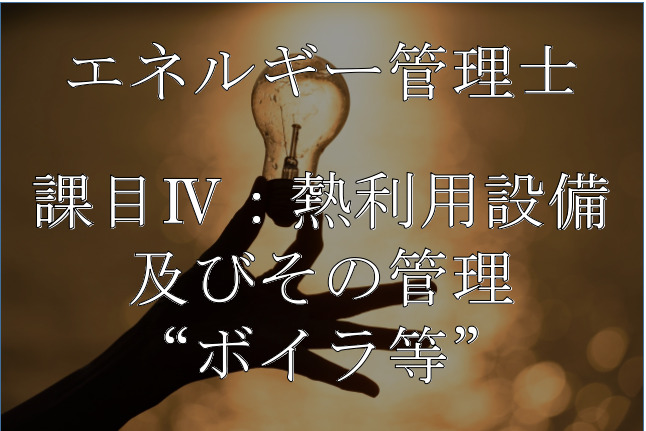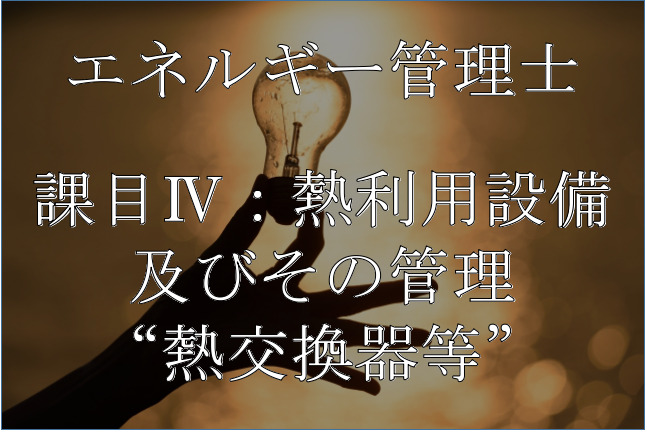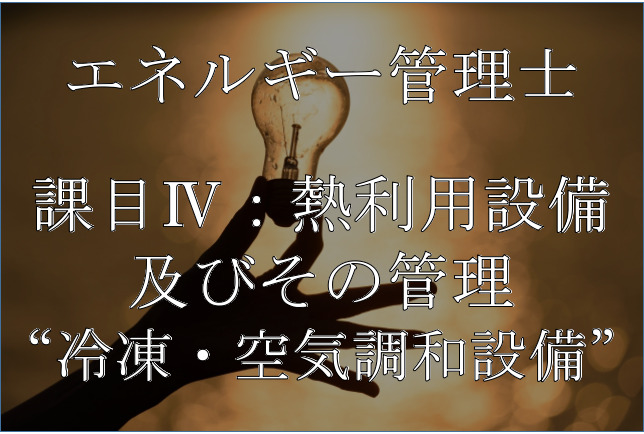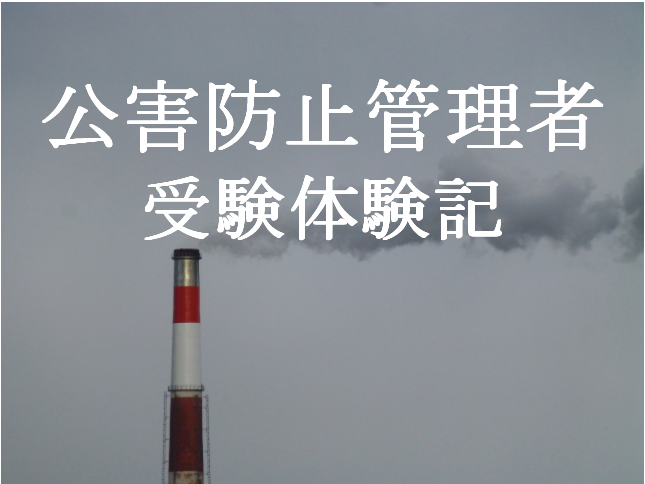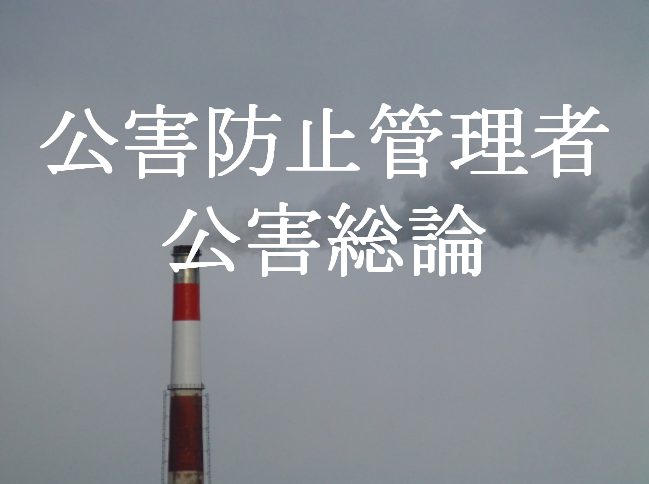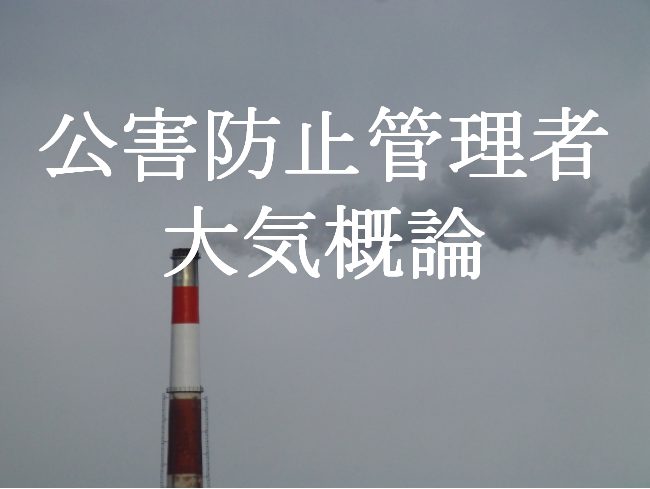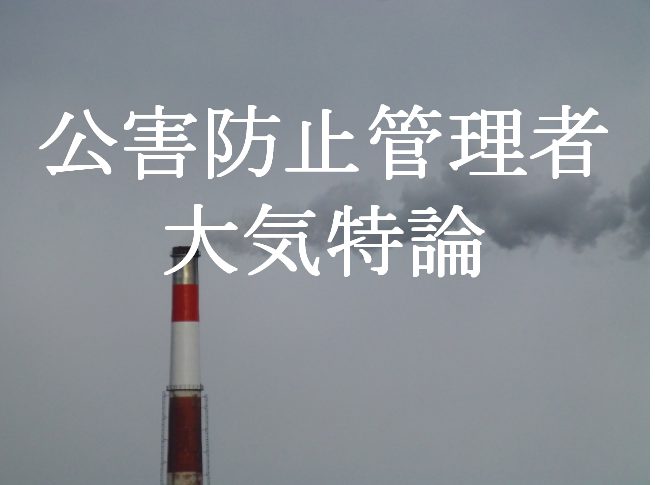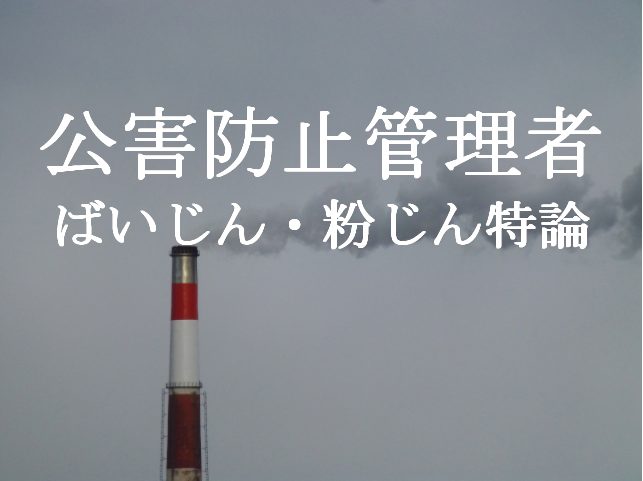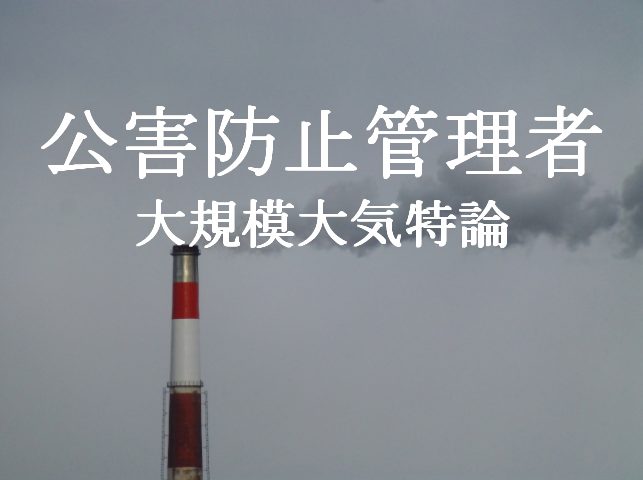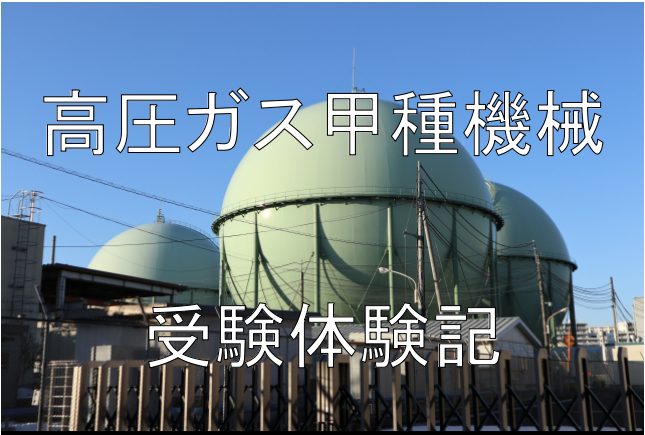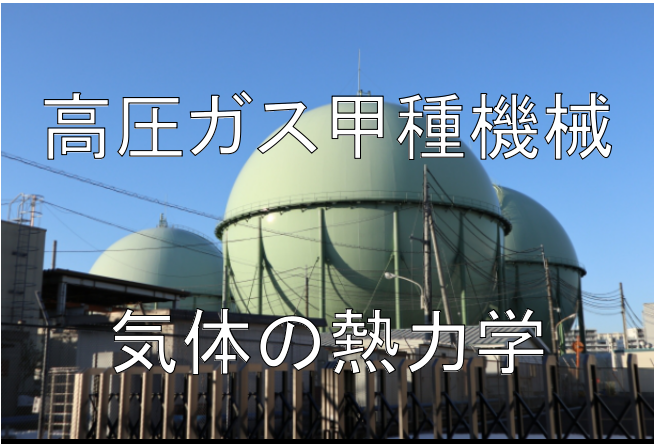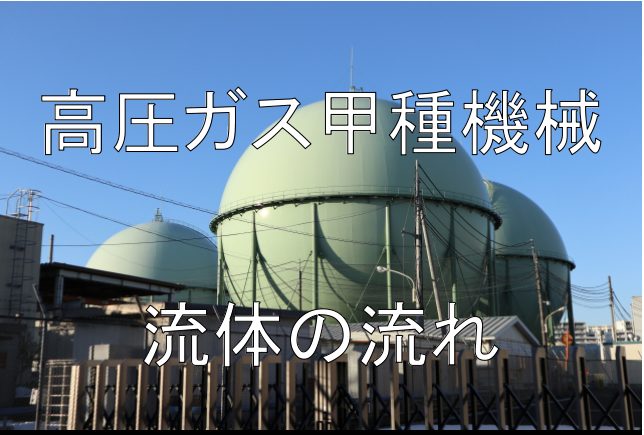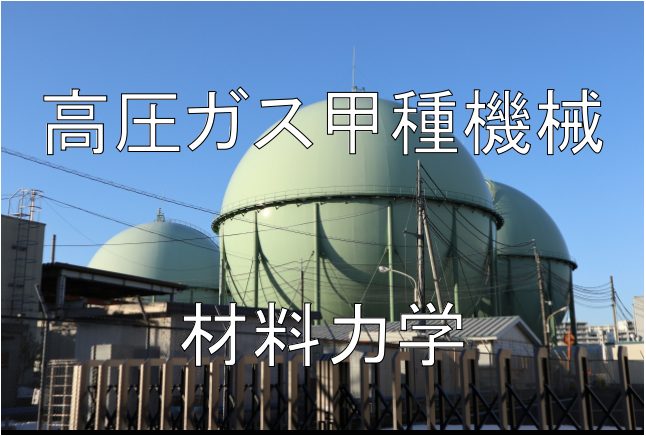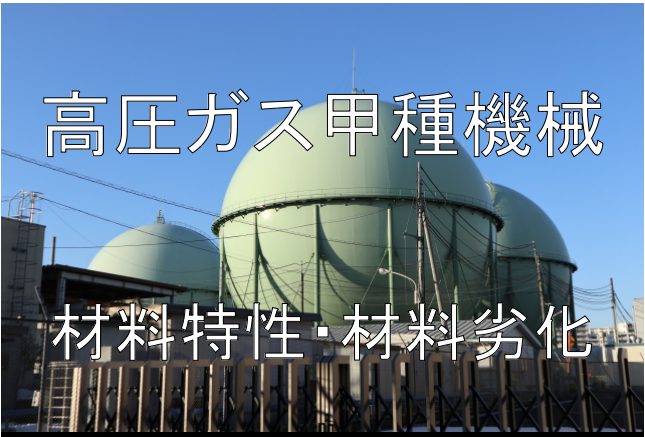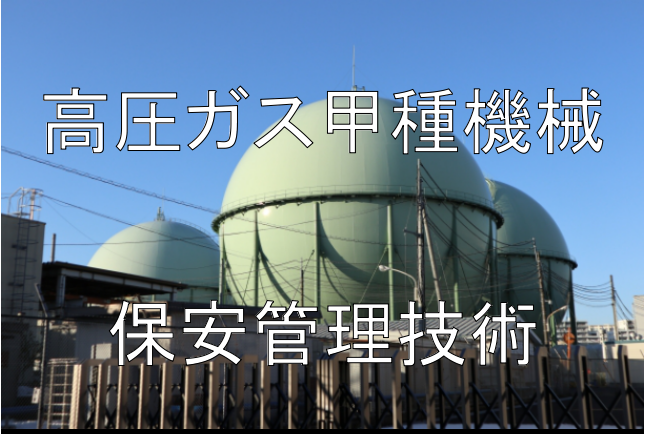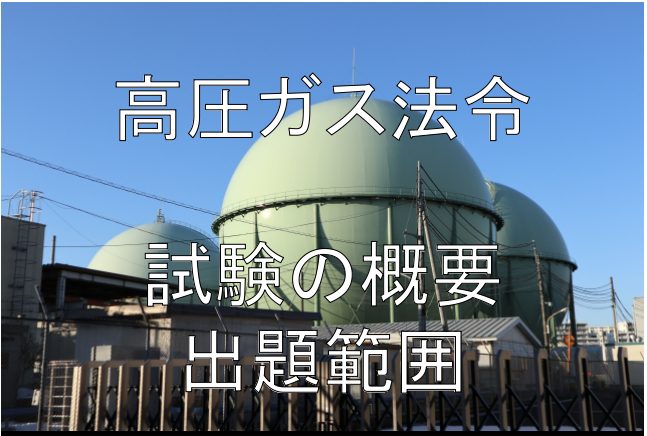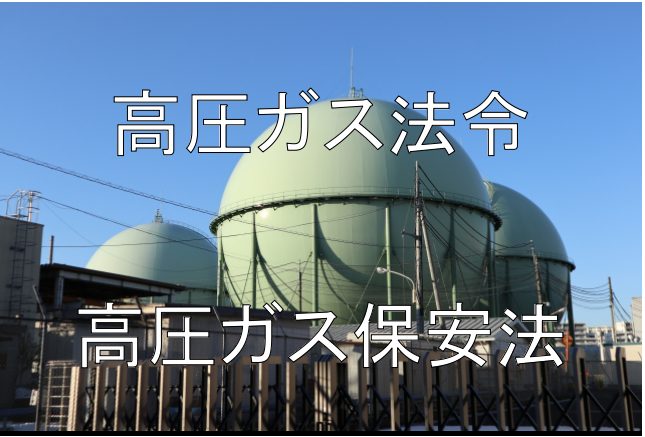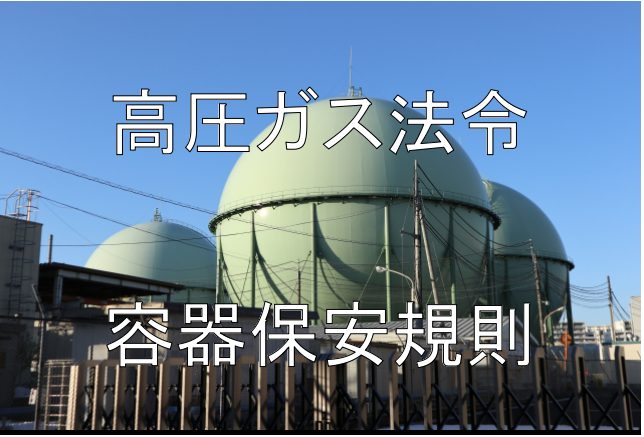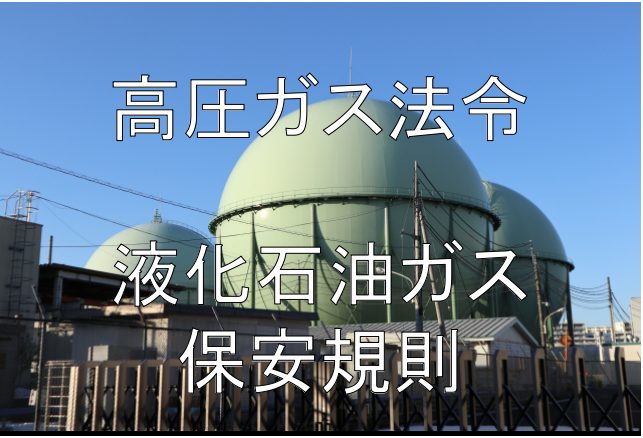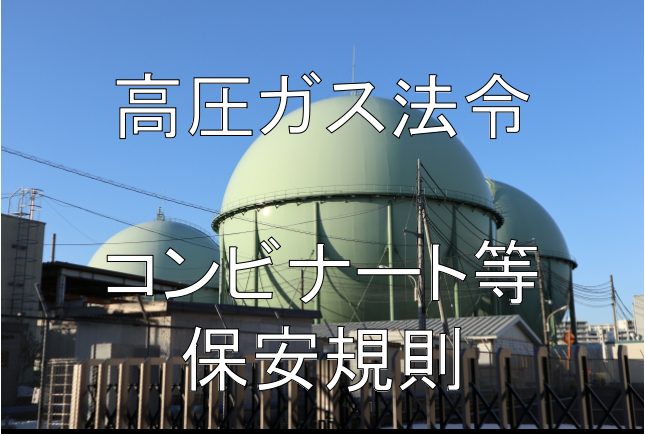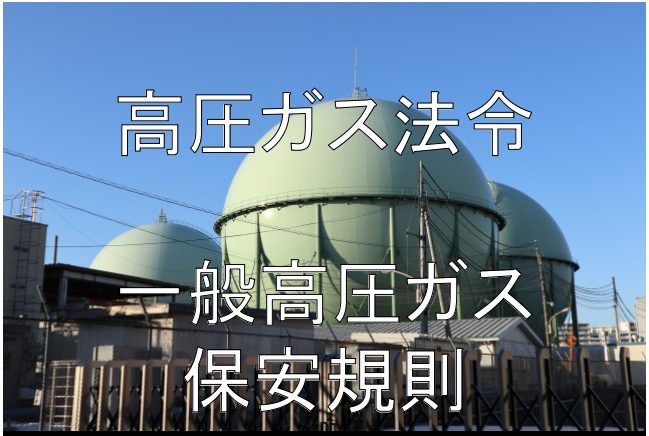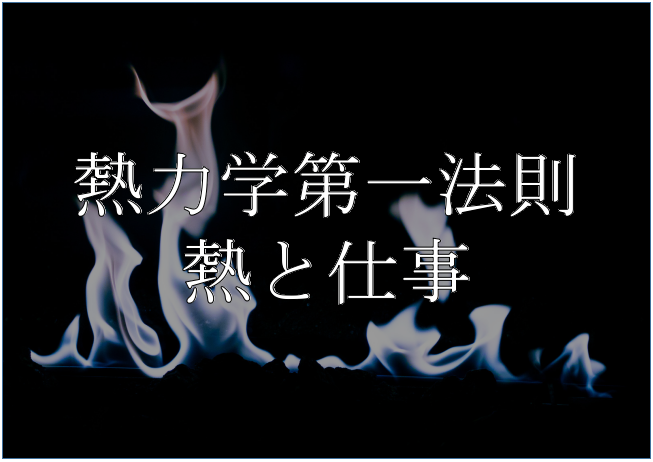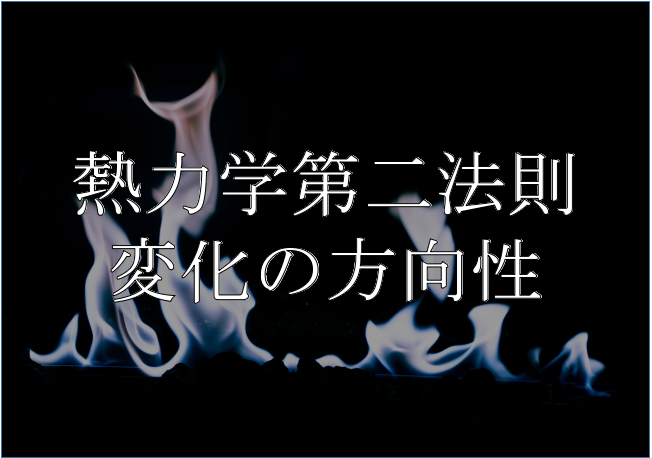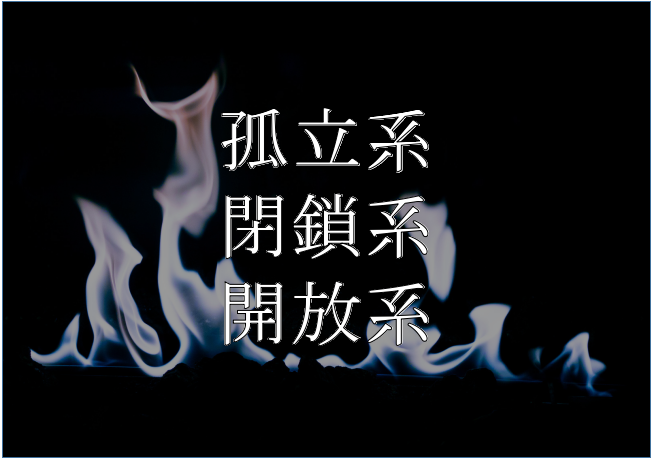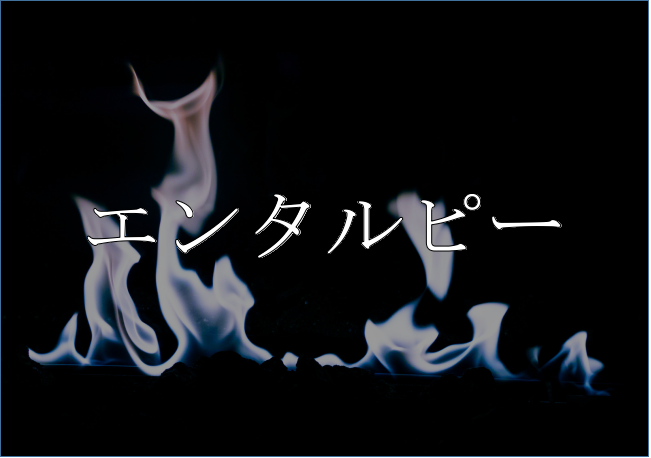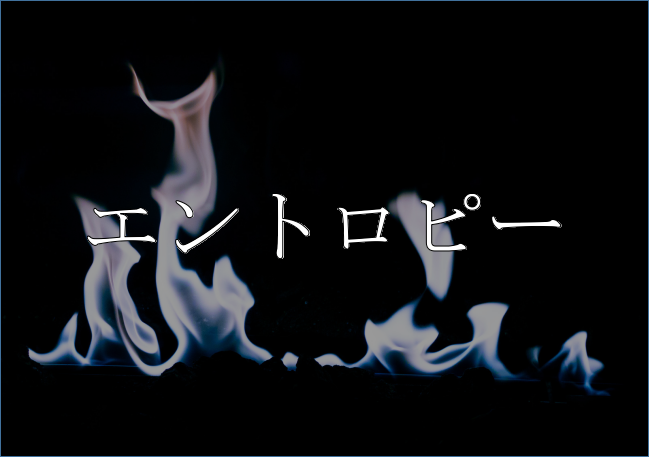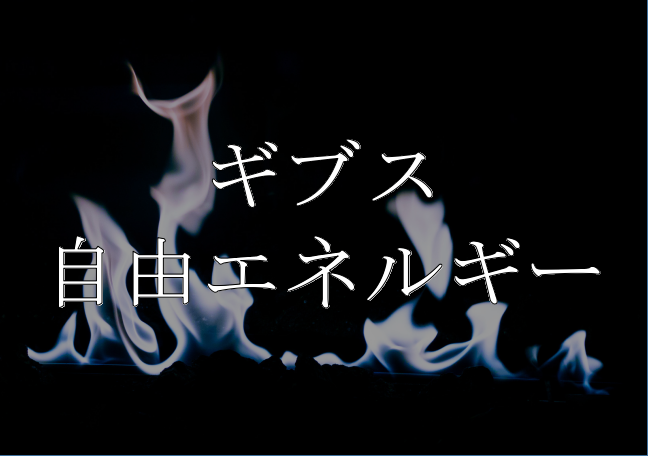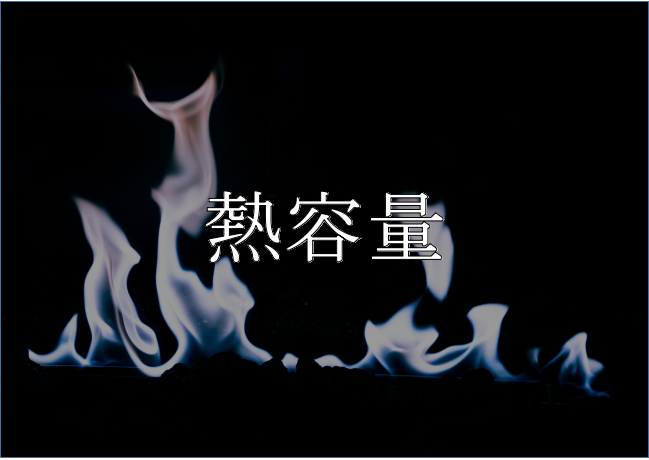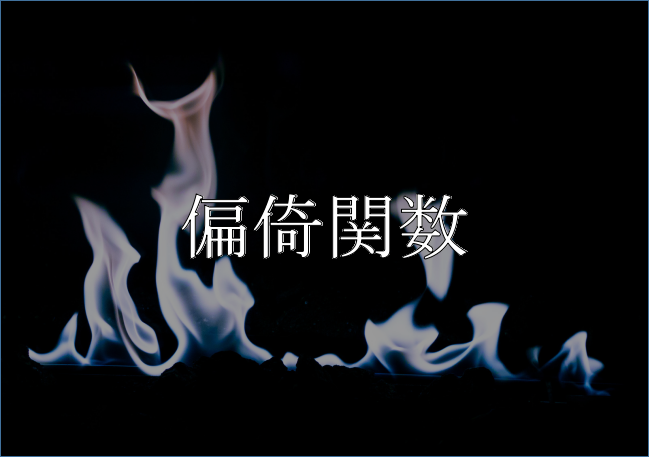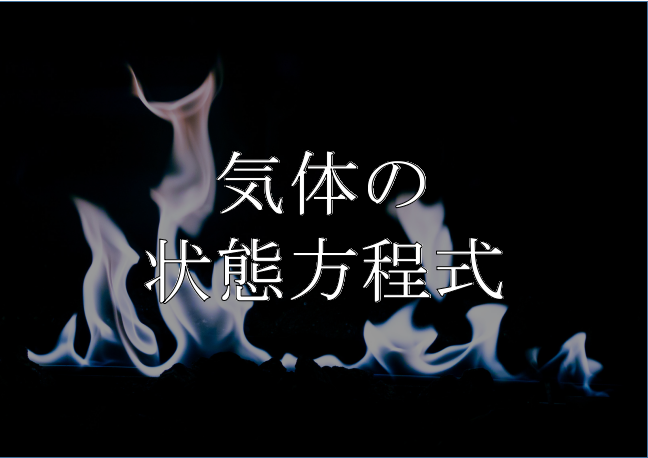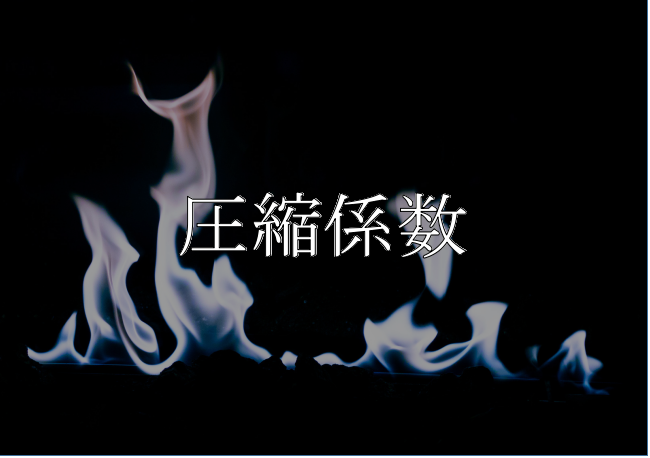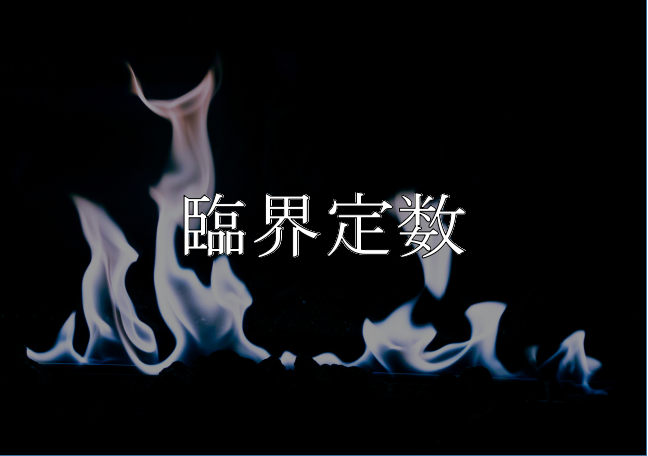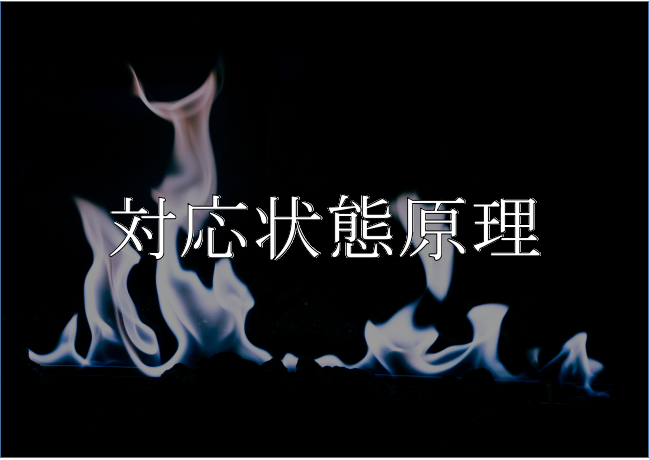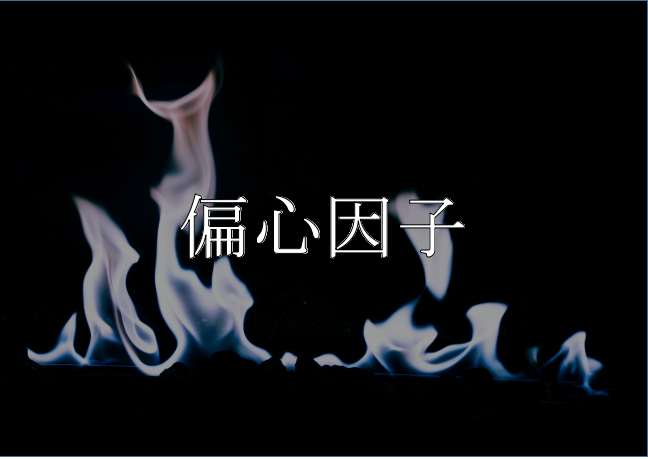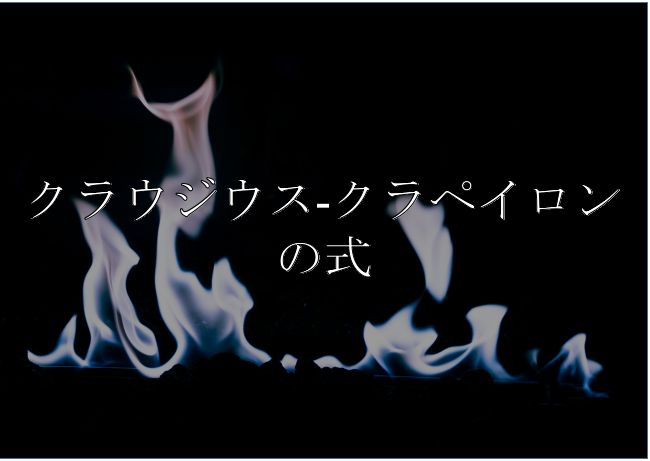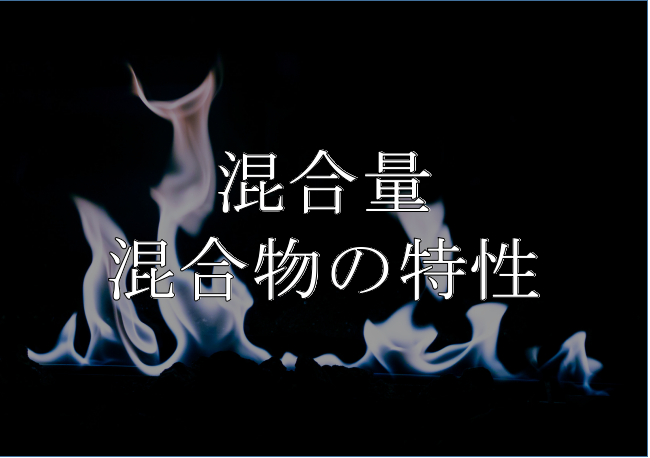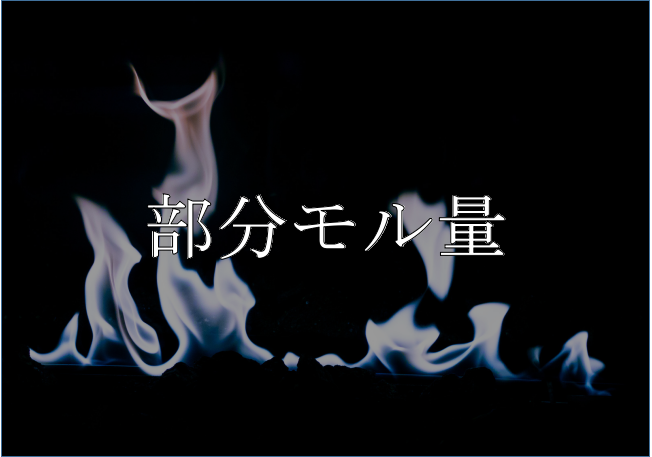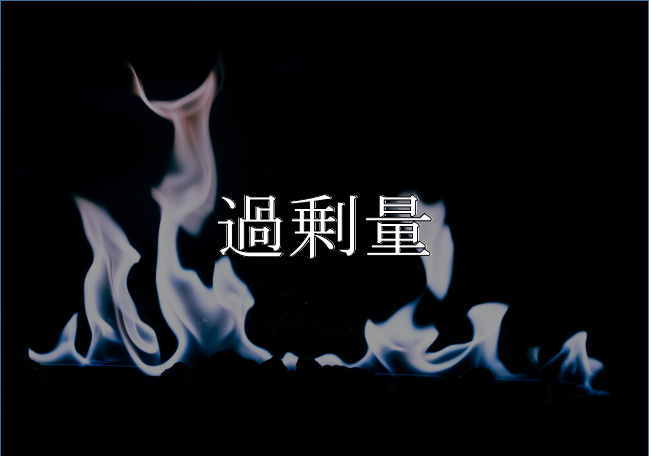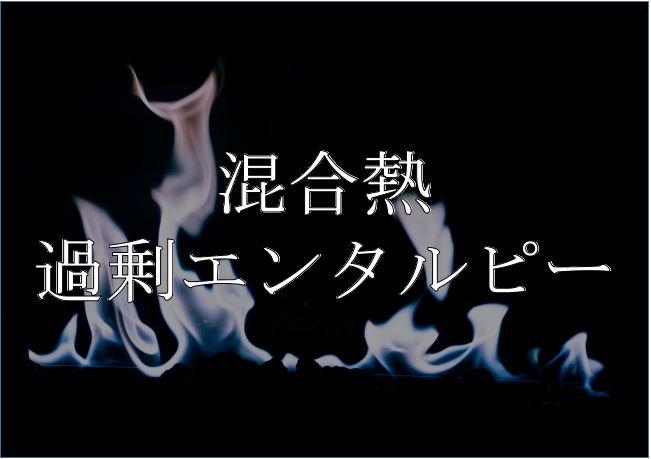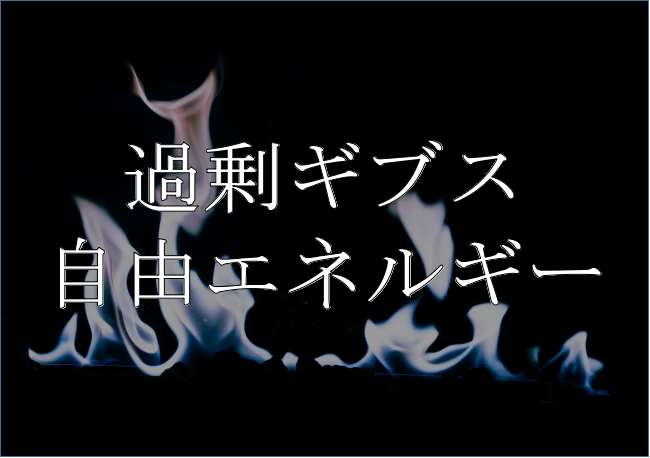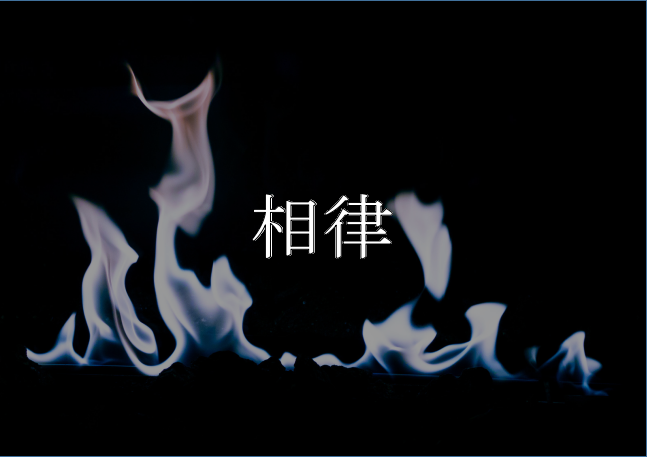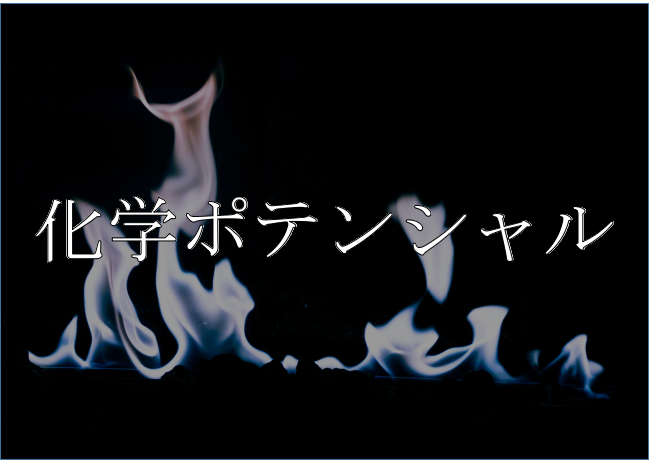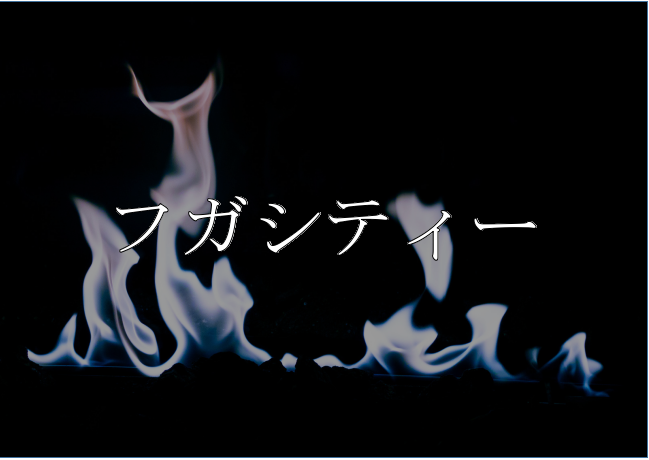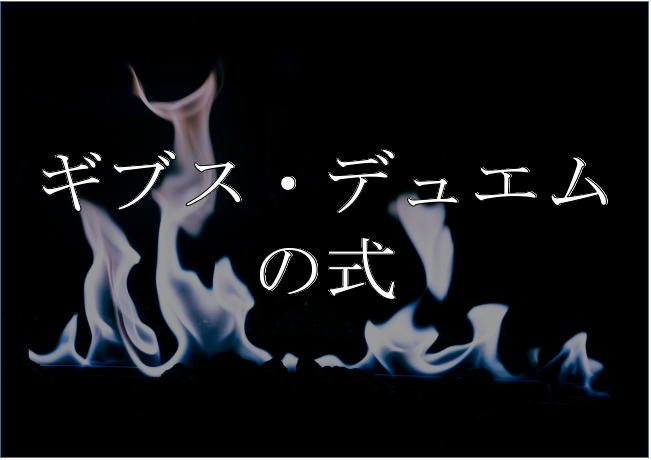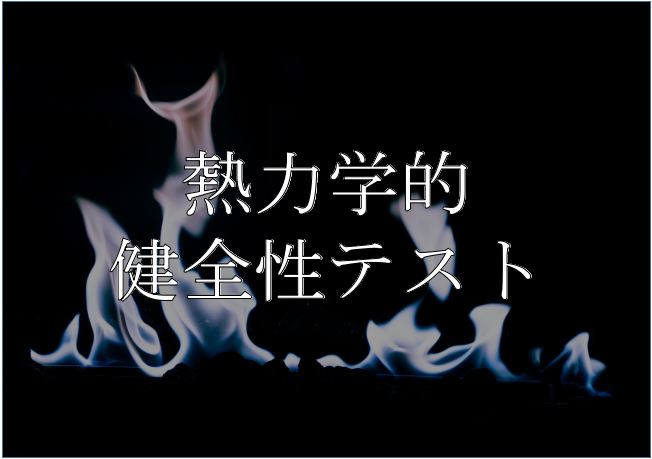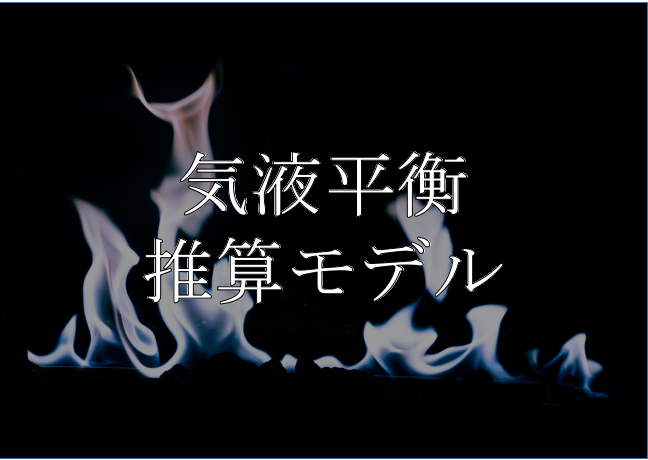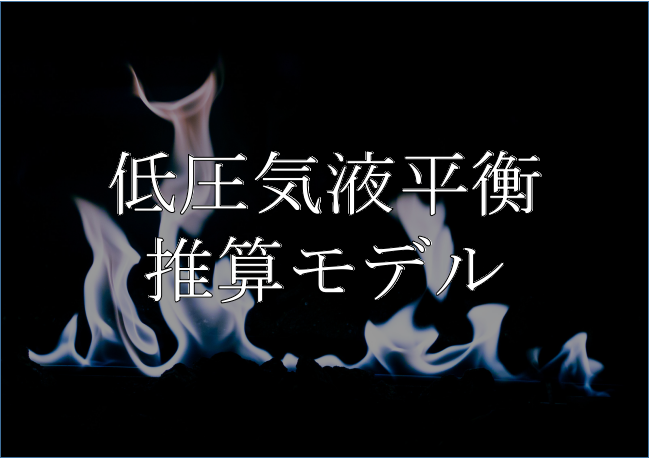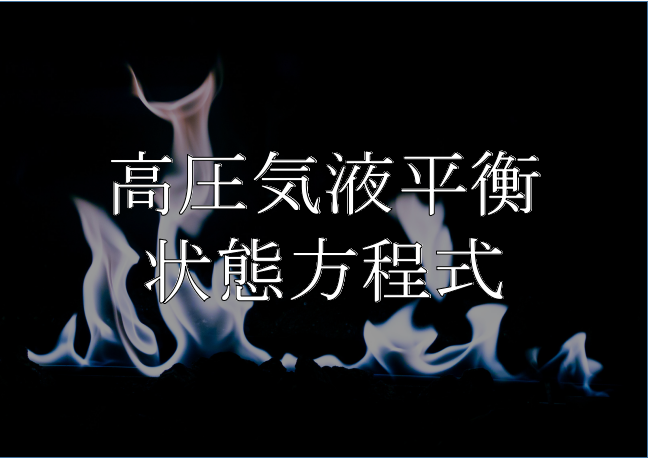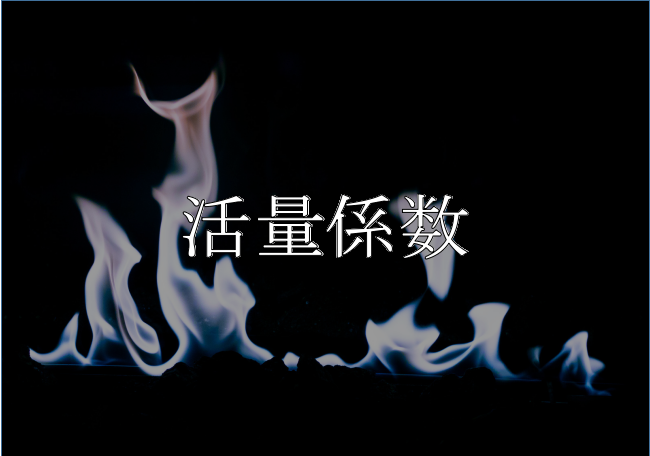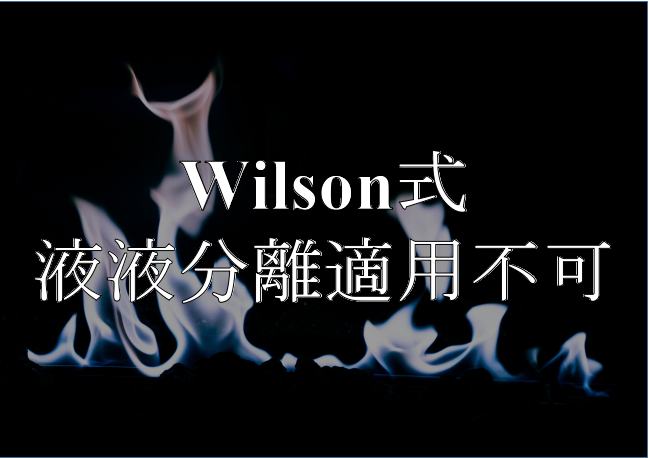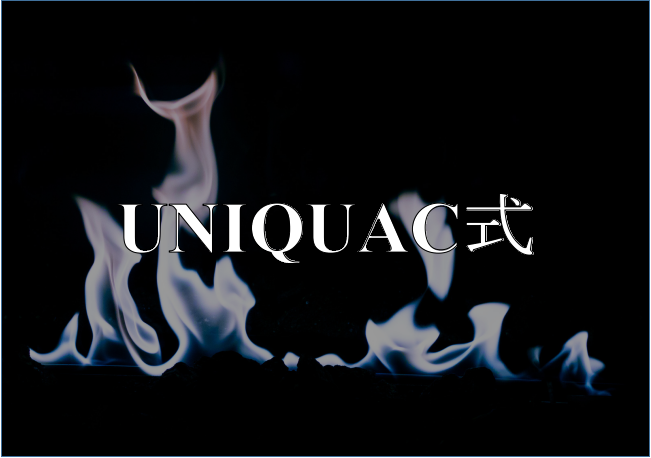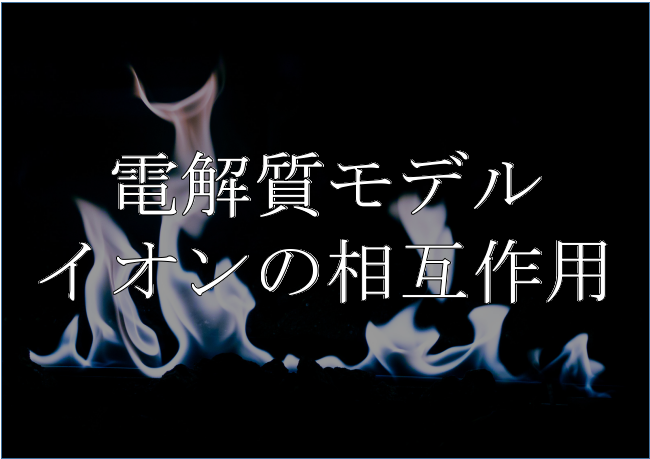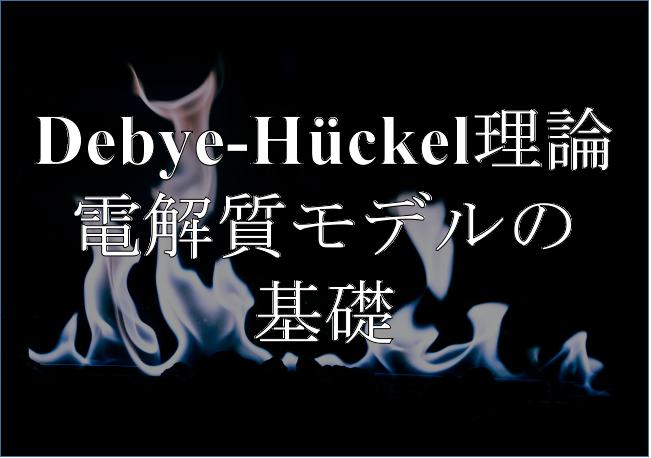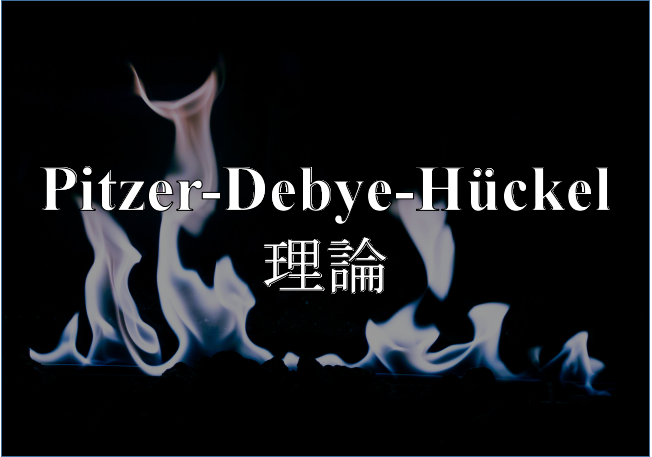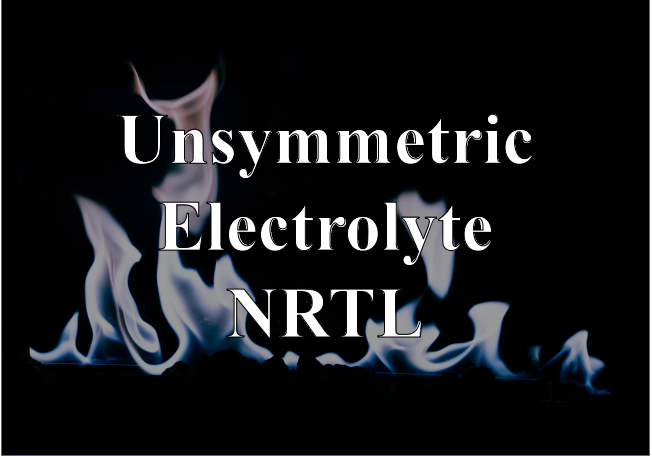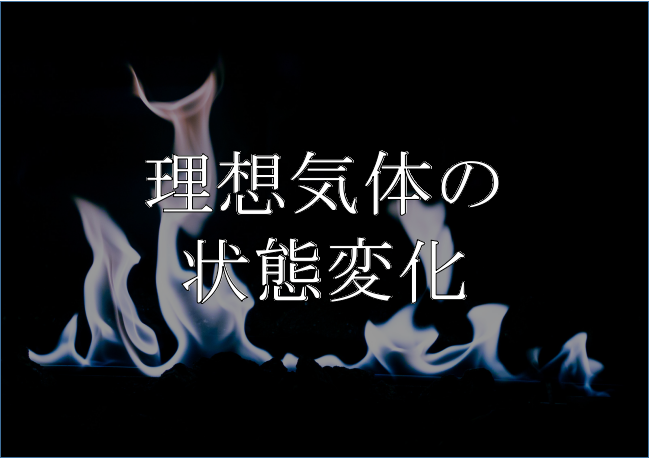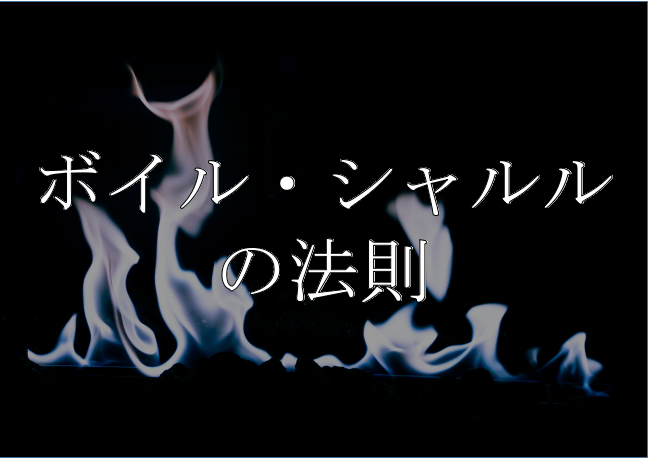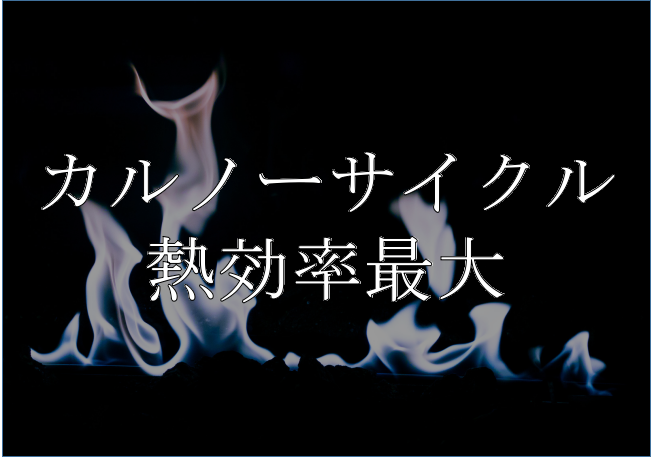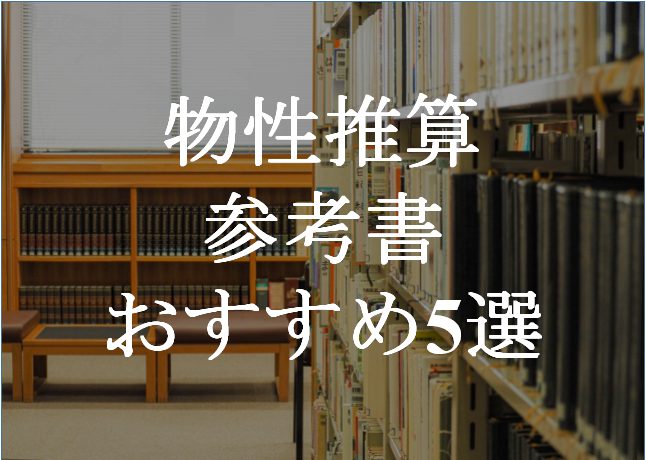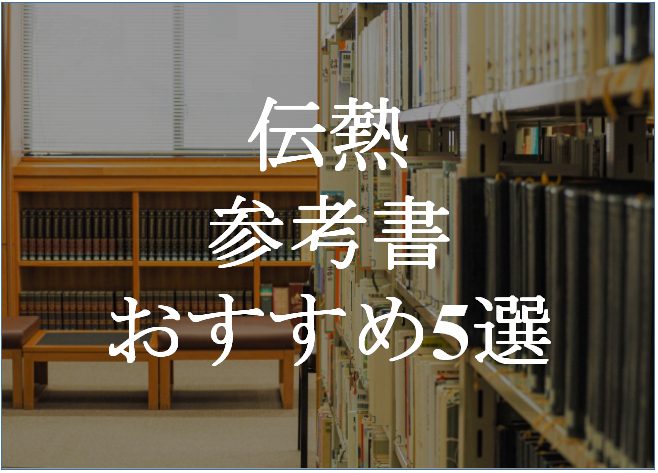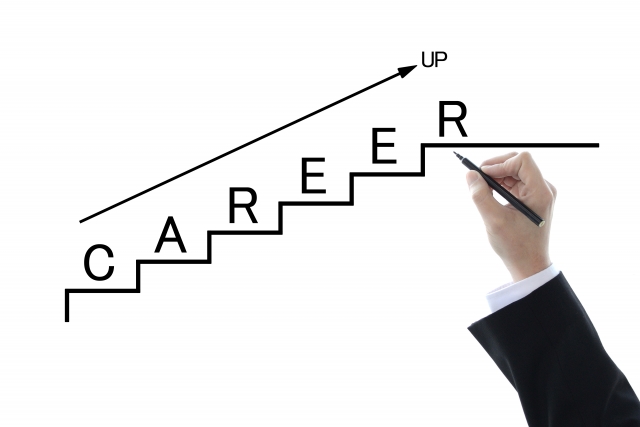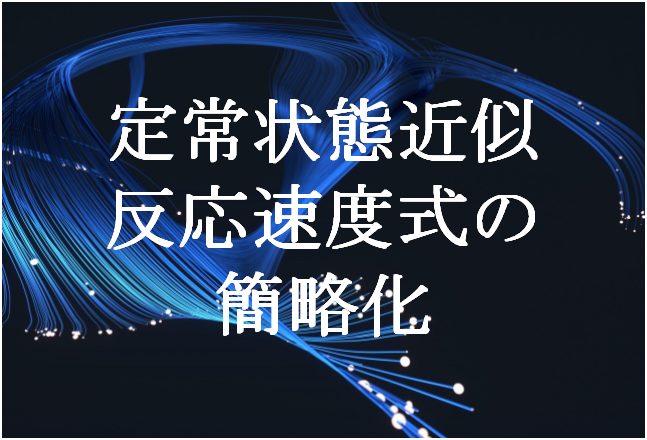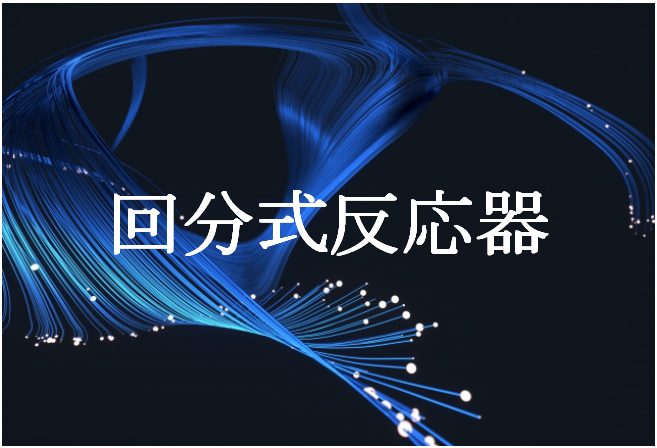P&IDの基礎
-

P&IDの全体構成について解説:レジェンド・P&ID・連結図・ヘッダー系統図など
P&ID(Piping and Instrumentation Diagram)は情報量が多いため、いくつかの要素に分けて記載されることが多いです。本記事ではP&IDの構成や概要について記載しています。
続きを見る
-

【P&IDレジェンド】について解説:略語・シンボル・定義等を記載
P&ID(Piping and instrumentation diagram)に記載する記号・シンボルの省略方法や情報の記載方法を定義する図面をレジェンド(Legend)、もしくはリードシート(Lead Sheet)といいます。会社によってP&IDの記載方法が微妙に異なるため、レジェンドをしっかりと確認して記号や略称の意味を把握することが必要です。
続きを見る
-

【P&ID】配管・計装系統図について解説:プラント設備の情報を記載した図面
P&ID(Piping and Instrumentation Diagram)は日本語で配管・計装系統図といい、プラントの製造工程を流れに沿って詳細に図示したものです。配管を含むプラントがある工場で働くにあたっては、P&IDから情報を読み取ることが業務上必要となってきます。
続きを見る
-

【P&ID】注意事項(NOTE)について解説
P&IDの情報をもとに配管や機器のレイアウトが決定されます。一方でプロセス上、配管や機器のレイアウトに何かしらの制約や要求事項が発生する場合があり、これをNOTE(注意事項)としてP&IDに記載する必要があります。
続きを見る
-

【P&ID】各段階の発行について解説
P&IDは仮図面を何回も発行していき、修正を重ねて完成図を目指します。この仮図面の発行は、ある程度区切りのいい所まで検討が進んだタイミングで行なわれることがほとんどで、どのような意図で仮図面を発行するのか名前が付いています。
続きを見る
集塵の基礎
-

粒子の【終末速度】について解説:重力と抗力の釣り合い
粒子が流体中を沈降する場合に、重力と抗力が釣り合い加速度がゼロになったときの沈降速度を終末速度(あるいは終端速度、終末沈降速度)といいます。流体中から粒子を分離する操作(固液分離、気液分離)においては、粒子の終末速度が重要な因子となることがあります。
続きを見る
-

【カニンガムの補正係数】について解説:粒子が受ける抵抗力の補正
粒子が微細になる、あるいは圧力が低くなると気体分子の不連続性が影響するようになり、粒子表面でガス分子がすべるため粒子への抵抗力が弱まります。このような場合でもStokesの式で計算できるように補正する係数をカニンガム(Cunningham)の補正係数といいます。
続きを見る
-

【ミストエリミネーター】について解説:ミスト除去装置の構造・種類
排ガス処理装置の中で主要なものの1つが湿式法ですが、吸収液の一部がミストとして排ガス中に含まれることが多いです。このようなミストを排ガス中から除去する必要があり、このミスト除去装置をミストエリミネーターといいます。
続きを見る
-

【ワイヤーメッシュ】について解説:メッシュ状シートによるミスト捕集
ミストエリミネーターの中でも主要な形式の1つがワイヤーメッシュです。細いワイヤーを編み込んでメッシュ状のシートとし、このシートを複数重ね合わせてミストの捕集効率を増加させています。ガスはワイヤーメッシュの網目を通過しますが、ミストは慣性力によりワイヤーに衝突することで捕集されます。
続きを見る
フィルター集塵
-

【フィルター効率】について解説:障害物による粒子の捕集効率
粉じんやダスト、ミスト等の粒子を捕集する際によく使用されるのが、障害物に粉じん等を捕集させる方法です。この方法の中でも特に、粒子をフィルターに衝突させて捕集する機構をフィルター集塵といいます。
続きを見る
-

【単一繊維捕集効率】について解説:繊維1本当たりの粒子捕集効率
フィルターの繊維1本が粒子をどの程度捕集するかを表わす効率を単一繊維捕集効率といいます。フィルターの総合的な捕集効率を算出するためには、この単一繊維捕集効率が重要になってきます。単一繊維捕集効率は粒子の大きさやフィルター繊維径、充填率の値によって大きく変化します。
続きを見る
-

【慣性捕集機構】について解説:慣性力による粒子の捕集
粒子を含む流体中にフィルター等の障害物を設置すると、流体は障害物を避けて流れますが、粒子は障害物を避けきれずに衝突し捕集されます。このような慣性力を利用した捕集機構を慣性捕集機構といいます。
続きを見る
-

【さえぎり捕集機構】について解説:障害物による粒子のさえぎり
粒子が小さくなると慣性力が働きにくくなり、粒子は流体と同じ運動をするようになります。障害物近傍を通過するとき、ガス分子は通過できますが、粒子は障害物に物理的にさえぎられて捕集されます。この捕集機構をさえぎり捕集機構といいます。
続きを見る
-

【拡散捕集機構】について解説:ブラウン拡散による粒子捕集
粒子が非常に小さくなると、ランダムな軌道で運動するようになります。これをブラウン運動といい、この運動により粒子を捕集する機構を拡散捕集機構といいます。拡散捕集は小さな粒子を捕集する場合の支配的な機構です。
続きを見る
集塵の種類
-

【重力集塵】について解説:重力による自然沈降分離
重力による自然沈降により粒子・粉じんを分離する装置を重力集塵装置といいます。重力沈降室内に処理ガスを供給し、下から沈降した粒子を取り出し分離します。集塵原理が単純である一方で、集塵率はそれほど高くなく40~60%ほどと言われています。
続きを見る
-

【遠心力集塵】について解説:サイクロンによる粒子捕集
含じんガスを旋回運動させて粒子に遠心力を作用させることで分離する機構を遠心力集塵といい、その代表的な装置をサイクロンといいます。重力よりも大きい加速度(数百~数千倍)を粒子に与えることができるため、重力集塵よりも小さい粒子を多く捕集することができます。
続きを見る
-

【洗浄集塵】について解説:液体による粒子捕集
液滴や液膜等の液体を利用して捕集する集塵機構を洗浄集塵といいます。液体を使用しない集塵方法を乾式集塵が呼ばれるのに対して、洗浄集塵は湿式集塵と呼ばれます。同一の圧力損失で比較すると、乾式集塵よりも湿式集塵の方が捕集効率が良くなることが多いです。
続きを見る
吸着等温式
-

【吸着等温線】を解説:平衡吸着量と圧力の関係
一定温度における平衡吸着量と圧力(または濃度)の関係を吸着等温線といいます。工業プロセスにおける吸着装置は等温下で運転させることが多く、吸着等温線の傾向を把握することは重要です。
続きを見る
-

【Langmuirの吸着等温式】を解説:単分子層吸着の等温式
吸着剤表面に単分子として吸着すると仮定して導出された(1)式をLangmuirの吸着等温式といいます。Langmuirの吸着等温式は最も基礎的な等温式の1つであり、気相の吸着で系の圧力が低い場合に見られることが多いです。
続きを見る
-

【BETの吸着等温式】を解説:多分子層吸着の等温式
吸着剤表面に多分子として吸着すると仮定し導出された(1)式をBETの吸着等温式といいます。BETの吸着等温式は、吸着材の比表面積を算出するのによく使用されます。本記事では、BETの吸着等温式の導出等について解説します。
続きを見る
1冊目
- 書籍タイトル:反応工学
- 著者:井本立也
- 発行者:白井十四雄
- 発行年:昭和43年
- 発行所:日刊工業新聞社
2冊目
- 書籍タイトル:化学反応操作
- 著者:後藤繁雄、板谷義紀、田川智彦、中村正秋
- 発行者:朝倉邦造
- 発行年:2002年
- 発行所:株式会社朝倉書店
3冊目
- 書籍タイトル:プロセス速度 反応装置設計基礎論
- 著者:菅原拓男、菅原勝康
- 発行年:2010年
- 発行所:共立出版株式会社
4冊目
- 書籍タイトル:現代化学工学
- 編者:橋本健治、荻野文丸
- 発行者:飯塚尚彦
- 発行年:2001年
- 発行所:産業図書株式会社
1冊目
- 書籍タイトル:設計者のための物性定数推算法
- 著者:大江修造
- 発行者:大久保健児
- 発行年:昭和60年
- 発行所:日刊工業新聞社
2冊目
- 書籍タイトル:気体、液体の物性推算ハンドブック[第三版]
- 著者:R.C.リード、J.M.プラウズニッツ、T.K.シャーウッド
- 監訳者:平田光穂
- 発行者:荒木亮一
- 発行年:昭和60年
- 発行所:マグロウヒルブック株式会社
化学工学
プラント設計
数値解析
資格
受験体験記
課目Ⅰ
課目Ⅱ
-

【課目Ⅱ:熱力学の基礎】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、熱力学の基礎について解説します。熱力学の基礎は課目Ⅱ"熱と流体の流れの基礎"の中で、大問4問中2問出題されておりウェイトが高い分野です。
続きを見る
-

【課目Ⅱ:流体工学の基礎】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、流体工学の基礎について解説します。流体工学の基礎は課目Ⅱ"熱と流体の流れの基礎"の中で、大問4問中1問出題されています。普段実務で配管の流量計算、圧損計算をやっている方にとっては得点源となるでしょう。
続きを見る
-

【課目Ⅱ:伝熱工学の基礎】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、伝熱工学の基礎について解説します。流体工学の基礎と同様に計算問題が少なく、かつ難易度も比較的簡単です。特に普段実務で扱っている伝熱形態が計算問題として出題されれば確実に点が取れるでしょう。
続きを見る
課目Ⅲ
-

【課目Ⅲ:燃料及び燃焼管理】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、燃料及び燃焼管理について解説します。ひたすら暗記する分野なので試験直前に追い込みをかけやすいですが、範囲が広いので全て覚えるのは大変です。優先順位をつけて勉強しましょう。
続きを見る
-

【課目Ⅲ:燃焼計算】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、燃焼計算について解説します。燃焼計算は課目Ⅲ"燃料と燃焼"の中で、大問3問中1問出題されています。大問がほぼ全て計算問題で構成されていますが、過去問と近い形式の問題が出やすいので得点源になります。
続きを見る
課目Ⅳ
-

【課目Ⅳ:計測及び制御】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、計測及び制御について解説します。計測の内容も制御の内容も、ある程度出題頻度が高い問題が決まっていますので、まずはその内容を重点的に勉強しましょう。
続きを見る
-

【課目Ⅳ:熱利用設備(ボイラ・内燃機関・ガスタービン等)】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、熱利用設備(ボイラ、蒸気輸送、貯蔵装置、蒸気原動機、内燃機関、ガスタービン)について解説します。実務で動力プラントに馴染みのある方は得点源となりますが、そうでない方には少し難しい分野だと思います。
続きを見る
-

【課目Ⅳ:熱利用設備(熱交換器・熱回収装置)】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、熱利用設備(熱交換器・熱回収装置)について解説します。この分野は課目Ⅳの中で選択問題として出題されています。出題内容が比較的簡単なので、特に他の分野にこだわりがなければこの分野を選択することをオススメします。
続きを見る
-

【課目Ⅳ:熱利用設備(冷凍・空気調和設備)】エネルギー管理士(熱分野)の出題分野を解説
この記事ではエネルギー管理士(熱分野)の出題分野である、熱利用設備(冷凍・空気調和設備)について解説します。冷凍サイクルの内容は多少課目Ⅱと被っていますが、空調関係の内容は新たに勉強する必要があります。
続きを見る
化学工学用語集
-

化学工学用語集:専門用語を詳しく解説
化学工学の専門用語をわかりやすく解説しています。あいうえお順、単位操作ごとに分けています。
続きを見る
技術記事
物性
-

【気液平衡】推算方法を解説:状態方程式モデル・活量係数モデルの使い分け
化学プラントにおいて気液平衡は多くの機器で取り扱いがあり、重要な物性となっています。その一方で、2成分間の相互作用を予測するのは非常に難しく、どんな系にも適用できるモデルは今のところ存在しません。したがって、取り扱う系に応じて気液平衡モデルを使い分ける必要があります。
続きを見る
-

【拡散係数】推算方法を解説:主要物質の実測値も記載
Fickの法則に使用されている係数を拡散係数Dといいます。この記事では主要な物質の拡散係数の実測値と、推算方法を紹介します。
続きを見る
-

【蒸発潜熱】推算方法を解説:主要物質の実測値も記載
活量係数モデルで気液平衡を計算する場合には、蒸発潜熱の推算が必要になります。活量係数モデルは気液平衡計算モデルの中でも使用頻度が高いので、蒸発潜熱の推算法も知っておいた方が良いでしょう。
続きを見る
参考書おすすめ
-

【物性推算の参考書5選】化学メーカーの設計担当者がおすすめ紹介
今回紹介する参考書は特に気液平衡に関して詳細な内容が書いてあるものを中心に選定しました。気液平衡は蒸留塔や熱交換器の設計をするうえで理解しておくべきです。
続きを見る
-

【伝熱の参考書5選】化学メーカーの設計担当者がおすすめ紹介
本記事は伝熱の参考書について、特に化学メーカーで伝熱計算することの多い熱交換器に特化した本をご紹介します。
続きを見る
-

【撹拌の参考書5選】化学メーカーの設計担当者がおすすめ紹介
本記事は撹拌の参考書についてご紹介します。化学工学の他の単位操作と比較して、撹拌は体系化が進んでいない分野だと言われており、わかりやすい参考書は貴重です。
続きを見る
数値計算
-

化学工学計算シミュレータの収束計算手法をわかりやすく解説
Aspen Plus等の化学工学計算シミュレータを使用するにあたって悩ましい問題の1つが収束計算です。この記事では化学工学計算シミュレータでよく使用される収束計算手法について解説しています。加えて、どのように設定すれば収束しやすいか、というコツも紹介しています。
続きを見る
-

【線形最小二乗法】をわかりやすく解説:表計算ソフトでのアレニウスプロット
最小二乗法はあるデータとモデルによる計算値との差の二乗和が最小になるようモデルのパラメータを決定する手法です。本記事では化学工学でよく線形プロットされることが多いアレニウスプロットを例に線形最小二乗法を解説しています。
続きを見る
-

化学工学で使用する数値計算ソフトの比較:メリット・デメリットを解説
この記事では私が実務で使ったことがある、あるいはこれから使おうと考えている計算ソフトのメリット・デメリットを比較して紹介します。計算ソフトは1つにこだわる必要はなく、様々なソフトを使用することで新しい発見が生まれます。
続きを見る
資格
-

【公害防止管理者】大気1種の受験体験記:2年かけて合格
公害防止管理者大気1種を2年かけて受験し合格しましたので、その体験を記事にしています。公害防止管理者とは何か?というお堅い内容は他の人の記事に任せるとして、この記事では主観100%の内容で書いています。
続きを見る
-

【高圧ガス製造保安責任者】甲種機械の受験体験記
この記事は高圧ガス製造保安責任者、甲種機械の受験体験記です。甲種機械は11月の国家試験で学識、保安管理技術、法令の3科目を受験し合格することで取得できます。ただし、毎年春(5月頃)に実施される検定試験で学識、保安管理技術の2科目を受験し合格すれば国家試験では免除されます。
続きを見る
-

【高圧ガス法令】高圧ガス製造保安責任者試験の概要・出題範囲を解説
この記事では高圧ガス製造保安責任者試験の法令分野の概要や傾向について解説します。検定試験とは毛色が異なり、"高圧ガス保安法"という高圧ガスの扱いに関する法律の内容となります。
続きを見る
仕事
-

【キャリアプラン】化学メーカー生産技術職を例に紹介
本記事では、生産技術職の実務担当者のキャリアプランについて紹介します。
続きを見る
-

【残業時間・繁忙期】化学メーカー生産技術職は忙しいのか?
本本記事では、生産技術職の残業時間や繁忙期について紹介します。
続きを見る
-

【実務担当者の仕事内容】化学メーカー生産技術職を例に紹介
本記事では、生産技術職の実務担当者の仕事内容について紹介します。
続きを見る
反応の基礎
-

【標準生成エンタルピー】を解説:反応熱計算における基準となるエンタルピー
ある化合物1molが標準状態(1atm、298.15K=25℃)において標準物質から生成するときに生じるエンタルピーを標準生成エンタルピーΔHof[kJ/mol]、もしくは標準生成熱といいます。
続きを見る
-

【Hessの法則】について解説:反応熱の計算
ある化学変化によって起こるエンタルピー変化量は、途中で様々な中間反応が起こったとしても最終的に同じ化学変化の状態に行き着くならばエンタルピー変化量は同じとなります。これをHess(ヘス)の法則といいます。
続きを見る
-

【定常状態近似】について解説:反応速度式の簡略化手法
反応速度がゼロと近似することを定常状態近似といいます。この近似を行なうことでいくつかの素反応で成り立つ式を簡略化することができます。この記事では臭化水素を例に定常状態近似の使用例を解説しています。
続きを見る
反応速度
-

【反応速度】について解説:物質濃度の時間変化
化学プラントでは化学反応を意図的に起こすことで製品を作ります。このとき、その化学反応がどのくらいの反応速度であるかを知ることは非常に重要です。この記事では反応速度の一般的な理論について解説しています。
続きを見る
-

【アレニウスの式】について解説:反応速度の温度依存性
一般に温度が高くなると反応速度は速くなります。このような温度依存性を表わす式をアレニウスの式といいます。本記事ではアレニウスの式を線形プロットして頻度因子Aと活性化エネルギーEを算出するアレニウスプロットについて解説します。
続きを見る
-

【反応次数】の算出方法(微分法・積分法)について解説
化学反応速度を求めるためには、その反応の次数を知ることが必要です。有名な反応ですでに反応次数が知られていればよいですが、そうでない場合は実験データから反応次数を決定する必要があります。この記事では反応次数の決定手法について解説しています。
続きを見る
平衡反応
-

【平衡定数】について化学ポテンシャルによる導出を解説
可逆反応では正反応と逆反応のどちらにも進行する可能性があり、ギブス自由エネルギーが小さくなる方向へ反応が進行します。あるところでギブス自由エネルギーが最小となると、見かけ上反応が止まったように見えます。この状態のことを平衡状態といい、平衡状態における各成分の関係を表わす定数を平衡定数Kといいます。
続きを見る
-

【ル・シャトリエの原理】を解説:平衡が動く方向を示す法則
平衡状態にある系に外部から状態を変化させる操作を行なった場合に、系はその変化を相殺するように平衡を移動させます。このような原理をル・シャトリエの原理といいます。
続きを見る
-

【ファントホッフの式】を解説:平衡定数の温度依存性
平衡定数Kと温度T、標準反応エンタルピーΔH0の関係をファント・ホッフ(van't Hoff)の式といいます。ファント・ホッフの式を最も有効に活用できるのは、標準状態(25℃)以外の温度の平衡定数を求めるときでしょう。
続きを見る
反応器設計
-

【回分式反応器】を解説:少量多品種向きの反応器
最初に原料を全て反応器に仕込み反応させるタイプを回分式反応器をいいます。このご時世は、機能性材料をユーザーに合わせてグレードを変えて製造する傾向にありますから、回分式反応器を見る機会は増えるかもしれません。
続きを見る
-

【連続槽型反応器(CSTR)】の基礎式・実務でのポイントを解説
連続的に物質が流入流出し、かつ槽型の反応器のことを連続槽型反応器(Continuous Stirred Tank Reactor)といいます。化学プラントの連続プロセスにおいて、一般的に使用される反応器の1つです。
続きを見る
-

【管型反応器(PFR)】の基礎式と実務でのポイントを解説
管内に原料を連続的に供給し、反応させる装置を管型反応器といいます。
特に管内で半径方向に濃度・温度分布がなく、入口から出口まで流れ方向にしか分布が存在しない管型反応器をPiston Flow Reactor(またはPlug Flow Reactor)といい、略してPFRといいます。続きを見る