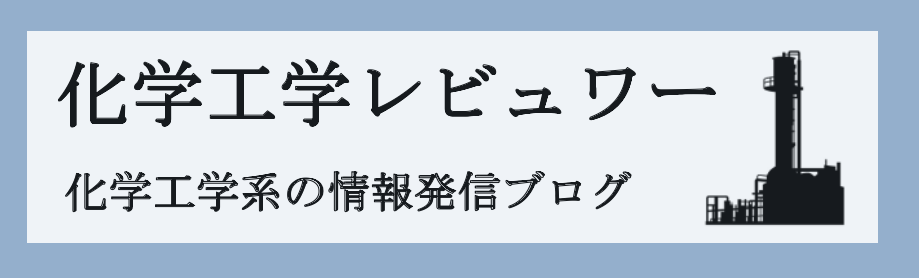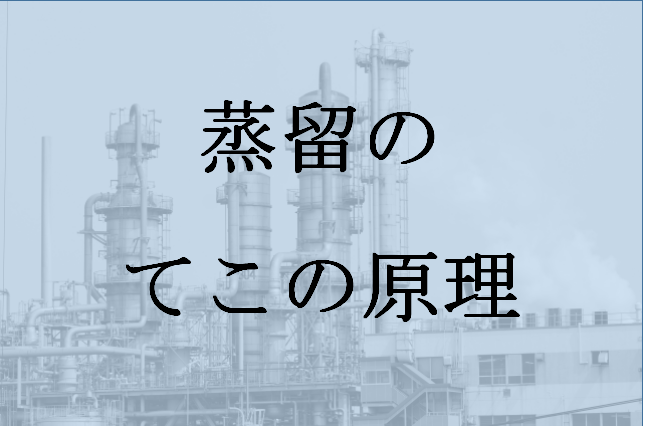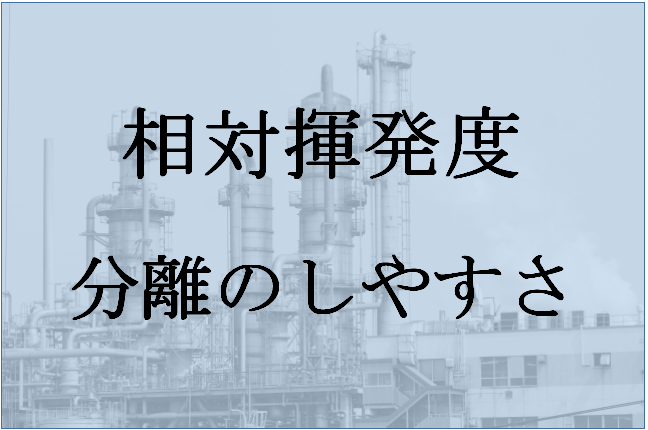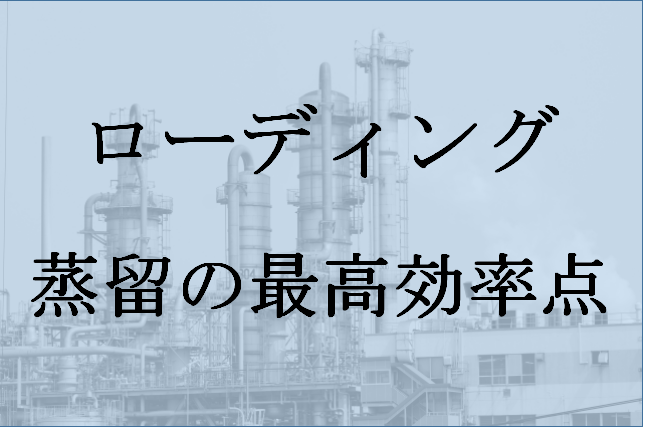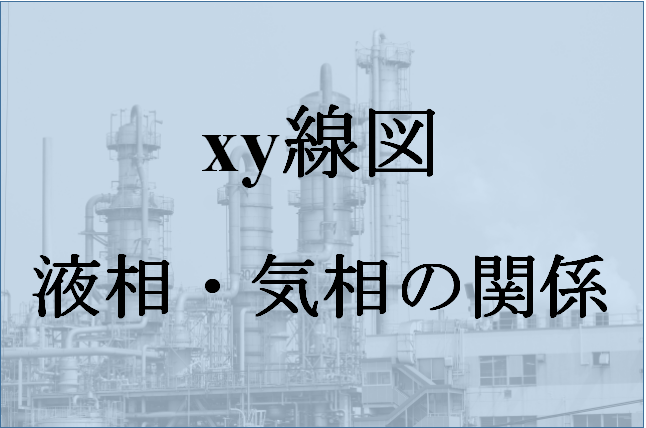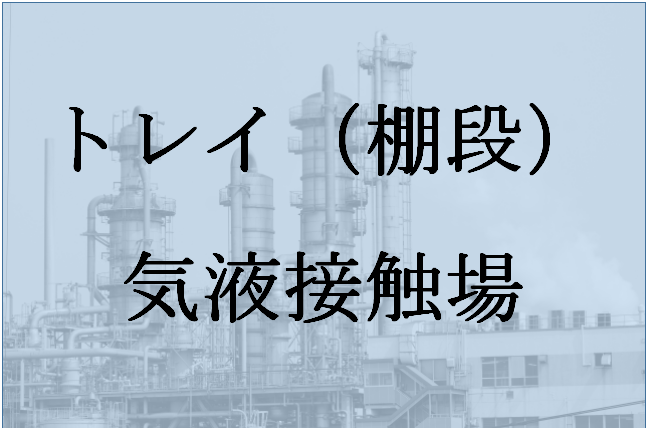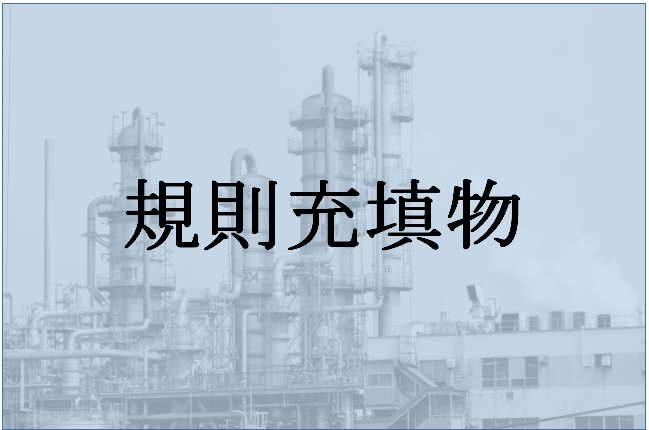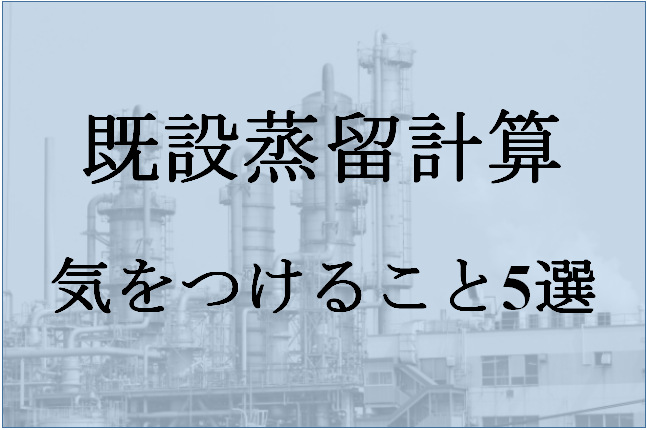蒸留の基礎
-
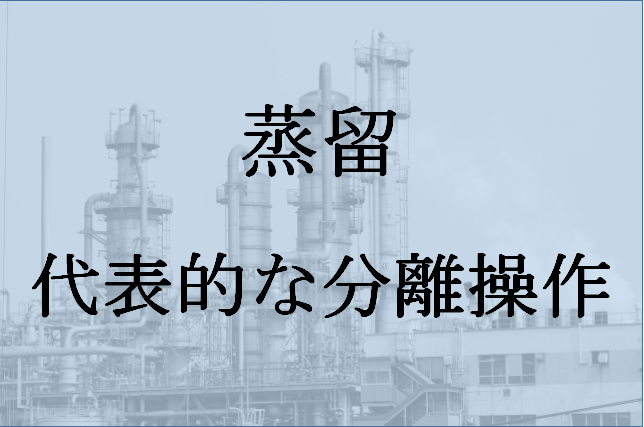
【蒸留】を操作方法ごとに解説:プラントの代表的な分離操作
沸点差を利用して混合物を分離・濃縮する操作のことを蒸留といいます。化学プラントや石油プラントで最もよく使用されている分離方法です。
続きを見る
-

蒸留の【てこの原理】を解説:簡易的に気液平衡を計算
Txy線図、Pxy線図のような線図上において、沸点曲線と露点曲線を平行に繋いだ線をタイラインといい、この線上で物質収支が成り立つ関係のことをてこの原理といいます。
続きを見る
-

【相対揮発度(比揮発度)】を解説:蒸留分離のしやすさを示す指標
ある2成分がどれだけ蒸留分離しやすいのかを示す指標を相対揮発度、もしくは比揮発度といいます。相対揮発度αABがわかれば気液平衡曲線が書けるため、蒸留において重要な指標と言えます。
続きを見る
-

【還流】を解説:効率の良い蒸留操作には必須!
蒸留塔の塔頂から流出した蒸気を凝縮させて液にし、塔内へ戻す操作のことを還流といいます。精留塔においては還流をすることが必須条件になっています。
続きを見る
-

【ローディング】を解説:蒸留塔の理論上の最高効率点
充填塔の操作において液流速を一定に保ち、ガス速度を増加させていった場合に、ガス速度がある値を超えると、ガスの圧力損失が急激に増加し、液ホールドアップが増加し始めます。この点をローディング、もしくはローディング点といい、このときのガス速度をローディング速度といいます。
続きを見る
-

【フラッディング(溢汪)】を解説:蒸留塔の運転上限
充填塔の操作においてガス速度を速くし過ぎると、液が塔内を流下できなくなりガスによって持ち上げられてしまいます。この結果、塔底から液が出てこなくなり塔頂から液が溢れ出します。この状態をフラッディング(溢汪 いつおう)といい、フラッディングが始まる点をフラッディング点と呼びます。
続きを見る
-

【エントレインメント(飛沫同伴)】を解説:蒸留塔の効率低下原因
塔内のガス流速が速い場合に、トレイ上や充填物表面の液滴がガスに同伴し上段へ運ばれる現象をエントレインメント(飛沫同伴)といいます。
続きを見る
xy・Txy・Pxy線図
-

【xy線図】を特徴的な2成分系ごとに解説:液相・気相の関係図
ある2成分の気液平衡関係を表わすグラフのことをxy線図といいます。2成分のうち沸点が低い方をプロットするのが蒸留分野の慣習となっています。
続きを見る
-

【Txy線図】を解説:温度・液相組成・気相組成の関係図
ある2成分において、圧力を一定とした場合の液相組成x、気相組成y、温度Tの関係を表わすグラフのことをTxy線図といいます。
続きを見る
-

【Pxy線図】を解説:圧力・液相組成・気相組成の関係図
ある2成分において、温度を一定とした場合の液相組成x、気相組成y、圧力Pの関係を表わすグラフのことをPxy線図といいます。
続きを見る
棚段塔
-

【棚段塔】のメリット・デメリットを解説:古くから実績がある蒸留塔
塔内にトレイ(棚段)を設置し、トレイ上に保持されている液中にガスを分散させて気液接触させる装置のことを棚段塔といいます。
続きを見る
-

【トレイ(棚段)】を解説:蒸留における効率的な気液接触場
棚段塔に使用される液を保持するための板をトレイ(棚段)といいます。トレイ上に保持した液と塔底から登ってくるガスを接触させるために、トレイにはガスの通り穴が多数空いています。
続きを見る
-

【ウィーピング】を解説:蒸留塔トレイからの液漏れ現象
棚段塔において、トレイの小孔(ガスの通り穴)から液が漏れる現象をウィーピングといいます。
ウィーピングが起こっても塔を運転することはできますが、トレイ上の液深が低くなり気液接触の効率が悪化してしまいます。続きを見る
充填塔
-

【不規則充填物】を第1世代~第4世代に分けて解説
充填塔内にランダムに充填するタイプの充填物を不規則充填物といいます。詳細な設計データは各文献やカタログ、計算ソフトに任せるとして、ここでは代表的な充填物を各世代ごとに簡単に紹介します。
続きを見る
-

代表的な【規則充填物】を解説:Sulzer・Koch・月島の充填物紹介
規則充填物とは、充填塔内に設置した充填物が規則的な構造を持っているもののことをいいます。トレイと比較して規則充填物は圧力損失が少ないため、特に真空蒸留系に好んで使用されるようになりました。
続きを見る
-

【HETP】を解説:充填塔の理論段数1段相当の高さ
HETPはHeight Equivalent to a Theoretical Plateの略で、理論段数1段と同等の性能となる充填高さを表わします。段塔の考え方である理論段数をそのまま充填塔に利用できるため、非常に便利な指標です。
続きを見る
蒸留塔設計
-

既設プラントの蒸留計算をするときに気をつけていること5選
蒸留計算の手法自体は確立されているのですが、蒸留塔の能力計算となると途端に実測値と計算値が合わなくなることがよくあります。本記事では、化学メーカーの設計担当者が実務で既設プラントの蒸留計算をするときに気をつけていることを5つ紹介します。
続きを見る
-

【McCabe-Thieleの階段作図】を徹底解説:蒸留塔理論段数の簡易計算法
理論段数を作図で簡便に求める方法のことを、McCabe-Thiele(マッケーブ-シール)の階段作図といいます。この方法は蒸留塔の操作を図で表すことで、蒸留操作を直感的に理解できる点が非常に優れています。
続きを見る
-

【理論段数】の推算方法を解説:蒸留塔の分離性能を決める
理想的な条件を考えると、トレイの各段では気液平衡に達しています。このときに、要求される塔出口のスペックを満たすために必要なトレイ段数のことを理論段数といいます。
続きを見る