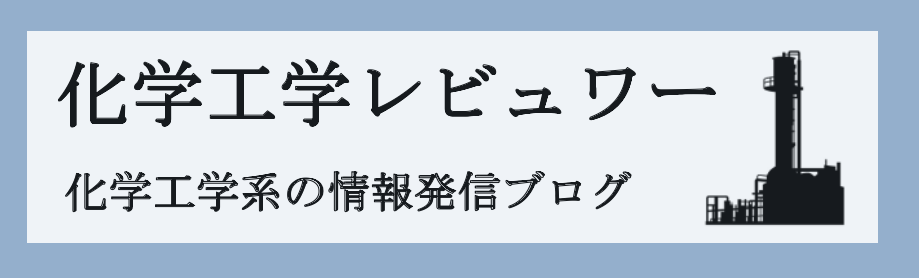概要
実在気体の圧力や相平衡を、理想気体と同様の形式で扱うために導入された概念をフガシティーfといいます。
$$μ_{i}(p_{i})=μ_{i}^{0}+RT{\rm{ln}}\frac{f_{i}}{p^{0}}・・・(1)$$
μi:成分iの化学ポテンシャル、fi:成分iのフガシティー
μi0:標準状態における成分iの化学ポテンシャル
(1)式がフガシティーの定義となります。
実務で気液平衡を計算する際には、気液のフガシティーが一致することを前提として式を立てており、重要な概念です。
本記事ではフガシティーについて解説しています。
定義
フガシティーの定義について解説します。
理想気体における化学ポテンシャルの圧力依存性
まずギブス・デュエムの式から、
$$SdT-VdP+\sum n_{i}dμ_{i}=0・・・(2)$$
(2)式が成り立ちます。
(2)式で温度一定、組成一定条件で圧力変化を考えると、
$$\Bigl(\frac{∂μ_{i}}{∂p}\Bigr)_{T,n_{j}}=\bar{V_{i}}・・・(3)$$
(3)式となります。
仮に扱う系が理想気体であれば、状態方程式から、
$$\Bigl(\frac{∂μ_{i}}{∂p}\Bigr)_{T,n_{j}}=\frac{RT}{p_{i}}・・・(4)$$
(4)式となります。
(4)式を圧力pで積分すると、
$$μ_{i}(p_{i})=μ_{i}^{0}+RT{\rm{ln}}\frac{p_{i}}{p^{0}}・・・(5)$$
(5)式となり、理想気体における化学ポテンシャルの圧力依存性を表わす式が導出されました。
フガシティーの導入
ここから、(5)式を実在気体にも使用できるよう拡張したいのですが、分子間相互作用を厳密に考慮しようとすると式の形が複雑になります。
そこでルイスは、ある実在気体と同じ化学ポテンシャルを持つ理想気体の圧力としてフガシティーfを定義しました。
すると(5)式は、
$$μ_{i}(p_{i})=μ_{i}^{0}+RT{\rm{ln}}\frac{f_{i}}{p^{0}}・・・(1)$$
記事冒頭の(1)式のように表すことができます。
あるいは、標準状態における圧力p0もフガシティーで表すと、
$$μ_{i}(p_{i})=μ_{i}^{0}+RT{\rm{ln}}\frac{f_{i}}{f^{0}}・・・(6)$$
fi0:標準状態における純成分iのフガシティー
(6)式となります。
このフガシティーで実在気体の非理想的な相互作用が生じたときの圧力を表わすことで、理想気体の仮定から導かれた(5)式をほとんどそのままの形で使用することができます。
フガシティー係数
系の圧力が十分に低い場合は理想気体に近似できます。したがって、フガシティーには、
$$\lim_{p \to 0} \frac{f_{i}}{p_{i}}=1・・・(7)$$
(7)式の関係があります。
加えて、(7)式における成分iのフガシティーfiと理想気体の圧力piの比をフガシティー係数φiといいます。
$$φ_{i}≡\frac{f_{i}}{p_{i}}・・・(8)$$
理想気体である場合φi=1となります。
また、(8)式を(1)式に代入すると、
$$μ_{i}(p_{i})=μ_{i}^{0}+RT{\rm{ln}}\frac{p_{i}}{p^{0}}+RT{\rm{ln}}φ_{i}・・・(9)$$
(9)式となり、理想気体で成り立つ(5)式に対して、RTlnφiで補正している形になります。
したがって、フガシティー係数は理想気体からどれくらいずれているか(偏倚)を意味します。
フガシティー係数の算出
実用上は、フガシティー係数φをどのように求めるかが非常に重要です。
ここでは、状態方程式からフガシティー係数φを算出するための基礎式を導出してみます。
まず、ギブス自由エネルギーの偏倚関数(g-gid)T,Pは(9)式から、
$$(g-g^{id})_{T,P}=RT{\rm{ln}}φ_{i}・・・(10)$$
g:実在気体のモルギブス自由エネルギー[J/mol]
gid:理想気体のモルギブス自由エネルギー[J/mol]
(10)式で表され、変形すると、
$${\rm{ln}}φ_{i}=\frac{(g-g^{id})_{T,P}}{RT}・・・(11)$$
(11)式となります。
次にギブス自由エネルギーの定義から、
$$(g-g^{id})_{T,P}=(h-h^{id})_{T,P}-T(s-s^{id})_{T,P}・・・(12)$$
h:実在気体のモルエンタルピー[J/mol]、hid:理想気体のモルエンタルピー[J/mol]
s:実在気体のモルエントロピー[J/(mol・K)]、sid:理想気体のモルエントロピー[J/(mol・K)]
ギブス自由エネルギーの偏倚関数はエンタルピーとエントロピーの偏倚関数で表されます。
続いて、Maxwellの関係式から、
$$\Bigl(\frac{∂s}{∂P}\Bigr)_{T}=-\Bigl(\frac{∂v}{∂T}\Bigr)_{P}・・・(13)$$
v:モル体積[m3/mol]
(13)式が成り立ちます。
理想気体の状態方程式Pv=RTを使用すると、
$$\Bigl(\frac{∂s^{id}}{∂P}\Bigr)_{T}=-\frac{R}{P}・・・(14)$$
(14)式となります。
したがって、エントロピーの偏倚関数(s-sid)T,Pは、
$$(s-s^{id})_{T,P}=\int_{0}^{P}[-\Bigl(\frac{∂v}{∂T}\Bigr)_{P}+\frac{R}{P}]dP・・・(15)$$
(15)式となります。
同様にエンタルピーもMaxwellの関係式を利用して導出することができ、
$$\Bigl(\frac{∂h}{∂P}\Bigr)_{T}=-T\Bigl(\frac{∂v}{∂T}\Bigr)_{P}+v・・・(16)$$
(16)式となります。
理想気体においてはPv=RTを使用し、
$$\Bigl(\frac{∂h^{id}}{∂P}\Bigr)_{T}=-T\Bigl(\frac{∂(RT/P)}{∂T}\Bigr)_{P}+v=-v+v=0・・・(17)$$
(17)式となります。
したがって、エンタルピーの偏倚関数(h-hid)T,Pは、
$$(h-h^{id})_{T,P}=\int_{0}^{P}[-T\Bigl(\frac{∂v}{∂T}\Bigr)_{P}+v]dP・・・(18)$$
(18)式となります。
(15)、(18)式を(12)式に代入し、
$$\begin{align}(g-g^{id})_{T,P}&=\int_{0}^{P}[-T\Bigl(\frac{∂v}{∂T}\Bigr)_{P}+v]dP-T(\int_{0}^{P}[-\Bigl(\frac{∂v}{∂T}\Bigr)_{P}+\frac{R}{P}]dP)\\&=\int_{0}^{P}(v-\frac{RT}{P})dP・・・(19)\end{align}$$
(19)式となりました。
(19)式を(11)式に代入すれば、フガシティー係数φを計算できる式が得られます。
$${\rm{ln}}φ_{i}=\frac{1}{RT}\int_{0}^{P}(v-\frac{RT}{P})dP・・・(20)$$
ただし、(20)式をそのまま使用することを考えると、状態方程式を体積v=の形に変形する必要があり、式によっては非常に困難です。
状態方程式は圧力P=の形で表されることが多いので、(20)式を使いやすいように変形しておきましょう。
圧縮係数の定義から、
$$Pv=zRT・・・(21)$$
z:圧縮係数
(21)式が成り立ちます。
(21)式を温度T一定で全微分すると、
$$Pdv+vdP=RTdz・・・(22)$$
(22)式となります。
両辺をdvで割って整理すると、
$$\Bigl(\frac{∂P}{∂v}\Bigr)_{T}=\frac{RT}{v}\Bigl(\frac{∂z}{∂v}\Bigr)_{T}-\frac{P}{V}・・・(23)$$
(23)式となります。
次に、積分するパラメータを圧力から体積へ変換します。
$$\begin{align}\Bigl(\frac{∂{\rm{ln}}φ}{∂v}\Bigr)_{T}&=\Bigl(\frac{∂{\rm{ln}}φ}{∂P}\Bigr)_{T}・\Bigl(\frac{∂P}{∂v}\Bigr)_{T}\\&=\frac{1}{RT}(v-\frac{RT}{P})・\Bigl(\frac{RT}{v}\Bigl(\frac{∂z}{∂v}\Bigr)_{T}-\frac{P}{V}\Bigr)\\&=(1-\frac{1}{z})\Bigl(\frac{∂z}{∂v}\Bigr)_{T}+\frac{1}{v}(1-z)\\&=\Bigl(\frac{∂z}{∂v}\Bigr)_{T}-\Bigl(\frac{∂{\rm{ln}}z}{∂v}\Bigr)_{T}+(\frac{1}{v}-\frac{P}{RT})・・・(24)\end{align}$$
(24)式をP=0~Pまで積分します。
- P=0のとき、v=∞、z=1
- P=Pのとき、v=v、z=z
となりますので、
$$\begin{align}{\rm{ln}}φ&=\int_{∞}^{v}[\Bigl(\frac{∂z}{∂v}\Bigr)_{T}-\Bigl(\frac{∂{\rm{ln}}z}{∂v}\Bigr)_{T}]dv+\int_{∞}^{v}(\frac{1}{v}-\frac{P}{RT})dv\\&=[z-{\rm{ln}}z]^{z}_{1}+\frac{1}{RT}\int_{∞}^{v}(\frac{RT}{v}-P)dv\\&=z-{\rm{ln}}z-1+\frac{1}{RT}\int_{∞}^{v}(\frac{RT}{v}-P)dv・・・(25)\end{align}$$
(25)式となり、使用しやすい形に変形できました。
気液平衡におけるフガシティー
気液平衡の成立条件
以下の化学ポテンシャルの記事で、気液平衡が成立する条件は気相・液相における各成分の化学ポテンシャルが一致することがと述べました。
-
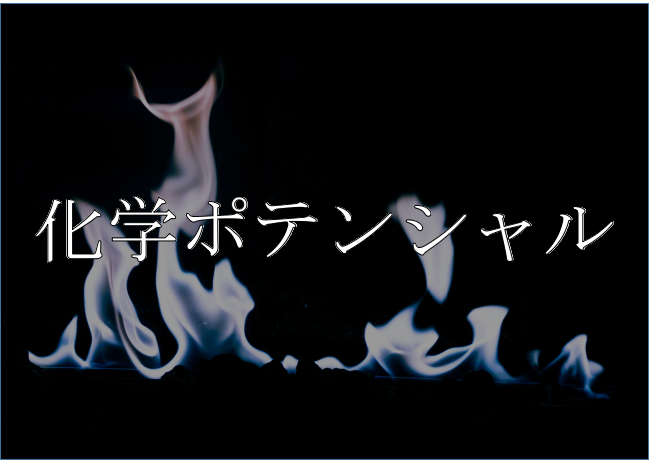
【化学ポテンシャル】をわかりやすく解説:開放系への理論の拡張
実際の系では、外部から物質を出入りさせることは当たり前に行なう操作ですので、開放系にまで理論を拡張する必要があります。そこで、外部からの物質の出入りにより物質量が変化するように熱力学の第一法則を修正し、新たに化学ポテンシャルが定義されました。
続きを見る
$$μ_{i}^{V}=μ_{i}^{L}・・・(26)$$
一方で、化学ポテンシャルは(6)式に示したようにフガシティーで表されます。
$$μ_{i}(p_{i})=μ_{i}^{0}+RT{\rm{ln}}\frac{f_{i}}{f^{0}}・・・(6)$$
気相・液相それぞれに(6)式を適用すると、
$$μ_{i}^{0V}+RT{\rm{ln}}\frac{{f_{i}}^{V}}{f^{0V}}=μ_{i}^{0L}+RT{\rm{ln}}\frac{{f_{i}}^{L}}{f^{0L}}・・・(27)$$
(27)式となります。
ここで、気液平衡においては気相・液相の温度及び圧力が一致します。
したがって、純物質の化学ポテンシャルμ0は両相で一致し、標準状態における純成分iのフガシティーfi0も一致します。
これにより(27)式は、
$$f_{i}^{V}=f_{i}^{L}・・・(28)$$
(28)式となり、気液平衡が成立する条件は気相・液相における各成分のフガシティーが一致することであることがわかりました。
各相のフガシティーの表現
気相・液相のフガシティーの計算手法は、主に以下の2種類の方法がよく使用されています。
①気相:状態方程式 液相:状態方程式
フガシティー係数の定義式である(8)式を(28)式に適用すると、
$$p_{i}φ_{i}^{V}=p_{i}φ_{i}^{L}$$
$$y_{i}φ_{i}^{V}=x_{i}φ_{i}^{L}・・・(29)$$
φiV:気相における成分iのフガシティー係数
φiL:液相における成分iのフガシティー係数
(29)式となります。
したがって、気相・液相両方のフガシティー係数を(25)式から状態方程式を使用して求めることになります。
$$\begin{align}{\rm{ln}}φ^{V}&=z-{\rm{ln}}z-1+\frac{1}{RT}\int_{∞}^{v}(\frac{RT}{v}-P)dv・・・(25-a)\end{align}$$
$$\begin{align}{\rm{ln}}φ^{L}&=z-{\rm{ln}}z-1+\frac{1}{RT}\int_{∞}^{v}(\frac{RT}{v}-P)dv・・・(25-b)\end{align}$$
気体と液体の体積や圧縮係数が異なると思いますので注意しましょう。
②気相:状態方程式 液相:活量係数モデル
①で紹介した手法は、理想系に近い物質であれば比較的精度は良いでしょう。
ただし、液相における極性分子の相互作用など、非理想性が高くなると状態方程式では合わなくなります。
そこで、液相を活量係数γを使用して表現する手法が実用的であり、よく使用されています。
$$y_{i}φ_{i}^{V}P=x_{i}γ_{i}{f_{i}}^{0}・・・(30)$$
ここで、標準フガシティーfi0は、
$$f_{i}^{0}=φ_{i}^{s}P_{i}^{0}θ_{i}・・・(31)$$
$$θ_{i}={\rm{exp}}\frac{v_{i}(P-P_{i}^{s})}{RT}・・・(32)$$
φis:成分iの飽和蒸気圧Pisにおけるフガシティー係数
Pis:成分iの飽和蒸気圧、θi:ポインティング因子
(31)式で与えられます。
ポインティング因子は液の膨張・圧縮を表わしており、低圧ではθi=1とみなせます。
おわりに
フガシティーについて解説しました。
実在気体の圧力や相平衡を考えるうえで、非常に重要な概念です。