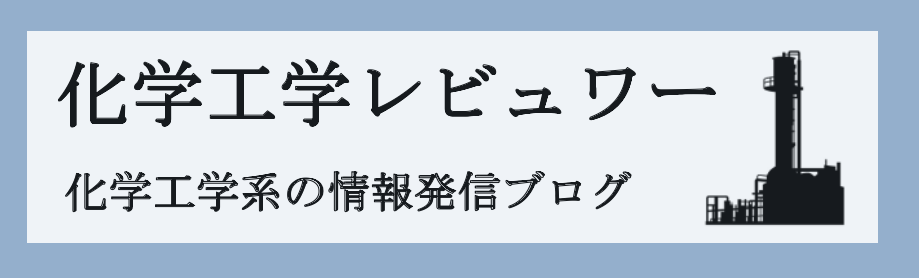化学ポテンシャルの定義
ギブス自由エネルギーGの導入により、閉鎖系における自発変化の方向性や平衡状態を表現することができるようになりました。
しかし実際の系では、外部から物質を出入りさせることは当たり前に行なう操作ですので、閉鎖系ではまだ不十分で開放系にまで理論を拡張する必要があります。
その一方で、熱力学の第一法則・第二法則、ギブス自由エネルギーは物質量や物質の組成を表わす状態量を含んでいません。
したがって、外部からの物質の出入りにより物質量が変化することで平衡状態が変化するような法則を新たに考える必要があります。
そこでGibbsは熱力学の第一法則である(1)式を、(2)式へと修正することで開放系へと理論を拡張しました。
$$dU=δQ+δW・・・(1)$$
U:内部エネルギー、Q:熱量、W:仕事
$$dU=δQ+δW+\sum_{i}μ_{i}dn_{i}・・・(2)$$
μ:化学ポテンシャル[J/mol]、n:物質量[mol]
(2)式においては、物質量当たりのエネルギーのようなものを表わす状態量を化学ポテンシャルμとして新たに定義して、物質量nとの積μ×nの全成分の和の項を新たに追加しています。
この項により物質量の変化が自発変化の方向や平衡状態に影響を及ぼすことができ、開放系へと理論が拡張されました。
化学ポテンシャルは(2)式からわかる通り、どのような過程を考えるかで定義式が異なります。
ここでは化学分野でよく考えられる等温・定圧条件下での化学ポテンシャルの定義を導出します。
(2)式において、温度T一定条件下ではエントロピーの定義より、
$$δQ=TdS・・・(3)$$
(3)式が成り立ちます。
また、圧力P一定条件下において、外部にする仕事をマイナスに取ると、
$$W=-PdV・・・(4)$$
(4)式となります。
(3)、(4)式を(2)式へと代入すると、
$$dU-TdS+PdV=\sum_{i}μ_{i}dn_{i}・・・(5)$$
(5)式となります。
(5)式において、温度T一定、圧力P一定であれば、
$$TdS=TdS+SdT=d(TS)・・・(6)$$
$$PdV=PdV+VdP=d(PV)・・・(7)$$
(6)、(7)式のような式変形が可能です。すると、(5)式は、
$$d(U+PV-TS)=\sum_{i}μ_{i}dn_{i}・・・(8)$$
(8)式となります。
エンタルピーの定義H=U+PV、ギブスエネルギーの定義G=H-TSから、
$$dG=\sum_{i}μ_{i}dn_{i}・・・(9)$$
(9)式のようにギブス自由エネルギーの微小変化dGで左辺を表わすことができました。
(9)式を化学ポテンシャルについて整理すると、
$$μ_{i}=(\frac{∂G}{∂n_{i}})_{T,P,n_{j}(j≠i)}・・・(10)$$
等温・定圧条件下での化学ポテンシャルの定義である(10)式となりました。
(10)式は温度T、圧力P、成分i以外の成分が一定の条件下で、成分iについて微小変化させたときのギブス自由エネルギー変化量が化学ポテンシャルであることを意味しています。
ちなみに単一の成分系の場合、(10)式は
$$μ=\frac{G}{n}・・・(11)$$
(11)式のような簡単な形に簡略化できます。
この場合、化学ポテンシャルは単位物質量(1mol)当たりのギブス自由エネルギーという非常にわかりやすい意味合いになります。
ただし、化学ポテンシャルがこの意味合いを持つのは単一成分系に限られる話で、多成分系では成り立たないことに気をつけましょう。
相平衡
相平衡のときに化学ポテンシャルがどのような関係を示すか考えてみましょう。
ここでは気液平衡に達している系を考え、簡単のために1成分系とします。
等温定圧条件下で、気液両相の間で物質を微小量dnだけ移動させたとき、系全体のギブス自由エネルギー変化dGは、
$$dG=μ_{g}dn_{g}+μ_{l}dn_{l}・・・(12)$$
μg:気相の化学ポテンシャル[J/mol]、μl:液相の化学ポテンシャル[J/mol]
ng:気相の物質量[mol]、nl:液相の物質量[mol]
(12)式となります。
系全体は容器に密閉されており物質が系外に流出することがないとすると、各相の物質量の変化は、
$$dn_{g}=-dn_{l}・・・(13)$$
(13)式となります。
(13)式を(12)式に代入すると、
$$dG=(μ_{g}-μ_{l})dn_{g}・・・(14)$$
(14)式となります。
もしこの系が気液平衡に達しているなら、ギブス自由エネルギー変化dG=0となります。
したがって(14)式において、いかなるdngについてもdG=0となるためには、
$$μ_{g}=μ_{l}・・・(15)$$
(15)式が成り立つ必要があります。
したがって、相平衡が成り立つ場合には、両相の化学ポテンシャルが等しくなります。
また、上の例で気液平衡に達していない場合について考えてみます。
仮に気相の化学ポテンシャルの方が液相の化学ポテンシャルより高いとすると、
$$μ_{g}-μ_{l}>0・・・(16)$$
(16)式となります。
平衡に達していない場合は自発変化が起こりますが、その方向性はdG<0です。
(14)、(16)式から、dG<0となるとき、dng<0となります。
気相の物質量変化がマイナスなので、気相から液相へと物質が移動することになります。
逆に液相の化学ポテンシャルの方が気相の化学ポテンシャルより高いとすると、
$$μ_{g}-μ_{l}<0・・・(17)$$
(17)式となり、同様の考えでdng>0となります。
気相の物質量変化がプラスなので、液相から気相へと物質が移動することになります。
このように化学ポテンシャルの高い方から低い方へと物質が移動する特徴が、位置エネルギー(ポテンシャルエネルギー)や電位(静電ポテンシャル)に似ていることから"化学ポテンシャル"という名前の由来となっています。
理想系の化学ポテンシャル
理想気体の化学ポテンシャル
理想気体の化学ポテンシャルを導出してみましょう。
ギブスエネルギーの定義式G=H-TSから、
$$\begin{align}dG&=d(H-TS)=d(U+PV)-d(TS)\\&=TdS-PdV+PdV+VdP-(SdT+TdS)\\&=VdP-SdT・・・(18)\end{align}$$
ギブス自由エネルギーに関して(18)式が成り立ちます。
ここで、物質Aの部分モルギブス自由エネルギーは物質Aの化学ポテンシャルと一致しますから、
$$\bar{G_{A}}=dμ_{A}=V_{mA}dP_{A}-S_{mA}dT・・・(19)$$
VmA:物質A1mol当たりの体積[m3/mol]
SmA:物質A1mol当たりのエントロピー[J/(mol・K)]
(19)式となります。
等温条件下でdT=0ですから、
$$dμ_{A}=V_{mA}dP_{A}・・・(20)$$
(20)式となります。
理想気体の状態方程式を使用しつつ、(20)式を分圧PAiからPAfまで積分すると、
$$\int_{μ_{Ai}}^{μ_{Af}}dμ_{A}=\int_{P_{Ai}}^{P_{Af}}\frac{RT}{P_{A}}dP_{A}$$
$$μ_{Af}=μ_{Ai}+RT{\rm{ln}}\frac{P_{Af}}{P_{Ai}}・・・(21)$$
(21)式となります。
ここで、始状態のAの分圧PAiを標準圧力PAoとし、そのときの化学ポテンシャルをμAoとします。
(ここでいう標準圧力は1atm=1.013×105Paの場合もあれば、1bar=105Paの場合もあり文献等により異なります。)
また、終状態のAの分圧をPAとし、そのときの化学ポテンシャルをμAとします。
$$μ_{A}={μ_{A}}^{o}+RT{\rm{ln}}\frac{P_{A}}{{P_{A}}^{o}}・・・(22)$$
PAo=1barとして簡略化すると、
$$μ_{A}={μ_{A}}^{o}+RT{\rm{ln}}P_{A}・・・(23)$$
(23)式のような理想気体における化学ポテンシャルと分圧の関係を導くことができました。
理想溶液の化学ポテンシャル
続いて、理想溶液の化学ポテンシャルを導出してみましょう。
気液平衡に達している場合、気体と液体の化学ポテンシャルは一致するため、
$$μ(g)=μ(l)・・・(24)$$
μ(g):気相の化学ポテンシャル、μ(l):液相の化学ポテンシャル
(24)式となります。
ここでまず、系の成分がAのみの純成分である場合、化学ポテンシャルは(22)式から、
$${μ_{A}(l)}^{*}={μ_{A}(g)}^{*}={μ_{A}}^{o}+RT{\rm{ln}}\frac{{P_{A}}^{*}}{{P_{A}}^{o}}・・・(25)$$
μA(g)*:成分Aの純気体の化学ポテンシャル、μA(l)*:成分Aの純液体の化学ポテンシャル
PA*:成分Aの純物質蒸気圧
(25)式となります。
次に多成分系における成分Aについても考えます。前述したように、化学ポテンシャルは多成分系における混合の影響も加味して表現できますから、
$$μ_{A}(l)=μ_{A}(g)={μ_{A}}^{o}+RT{\rm{ln}}\frac{P_{A}}{{P_{A}}^{o}}・・・(26)$$
(26)式のように表すことができます。
(25)、(26)式からμAoを消去すると、
$$μ_{A}(l)={μ_{A}(l)}^{*}+RT{\rm{ln}}\frac{P_{A}}{{P_{A}}^{*}}・・・(27)$$
(27)式が成り立ちます。
ここで、理想溶液におけるRaoultの法則から、
$$P_{A}=x_{A}{P_{A}}^{*}・・・(28)$$
xA:成分Aの溶液中のモル分率[-]
(28)式が成り立ちます。
(28)式を(27)式に代入すると、
$$μ_{A}(l)={μ_{A}(l)}^{*}+RT{\rm{ln}}x_{A}・・・(29)$$
(29)式となります。
(29)式が理想溶液における化学ポテンシャルで、溶液のモル分率から化学ポテンシャルを算出することができます。
化学平衡
化学平衡に化学ポテンシャルを適用することで、平衡定数Kがどのような関係式になるかを導くことができます。
仮に(30)式のような理想気体である物質A,B,C,Dに関する化学平衡反応が、等温定圧下で起こることを考えます。
$$aA+bB⇄cC+dD・・・(30)$$
等温等圧条件下の化学平衡状態では、反応系と生成系のギブス自由エネルギーが等しくなります。
$$G_{生成系}=G_{反応系}・・・(31)$$
化学ポテンシャルと(30)式の化学量論係数で(31)式を表わすと、
$$cμ_{C}+dμ_{D}=aμ_{A}+bμ_{B}・・・(32)$$
(32)式となります。
(32)式の各物質の化学ポテンシャルに(23)式を代入すると、
$$c{μ_{C}}^{o}+d{μ_{D}}^{o}-a{μ_{A}}^{o}-b{μ_{B}}^{o}=-RT{\rm{ln}}\frac{{P_{C}}^{c}{P_{D}}^{d}}{{P_{A}}^{a}{P_{B}}^{b}}・・・(33)$$
(33)式となります。
(33)式の左辺は標準状態における生成系と反応系の化学ポテンシャルの差となっており、これは標準ギブス自由エネルギー変化ΔGoを表わします。
また、右辺の対数の中身は平衡定数Kpと定義されます。したがって、
$$K_{p}=\frac{{P_{C}}^{c}{P_{D}}^{d}}{{P_{A}}^{a}{P_{B}}^{b}}・・・(34)$$
$$ΔG^{o}=-RT{\rm{ln}}K_{p}・・・(35)$$
(34)、(35)式となります。
また、(35)式を変形すると、
$$K_{p}={\rm{exp}}(-\frac{ΔG^{o}}{RT})・・・(36)$$
(36)式の形となります。
したがって、平衡定数を求めたいときは、標準状態におけるギブスエネルギー変化ΔGoを求めればよいことになります。
おわりに
化学ポテンシャルについて解説しました。
普段の業務でよく扱う相平衡、化学平衡の基礎的な概念です。実際には、さらに実在気体・実在溶液へと理論を拡張していきます。