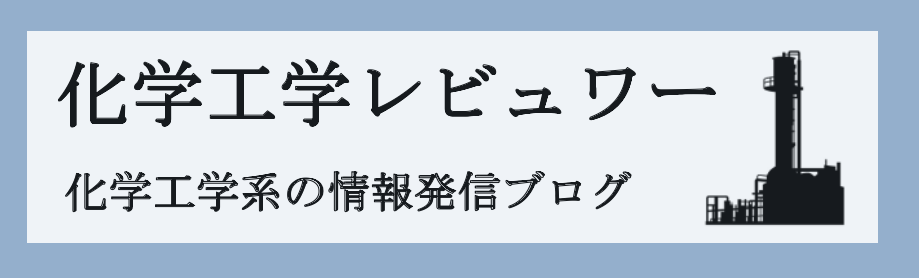概要
定圧変化における系のエネルギーや熱量を表わす状態量をエンタルピーといいます。
定圧変化における熱力学の第一法則を微分形で表すと、
$$δQ=dU+PdV・・・(1)$$
Q:熱量、U:内部エネルギー、P:圧力、V:体積
(1)式となります。
定圧変化であれば、dP=0となるため、
$$PdV=PdV+VdP=d(PV)・・・(2)$$
(2)式が成り立ちます。
(2)式を(1)式に代入すると、
$$\begin{align}δQ&=dU+d(PV)\\&=d(U+PV)・・・(3)\end{align}$$
(3)式となります。
ここで、(3)式の右辺の括弧内を新たに状態量Hを使用して
$$H=U+PV・・・(4)$$
(4)式で定義します。この(4)式がエンタルピーHの定義式です。
(4)式を(3)式に代入すると、
$$δQ=dH・・・(5)$$
(5)式となり、状態1から状態2まで積分すると、
$$Q=\int_{1}^{2}dH=H_{2}-H_{1}=ΔH・・・(6)$$
(6)式となります。
したがって、定圧変化においては、状態量ではない熱量Qを状態量であるエンタルピーの変化ΔHから算出することができます。
実際のプラントでは、定圧下で反応させたり加熱したりすることが多いので、エンタルピーは非常に重要な指標となります。
温度変化時のエンタルピーと熱量
エンタルピーを使用すれば、定圧条件下でどのくらいの熱量を与えれば物質の温度が変化するのか表すことができます。
ある圧力P一定条件下において、物質の温度をT1からT2まで変化させることを考えます。
温度T1、T2におけるエンタルピーをH1、H2とすると、単位質量当たりの熱量Q[kJ/kg]は、
$$Q=H_{2}-H_{1}=ΔH・・・(7)$$
(7)式のように状態1,2のエンタルピー差ΔHで表せます。
また、定圧比熱Cpの定義は(8)式となります。
$$C_{p}=(\frac{∂H}{∂T})_{p}・・・(8)$$
Cp:定圧比熱[kJ/(kg・K)]
(8)式を状態1から状態2まで積分すると、
$$H_{2}-H_{1}=\int_{T_{1}}^{T_{2}}C_{p}dT・・・(9)$$
(9)式となり、(9)式を(7)式に代入することで、
$$Q=\int_{T_{1}}^{T_{2}}C_{p}dT・・・(10)$$
(10)式となります。
定圧比熱Cpは通常、温度Tの関数になるため、Tについて積分することで熱量Qを求めることができます。
ただ、温度上昇が狭い範囲で、定圧比熱がほぼ一定とみなせる場合は、
$$Q=C_{p}(T_{2}-T_{1})・・・(11)$$
(11)式のように簡略化することができます。
相変化を含むエンタルピーと熱量
相変化のみ考慮
相変化によって温度が変化しない場合もエンタルピー変化で熱量を表わすことができます。
例えば、液体が気体に蒸発することを考えます。
液体のときのエンタルピーをHL、気体のときのエンタルピーをHVとすると、液体から気体への相変化に必要な熱量Qは、
$$Q=H^{V}-H^{L}=ΔH_{v}・・・(12)$$
ΔHv:蒸発潜熱[kJ/kg]
(12)式で表されます。
ΔHvを蒸発潜熱といい、別途推算式などを使用して値を求めます。
蒸発潜熱の推算方法については以下の記事で解説しています。
-

【蒸発潜熱】推算方法を解説:主要物質の実測値も記載
活量係数モデルで気液平衡を計算する場合には、蒸発潜熱の推算が必要になります。活量係数モデルは気液平衡計算モデルの中でも使用頻度が高いので、蒸発潜熱の推算法も知っておいた方が良いでしょう。
続きを見る
相変化と温度上昇を考慮
相変化と温度上昇の両方を含む場合でも同様にエンタルピー変化で熱量を表わすことができます。
ここでは温度0Kの固体を温度TKの気体まで加熱するときに必要な熱量Qを表わしてみましょう。
まず、温度0Kの固体のエンタルピーをHSとします。
続いて、温度TKの気体のエンタルピーHVは相変化と温度上昇を考慮し、
$$H^{V}=H^{s}+\int_{0}^{T_{s}}{C_{p}}^{S}dT+ΔH_{f}+\int_{T_{s}}^{T_{b}}{C_{p}}^{L}dT+ΔH_{v}+\int_{T_{b}}^{T}{C_{p}}^{G}dT・・・(13)$$
Ts、Tb:物質の融点、沸点[K]
CpS、CpL、CpG:固体、液体、気体の定圧比熱[kJ/(kg・K)]
ΔHf、ΔHv:融解潜熱、蒸発潜熱[kJ/kg]
(13)式で表されます。
したがって、熱量Qは変化前後のエンタルピー差を取り、
$$Q=H^{V}-H^{s}=\int_{0}^{T_{s}}{C_{p}}^{S}dT+ΔH_{f}+\int_{T_{s}}^{T_{b}}{C_{p}}^{L}dT+ΔH_{v}+\int_{T_{b}}^{T}{C_{p}}^{G}dT・・・(14)$$
(14)式で算出することができます。
理想気体のエンタルピー
理想気体では、状態方程式(15)式が成り立ちます。
$$PV=nRT・・・(15)$$
(15)式をエンタルピーの定義式(4)式に代入すると、
$$H=U+nRT・・・(16)$$
となります。
内部エネルギーUは温度の関数であり、PVの項も温度Tで置き換わりました。
したがって理想気体においては、エンタルピーHは圧力Pの依存性がなく、温度Tのみの関数となります。
温度Tのみでエンタルピーを決定できるのはかなり便利です。
例えばAspen Plus等のシミュレータでは、まず所定の温度における理想気体のエンタルピーを計算しています。
その後、理想気体からのエンタルピーのずれ(偏寄)を計算することで最終的な系のエンタルピーを決定しています。
化学反応におけるエンタルピーと熱量
化学反応は圧力一定で行われることが多く、生成した物質が膨張・圧縮します。
例えば物質が膨張して外部に仕事をすることで、反応系の持つエネルギーが減少してしまうため、加えるべき熱量Qは仕事分も考慮して決定する必要があります。
そこで、エンタルピー変化から熱量を決定することで、仕事を含めたエネルギーとして扱えるため非常に便利です。
化学反応によるエンタルピー変化を特に反応熱といいますが、関する法則としてHessの法則が挙げられます。
-

【Hessの法則】について解説:反応熱の計算
ある化学変化によって起こるエンタルピー変化量は、途中で様々な中間反応が起こったとしても最終的に同じ化学変化の状態に行き着くならばエンタルピー変化量は同じとなります。これをHess(ヘス)の法則といいます。
続きを見る
反応熱は反応前の物質と反応後の物質によって一意に決まり、反応途中の経路には無関係である、という法則です。
詳細は上の記事で解説していますが、この法則を利用することで様々な化学反応の反応熱を簡便に求めることができます。
また、Hessの法則で反応熱を扱う場合、通常は標準状態(1atm、25℃)で考えることが多いでしょう。
仮に、任意の温度T℃の反応熱を求めたい場合は、定圧モル熱容量Cpによる顕熱を考慮する必要があります。
任意の温度Tにおける反応熱をΔHT0とすると、
$$Δ{H_{T}}^{0}=ΔH_{A}+Δ{H_{298}}^{0}+ΔH_{B}・・・(17)$$
ΔHA、ΔHB:原料物質A、生成物質Bの温度変化に伴うエンタルピー変化[kJ/mol]
ΔH2980:標準状態における反応熱[kJ/mol]
(17)式で表すことができます。
温度変化によるエンタルピー変化は、
$$ΔH_{A}=\int_{T}^{298}C_{pA}dT・・・(18)$$
$$ΔH_{B}=\int_{298}^{T}C_{pB}dT・・・(19)$$
CpA、CpB:原料物質A、生成物質Bの定圧モル熱容量[kJ/(mol・K)]
(18)、(19)式で表されますから、(17)式に代入し整理すると、
$$Δ{H_{T}}^{0}=Δ{H_{298}}^{0}+\int_{298}^{T}(C_{pB}-C_{pA})dT・・・(20)$$
(20)式のように生成物質Bと反応物質Aの定圧比熱Cpの差からΔHT0を求めることができます。
定常流れにおけるエンタルピー

上図のような、ある定常流れにポンプで仕事W'を加え、熱交換器で熱量Qを加える場合のエネルギー収支を考えてみます。
定常流れに加えられた仕事W'と熱量Qは、
- 内部エネルギー:U
- 流れ仕事:PV
- 位置エネルギー:mgZ
- 運動エネルギー:mu2/2
以上の4つのエネルギーへと振り分けられます。
ここで流れ仕事PVとは、流体が流れるために必要な仕事です。
流体が流路の壁面に及ぼす圧力をP[N/m2]、壁面積をS[m2]とすると、流体が壁面に及ぼす力は、
$$P×S=PS・・・(21)$$
(21)式となります。
次に流体の流れる距離は、流体の体積をV[m3]とすると、V/Sとなります。
したがって、流体が壁面に及ぼす仕事は力×距離なので、
$$PS×V/S=PV・・・(22)$$
(22)式のようにPVとなります。
流体が流路を流れるためには、流体が壁面に及ぼす仕事PVに打ち勝つだけのエネルギーを与える必要があります。
したがって、流体の流れ仕事もPVとなります。
入口である状態1と出口である状態2でエネルギー収支を取ると、
$$\begin{align}Q_{12}+W_{12}'&=(U_{2}-U_{1})+(P_{2}V_{2}-P_{1}V_{1})+(mgZ_{2}-mgZ_{1})\\&+(\frac{1}{2}m{u_{2}}^{2}-\frac{1}{2}m{u_{1}}^{2})・・・(21)\end{align}$$
m:質量流量[kg/h]、g:重力加速度[m/s2]
(21)式となります。
ここで、エンタルピーの定義H=U+PVを使用すると、
$$\begin{align}Q_{12}+W_{12}'&=(H_{2}-H_{1})+(mgZ_{2}-mgZ_{1})\\&+(\frac{1}{2}m{u_{2}}^{2}-\frac{1}{2}m{u_{1}}^{2})・・・(22)\end{align}$$
(22)式となります。
したがって、定常流れに加えたエネルギーは、エンタルピー変化、位置エネルギー変化、運動エネルギー変化に利用されることがわかります。
また、これら3つのエネルギーの中では、通常はエンタルピー変化が圧倒的に大きな値となります。
例として、ある程度常識的なパラメータを与えて、単位質量当たりの各エネルギー変化[J/kg]を求めて比較してみます。
- 高低差ΔZ=10mのとき、位置エネルギー変化=98J/kg
- 流速u1=0.1m/s、u2=2m/sのとき、運動エネルギー変化≒2J/kg
- 水を10K温度上昇させるとき、エンタルピー変化≒41800J/kg
以上のように、圧倒的にエンタルピー変化の値がおおきく、他のエネルギー変化量はほとんど無視できるレベルです。
余談ですが流体力学の分野では、渦流れによる運動エネルギーの損失は最終的に熱となって消散するとされます。
しかし、消散した熱の分だけ流体が温度上昇するような計算はあまりしません。
前述したようにもともと流体が持っているエンタルピーが圧倒的に大きいので、ほとんどの場合で熱消散分のエネルギーは無視できるからです。
おわりに
熱力学における重要な用語の1つであるエンタルピーについて解説しました。
基本的に定圧変化を前提としていることを覚えておきましょう。