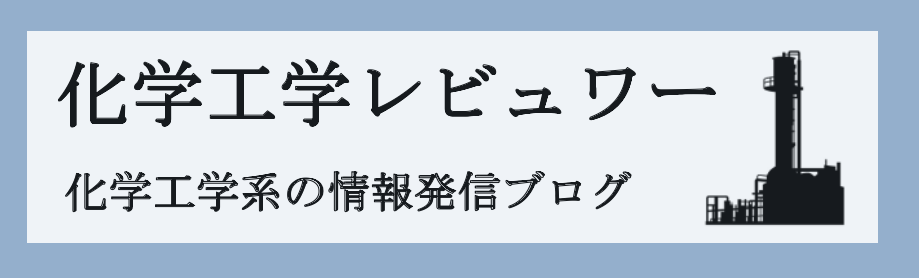概要
難溶性のガスについて、ガスの分圧と液中のガス濃度が比例する法則のことをHenryの法則といいます。
$$p_{A}=HC_{A}・・・(1)$$
pA:成分Aの分圧[Pa]、H:Henry定数[Pa m3/mol]、CA:成分Aの液中濃度[mol/m3]
一般にHenryの法則は(1)式で表されます。
また、(1)式をモル分率で表すこともでき、(2)式となります。
$$y_{A}=mx_{A}・・・(2)$$
yA:成分Aの気相モル分率[-]、m:Henry定数[-]、xA:成分Aの液相モル分率[-]
Henryの法則はガス吸収やガス放散において重要な考え方となります。
特にガス吸収の原理を説明するためのモデルの1つである、二重境膜説でHenryの法則は登場しますので覚えておきたいところです。
高濃度領域への拡張
(1)、(2)式は一般的に、溶解する成分Aの濃度が小さいときに成り立ちます。
成分Aの濃度が大きくなると、Henryの法則からずれてしまい適用できなくなります。
そこで、Henryの法則に活量係数を導入し一般化することで、高濃度領域でも使用できる式がLewisによって提案されています。
Henryの法則を一般化すると、圧力Pはフガシティーfで置き換えられます。
$$f_{A}=Hx_{A}・・・(3)$$
(3)式のままでは低濃度領域でしか成り立ちません。
ここで、新たにHenry基準の活量係数γ*を導入します。
$$f_{A}=Hγ^{*}x_{A}・・・(4)$$
(4)式において、高濃度領域でのずれを活量係数γ*が補正することで高濃度領域でもHenryの法則が適用できるようになります。
ちなみにHenry基準の活量係数γ*は気液平衡の活量係数γとは異なりますので混同しないようにしましょう。
しかし、実はHenry基準の活量係数と気液平衡の活量係数は深い関係にありますので後述します。
Henry定数とHenry基準の活量係数の算出
Henry定数は実測値が豊富ではありません。自分が計算したい系の実測値が存在することはほとんどないでしょう。
そこで、比較的実測値の多い気液平衡データからHenry定数を推算することができます。
加えて、前述したHenry基準の活量係数γ*も同様に推算することができますので紹介します。
Henryの法則を適用した場合の液相のフガシティーは(4)式で表されます。
$$f_{A}=Hγ^{*}x_{A}・・・(4)$$
一方でRaoultの法則を適用した場合の液相のフガシティーは(5)式で表されます。
$$f_{A}=f^{0}γx_{A}・・・(5)$$
(4)式と(5)式が等しいことから、
$$Hγ^{*}x_{A}=f^{0}γx_{A}$$
$$Hγ^{*}=f^{0}γ・・・(6)$$
となります。
xA→0のときは活量係数の補正なしでHenryの法則が成り立ちますから、γ*=1となります。
一方で気液平衡の活量係数については、xA→0のときは無限希釈活量係数γ0となります。
したがって(6)式は
$$H=f^{0}γ^{0}・・・(7)$$
となります。
低圧下ではフガシティーf0は成分Aの飽和蒸気圧と等しくなりますので、
$$H=P_{A}γ^{0}・・・(8)$$
(8)式となり、Henry定数は飽和蒸気圧と無限希釈活量係数から算出することができます。
また、(6)式に(7)式を代入すると、
$$f^{0}γ^{0}γ^{*}=f^{0}γ$$
$$γ^{*}=\frac{γ}{γ^{0}}・・・(9)$$
(9)式となり、Henry基準の活量係数γ*はγ、γ0から算出することができます。