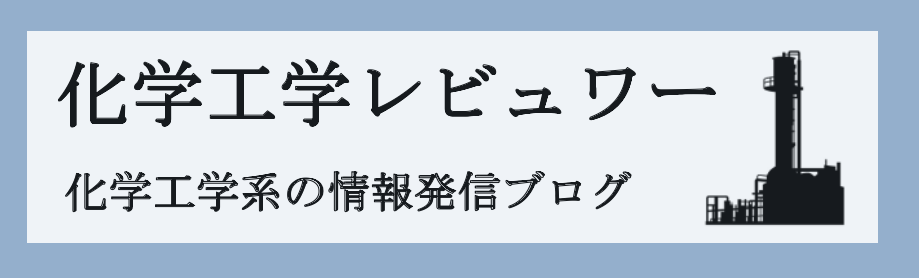概要
撹拌槽のスケールアップでは単位液量当たりの撹拌動力Pvを一定とする手法がよく使用されます。
これは撹拌槽の様々な特性が動力を基準として決定されることが多く、Pvを一定にしておけば不都合が生じにくいからです。
ただし、Pv一定のスケールアップはあくまでも撹拌という単位操作しか考慮していません。
撹拌反応槽では撹拌によって2液が混合し反応が進行しますが、Pv一定でスケールアップしたとしてもラボで得られた反応率やスペックを得られないことがあります。
これは混合速度に対する反応速度が相対的に大きい場合に生じやすく、撹拌のみを考慮したスケールアップでは対応しきれません。
この記事では撹拌反応槽におけるスケールアップで有効になり得る指標について解説します。
無次元数q
定義
化学工学社出版、高尾征治著の"反応系の撹拌混合技術"という参考書に無次元数qという指標が紹介されています。
$$q=\frac{k_{r}C_{0}[s^{-1}]}{m_{r}[s^{-1}]}・・・(1)$$
kr:反応速度定数[m3/(mol・s)]、C0:仕込み時の平均濃度[mol/m3]
mr:混合速度[1/s]
(1)式の分子は反応速度、分母は混合速度を表わしており、無次元数qは反応速度と混合速度の比となっています。
このqの値によって、反応と混合のどちらが律速となるか知ることができます。
qによる律速の判定
q<<1(反応律速系)
qが1より十分小さければ反応律速系になります。
(1)式から反応速度が遅く混合速度が速ければqが小さくなりやすいです。
撹拌槽の設計上、反応律速であることが最も望ましいです。
Pv一定でスケールアップすると混合時間が悪くなりますが、混合速度に対して反応速度が十分遅ければ、多少混合時間が悪化しても反応にはほとんど影響はありません。
加えて、反応速度が速いと原料の投入位置・方法等にも気を配る必要がありますが、反応速度が遅いとどのように投入しても同じ結果が得られるため、やはり反応律速系は設計が簡単です。
また、前述した参考書には、回分式反応器の場合は特に、
$$q≦0.1・・・(2)$$
(2)式の条件を満たすことで理想的な混合状態が達成されるとしています。
q≒1(反応混合競合系)
q=1に近いと反応混合競合系になります。
(1)式の反応速度と混合速度がほぼ同じ値となるとq≒1に近づきます。
撹拌槽の設計上、最も避けるべき状態です。
撹拌槽には速度分布も濃度分布も存在します。翼の周りの混合が速いところは反応律速となり、混合が遅いところは混合律速となり、槽内の局所で律速となる因子が異なります。
このような状態はスケールアップを考えると非常に難しいです。
一般的なPv一定のスケールアップでも速度分布や濃度分布まで同じにすることはできないので、スケールアップ前後で異なる反応率や転化率が得られる可能性が高いです。
対処法としては
- 回転数増加などで、系全体の混合速度を速くする
- 原料濃度を低くし、反応速度を遅くする
以上のような方法でqを小さくし反応律速に近づけることが挙げられます。
q>>1(混合律速系)
qが1より十分大きければ混合律速系になります。
(1)式から反応速度が速く混合速度が遅ければqが大きくなりやすいです。
撹拌槽の設計上、好ましくはないです。
しかし混合速度を速くするのも限界があり、ほぼ瞬間的に反応するような系では反応速度が速すぎるため混合律速となってしまいます。
ただ、考え方としてはわかりやすいです。混合速度=反応速度となっていますので、いかに混合速度を上げられるかが重要です。
- 回転数増加
- 翼径増加
- 原料投入位置を翼近傍に変更
例えば以上に示すような方法で混合速度を増加させることができます。
反応速度の算出方法
ここでは(1)式分子の反応速度をどう算出するかについて記載しています。
一次反応
撹拌槽を使用するような反応で、純粋な一次反応を扱うことは基本的にないです。
一次反応は基本的に
$$(-r_{A})=kC_{A}・・・(3)$$
(-rA):成分Aの反応速度[mol/(L・s)]、k:反応速度定数[s-1]、CA:成分Aの濃度[mol/L]
(3)式で表されるように、1種類の成分の濃度しか寄与しません。
2種類以上の液を混合させる必要があるから撹拌槽を使用するのであって、一次反応だとわざわざ撹拌槽を使用する必要がありません。
一次反応では管型反応器を使用することが多いでしょう。
二次反応
撹拌槽では二次反応を扱うことが多く、(4)式の形で表されます。
$$(-r_{A})=kC_{A}C_{B}・・・(4)$$
(-rA):成分Aの反応速度[mol/(L・s)]、k:反応速度定数[L/(mol・s)]
CA:成分Aの濃度[mol/L]、CB:成分Bの濃度[mol/L]
反応速度(-rA)自体の単位は単位体積・時間当たりの反応モル量[mol/(L・s)]で、(1)式分子の[s-1]とは異なります。
この単位の違いは無次元数qの導出過程にあるのですが、複雑なので本記事では割愛します。
(4)式を(1)式分子の形で表現するには、(4)式中の反応速度定数kと成分A,Bどちらかの濃度の積k×C[s-1]とすればよいです。
成分A,Bどちらの濃度にするかですが、その反応の律速となる成分を選択します。
2成分を混合して反応させる場合、どちらかの成分を過剰に投入するのが普通です。したがって、律速となり得るのは投入量が少ない成分の方です。
仮に成分Aを過剰に投入しているとすると、(1)式の分子はkCB[s-1]の値で計算します。
擬一次反応
2成分を混合して反応させていますが、反応速度は片方の成分の濃度の1乗に比例するような系を擬一次反応といいます。
擬一次反応は片方の成分が大過剰となっていて、反応が進行しても濃度変化がほとんど起きない場合等に当てはまります。
仮に成分Bが大過剰に投入され、擬一次反応とみなせる場合は、
$$(-r_{A})=kC_{A}・・・(3)$$
(-rA):成分Aの反応速度[mol/(L・s)]、k:反応速度定数[s-1]、CA:成分Aの濃度[mol/L]
一次反応と同様に(3)式で表すことができます。
この場合、(1)式の分子は反応速度定数k[s-1]の値で計算できます。
その他の反応次数
実際の反応では反応次数が整数とならない場合もあるかと思いますが、そのときの計算手法は現状確立されていません。
混合速度と比較できるように単位をs-1となるよう変形できるか別途考察が必要でしょう。
混合速度の算出方法
続いて混合速度の算出方法について解説します。
実験による算出
混合時間の測定
混合時間を測定して混合速度mrを算出する方法が挙げられます。
$$m_{r}=\frac{{\rm{ln}}(1/δ)}{t_{m}}・・・(5)$$
"反応系の撹拌混合技術"より引用
δ:濃度偏差のレベル[-]、tm:混合時間[s]
予め混合が完了したとみなせる濃度偏差のレベルδを設定しておき、その偏差に到達するまでの時間を測定します。
δの値は特に決まった値はありませんが、反応が十分に速い場合は濃度偏差1%程度(δ=0.01)でよいでしょう。
あとは(5)式を使用して混合速度mrを算出できます。
平均循環時間の測定
混合時間の測定よりも簡便な方法として、槽内の平均循環時間を測定する方法もあります。
液と同程度の密度の粒子を投入し、その粒子が循環する時間を測定します。
$$m_{r}=\frac{1}{t_{c}}・・・(6)$$
tc:平均循環時間[s]
"反応系の撹拌混合技術"より引用
槽内に基準となる検査面を設定します。その検査面を最初に通過してから、次に通過するまでの時間を測定します。
検査面はあまり粒子が通らないところに設置すると循環時間を長く見積もってしまうので、通常は翼の取付位置近傍に設定します。
あとは実験回数を重ねて、循環時間になるべく偏りがないくらいまでデータを取ってから平均循環時間を算出します。
(6)式から、平均循環時間の逆数が混合速度mrとなります。
推算式による算出
本来は実験で混合速度を算出するのが望ましいのですが、実験ができない場合もあります。
その場合は推算式で混合速度を算出します。
考え方は循環時間から混合速度を算出する(6)式とほぼ同様です。
$$t_{c}=\frac{V}{q_{c}}・・・(7)$$
V:液体積[m3]、qc:循環流量[m3/s]
理論的に(7)式で循環時間tcが算出できるので、同じように(6)式で混合速度mrを計算できます。
あとはどのように循環流量qcを決定するかですが、汎用的な撹拌翼のqcは循環流量数Nqcから計算できます。
$$N_{qc}=\frac{q_{c}}{nd^{3}}・・・(8)$$
$$N_{qc}=k・{n_{p}}^{0.7}(b/d)^{0.5}(d/D)^{0.1}(H/d)^{0.3}・・・(9)$$
k:定数、n:回転数[1/s]。np:翼枚数[-]、b:翼幅[m]
d:翼径[m]、D:槽径[m]、H:液高さ[m]
定数kは、
- k=1.3(パドル翼)
- k=1.1(ディスクタービン翼)
- k=0.82(ファウドラー翼)
以上の値が知られています。
また、式の適用範囲として、
- 0.25<d/D<0.45
- 0.1<b/d<0.4
- C1/D<0.5
以上の条件が挙げられます。C1は槽底から翼の取付位置までの高さです。
おわりに
反応速度と混合速度の比である無次元数qについて解説しました。
撹拌条件によって、反応率や製品品質が大きく変化する場合は混合律速となっている可能性が高いです。
無次元数qの指標を利用して、反応律速になるような条件を検討するのが有効な手段です。