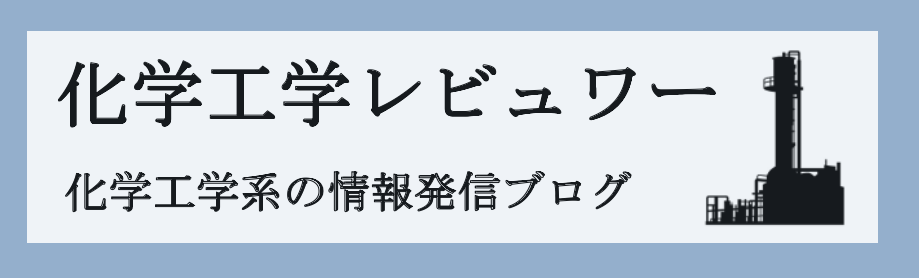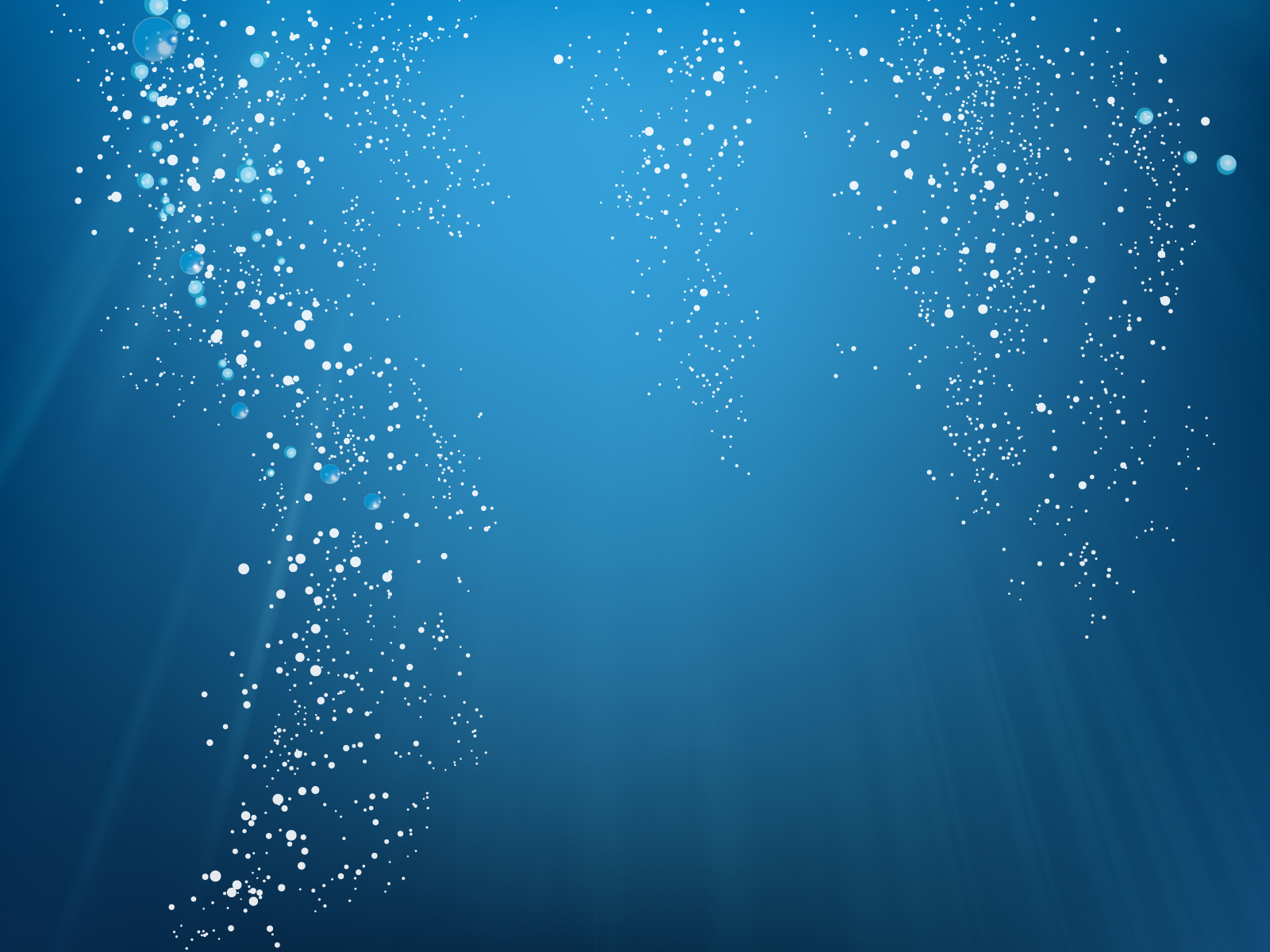物性の重要性
-

化学工学における物性定数推算法の重要性
化学工学という分野はプラントにある機器を設計するための学問であり世の中の産業に直接貢献できるため、非常に実用的である意味泥臭いイメージを多くの方が持っていると思います。自分で検討し設計したプラントが自分の検討通りに動いたときの感動はひとしおです。しかしその一方で最近感じるのがものづくりの現場とは程遠い化学物質の物性推算の重要性です。
続きを見る
物性推算手法
-

【気体密度】推算方法を解説:状態方程式・一般化圧縮係数線図による推算
この記事では気体密度の推算方法をおおまかに2種類に分けて紹介します。状態方程式による方法と一般化圧縮係数線図による方法の2種類です。
続きを見る
-

【液体密度】推算方法を解説:主要物質の実測値も記載
推算式も沸点においてのみ使用できる式から、臨界点以下の任意の温度で使用できるものまで様々です。この記事では主要な液体密度の推算方法を紹介します。
続きを見る
-

【純物質の蒸気圧】推算方法を解説:Antoine式が精度高い
蒸気圧とは気体と液体が平衡関係にある場合の気相の圧力のことで、化学プラントの装置設計においては非常に重要な物性です。特に蒸留塔のような2成分以上の混合物の気液平衡を扱う場合に、まず純物質の蒸気圧を算出する必要があります。
続きを見る
-

【比熱】推算方法を解説:分子構造や対応状態原理から推算
熱収支を計算するうえで最も重要な物性は比熱です。蒸気圧や蒸発潜熱はわからなくても場合によっては計算できますが、比熱がわからないと熱収支は計算できません。本記事では比熱の推算方法について紹介します。
続きを見る
-

【蒸発潜熱】推算方法を解説:主要物質の実測値も記載
活量係数モデルで気液平衡を計算する場合には、蒸発潜熱の推算が必要になります。活量係数モデルは気液平衡計算モデルの中でも使用頻度が高いので、蒸発潜熱の推算法も知っておいた方が良いでしょう。
続きを見る
-

【熱伝導度】推算方法を解説:フーリエの法則の比例定数
気体や液体の熱伝導度は主に熱流体解析をするうえで必要になってきます。熱伝導度はフーリエの法則で使用されているため、伝導伝熱の寄与に関係します。
続きを見る
-

【粘度】推算方法を解説:流体の流れやすさを示す指標
流動解析を実施する場合には粘度は最重要物性となりますので、粘度の推算法はある程度知っておいた方が良いでしょう。
続きを見る
-

【拡散係数】推算方法を解説:主要物質の実測値も記載
Fickの法則に使用されている係数を拡散係数Dといいます。この記事では主要な物質の拡散係数の実測値と、推算方法を紹介します。
続きを見る
-

【表面張力】推算方法を解説:主要物質の実測値も記載
表面張力は機器表面の濡れ性を考慮する際に必要となることがあります。例えば蒸留塔の詳細設計においては、充填物表面の濡れ面積を算出するのに表面張力が必要になります。充填物の濡れ性能は分離性能に大きく寄与するため、非常に重要な計算項目です。
続きを見る