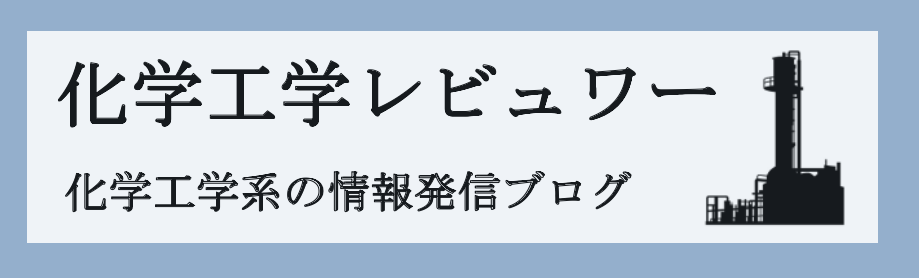概要
可逆反応では正反応と逆反応のどちらにも進行する可能性があり、ギブス自由エネルギーが小さくなる方向へ反応が進行します。
あるところでギブス自由エネルギーが最小となると、見かけ上反応が止まったように見えます。
この状態のことを平衡状態といい、平衡状態における各成分の関係を表わす定数を平衡定数Kといいます。
この記事では平衡定数の導出について解説しています。
高校までの平衡定数の導出
高校で習う平衡定数の導出について紹介します。
$$aA+bB⇄cC+dD・・・(1)$$
(1)式のような平衡反応を考えます。
平衡状態とは、(1)式の正反応と逆反応の反応速度が一致することを意味します。
したがって、
$$k{C_{A}}^{a}{C_{B}}^{b}=k'{C_{C}}^{c}{C_{D}}^{d}・・・(2)$$
CA,CB,CC,CD:各成分の濃度
k:正反応の反応速度定数、k':逆反応の反応速度定数
(2)式が成り立ちます。
また、平衡定数は正反応の反応速度定数kと逆反応の反応速度定数k'の比で表されるため、
$$K=\frac{k}{k'}=\frac{{C_{C}}^{c}{C_{D}}^{d}}{{C_{A}}^{a}{C_{B}}^{b}}・・・(3)$$
(3)式の関係が成り立ちます。以上が高校までの平衡反応の導出です。
結果的に平衡定数が(3)式で表されることは合っているのですが、導出でおいた反応速度式の仮定に無理があります。それは、
$$r=k{C_{A}}^{a}{C_{B}}^{b}・・・(4)$$
$$r'=k'{C_{C}}^{c}{C_{D}}^{d}・・・(5)$$
r,r':正反応、逆反応の反応速度
正反応、逆反応の速度についてそれぞれ(4),(5)式が成り立つとしている点です。
(4),(5)式は素反応であれば成り立ちますが、そうでなければ必ずしも成り立つとは限りません。
例えば有名な平衡反応で、(6)式の水素と臭素の反応があります。
$$H_{2}+Br_{2}⇄2HBr・・・(6)$$
上の導出に無理やり当てはめると、HBrの生成速度は、
$$\frac{dC_{HBr}}{dt}=k{C_{A}}^{a}{C_{B}}^{b}-k'{C_{C}}^{c}{C_{D}}^{d}・・・(7)$$
(7)式のような形になりそうですが、実際はそうはならず、
$$\frac{dC_{HBr}}{dt}=\frac{k_{1}{C_{H_{2}}}{C_{Br_{2}}}^{1/2}}{1+k_{2}{C_{HBr}}/{C_{Br_{2}}}}・・・(8)$$
(8)式のような複雑な形となることが知られています。
これは(6)式が全部で5つの素反応で構成されており、素反応を全て統合した結果、見かけ上(6)式のような反応にみえていることが原因です。
したがって、(1)式で表される正反応・逆反応が全て(4),(5)式のような化学量論係数を反応次数として使用した式で表されるという考えは間違っています。
ではなぜ平衡定数Kは(3)式の形になるのか、というのは高校では習わない化学ポテンシャルからの導出で説明できます。
化学ポテンシャルからの導出
次に、化学ポテンシャルを使用した導出を行ないます。
化学ポテンシャルは閉鎖系までしか適用できないギブス自由エネルギーの理論を開放系まで拡張した意味合いを持っています。
化学反応が平衡に達したとき、反応系と生成系の化学ポテンシャルが一致することを利用すれば平衡定数を導出できます。
また、ギブス自由エネルギーや化学ポテンシャルの値は絶対値はあまり意味はなく、基準となる状態からの相対値で議論されます。
標準状態時の成分iの化学ポテンシャルをμi0とした場合、任意の状態の成分iの化学ポテンシャルμiは
$$μ_{i}={μ_{i}}^{0}+RT{\rm{ln}}a_{i}・・・(9)$$
R:気体定数、T:温度、a:成分iの活量
(9)式で表されます。
ここで、aiは成分iの活量と呼ばれています。系が溶液系の場合、
$$a_{i}=γ_{i}C_{i}・・・(10)$$
γi:成分iの活量係数、Ci:成分iの濃度
活量aiは(10)式で表されます。
仮に系がRaoultの法則に従う理想溶液の場合、活量係数γiは1となり、(9)式は
$$μ_{i}={μ_{i}}^{0}+RT{\rm{ln}}C_{i}・・・(11)$$
(11)式に簡略化することができます。
ここで平衡反応に話を戻しますと、平衡時の(1)式の左辺と右辺の化学ポテンシャルは同じなので、
$$aμ_{A}+bμ_{b}=cμ_{C}+dμ_{D}・・・(12)$$
(12)式となります。
(12)式に成分A,B,C,Dの化学ポテンシャルを(11)式を参考にして代入すると、
$$-a{μ_{A}}^{0}-b{μ_{B}}^{0}+c{μ_{C}}^{0}+d{μ_{D}}^{0}=RT(a{\rm{ln}}C_{A}+b{\rm{ln}}C_{B}-c{\rm{ln}}C_{C}-d{\rm{ln}}C_{D})$$
$$-a{μ_{A}}^{0}-b{μ_{B}}^{0}+c{μ_{C}}^{0}+d{μ_{D}}^{0}=-RT{\rm{ln}}\frac{{C_{C}}^{c}{C_{D}}^{d}}{{C_{A}}^{a}{C_{B}}^{c}}・・・(13)$$
(13)式となります。この(13)式の右辺の対数内が平衡定数Kとなり、
$$K=\frac{{C_{C}}^{c}{C_{D}}^{d}}{{C_{A}}^{a}{C_{B}}^{c}}・・・(14)$$
(3)式と一致する式を導くことができました。
つまり、(1)式の化学量論係数a,b,c,dが平衡定数の次数になるのは、反応速度式の次数になるからではなく、化学ポテンシャルのバランスを考えた結果だということです。
また、(13)式の左辺をΔG0とおくと、
$$ΔG^{0}=-RT{\rm{ln}}K$$
$$K={\rm{exp}}(-\frac{ΔG^{0}}{RT})・・・(15)$$
(15)式となります。ちなみに、(15)式は質量作用の法則と呼ばれており、温度が一定ならば平衡定数Kが一定であることを示しています。
このように平衡定数Kは大学で習うギブス自由エネルギーや化学ポテンシャルなどの熱力学の観点から導出することができます。
おわりに
平衡定数Kについて解説しました。
反応速度式から平衡定数を考える癖がついていると、反応速度式の反応次数を間違えることがあります。気をつけましょう。