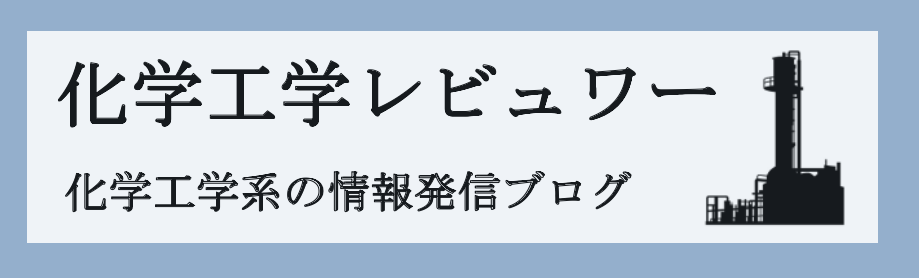概要
無次元混合時間ntMとは混合時間tM[s]に撹拌翼の回転数n[1/s]をかけて無次元化したものです。
無次元混合時間の値そのものにはあまり意味はなく、混合時間tMの算出に使用することが多いです。
乱流場(低粘度液)における無次元混合時間は
$$\frac{1}{nt_{M}}=0.092[(\frac{d}{D})^{3}N_{qd}+0.21(\frac{d}{D})(\frac{N_{p}}{N_{qd}})^{0.5}][1-{\rm{exp}}(-13(\frac{d}{D})^{2})]$$
上式がKamiwano et al. (1967)によって提案されています。
d:翼直径[m]、D:槽直径[m]、Np:動力数[-]、Nqd:吐出流量数[-]
層流場(高粘度液)における無次元混合時間は
$$\frac{1}{nt_{M}}=(9.8×10^{-5})(\frac{d^{3}}{D^{2}H})(N_{p}Re)$$
上式がMizushima et al. (1970)によって提案されています。
d:翼直径[m]、D:槽直径[m]、H:液高さ[m]、Np:動力数[-]、Re:撹拌レイノルズ数[-]
これらの式を使用して混合時間tMを求めることができます。
混合時間の算出意義
撹拌において混合時間とは性能そのもので重要な指標ではありますが、個人的には撹拌槽設計において混合時間の算出は重要視していません。
なぜなら撹拌槽のスケールアップにおいてよく使用されるPv=一定条件で混合時間を算出すると、スケールアップ後の混合時間はスケールアップ前より必ず悪くなるからです。
Pv一定条件での回転数の関係は
$$n_{2}=n_{1}(\frac{d_{2}}{d_{1}})^{-\frac{2}{3}}$$
となります。
この式から、スケールアップ後の回転数は必ずスケールアップ前より小さくなることがわかります。
一方で十分な乱流条件下では1/ntMは一定値となります。
$$n_{1}t_{M1}=n_{2}t_{M2}=一定$$
混合時間を同じにしようとするとtM1=tM2となり、
$$n_{1}=n_{2}$$
結果として回転数一定となります。
したがって、スケールアップ前後で混合時間を同じにしたい場合は、同じ回転数でスケールアップしなければなりません。
しかしPv=一定の場合はスケールアップ後の回転数は小さくなるので混合時間は長くなり悪化します。
"混合時間はスケールアップ前より悪くなります。"と言って、
上司にその撹拌槽の設計仕様が承認されるでしょうか?
ということで混合時間を推算式から算出しても上司を説得する材料にならない、という点で活用しづらい指標だと思っています。
とはいえおおよそどのくらいの時間で混合するかを知っておくことは重要なので、目安として算出はします。実機であればだいたい数十秒で混合すれば問題ない性能だと思います。
要求される混合時間
ここで、混合時間は悪くなるのになぜPv=一定のスケールアップがよく使用されているのかと疑問に思われる方がいるかもしれません。
それは実機サイズの撹拌槽で一般的に要求される混合時間が数十秒程度であり、スケールアップにより混合時間が長くなるといってもせいぜい数秒~数十秒の増加であるため問題ないからです。
実機の撹拌槽は最低でも数時間のスケールで運転されることが多いため、数十秒程度の混合時間の差異は誤差レベルです。
数秒の混合時間が要求される場合は、撹拌槽ではなく翼の回転速度が速いミキサーを選定した方がよいでしょう。
実験と推算式で混合時間を求めるのはどう違う?
推算式では混合時間しかわかりませんが、実験では混合時間以外にもどこが混ざりやすい、混ざりにくいという情報が得られる点が大きく違います。
特に均一混合で大事なのが滞留部(デッドスペース)の有無です。
撹拌槽のトラブルはたいてい滞留部を起点として起こるからです。
そのため、実験で混合時間を測定するのは非常に有用です。
実機で実験するのが難しければラボサイズにスケールダウンして実験してみるのも一つの手です。